
昨今、日本では、貯蓄型保険のニーズが高まっており、子供や孫の学資保険を検討する方が増えています。
特に、学資保険は、祖父母が契約者となって、孫の保険料を支払うことも可能なので、近年注目されている保険商材です。
しかし、祖父母が孫のために学資保険を契約する際は、親権者の同意・税金・契約形態など、注意しなければならない点があります。
本記事では、祖父母が孫のために学資保険を契約できるのかについてや、保険料を一括払いする際の「メリット」と「デメリット」を解説していきます。
学資保険とは

学資保険とは、契約者が毎月一定の保険料を支払うことにより、子供に必要な教育資金を計画的に積み立てられる「貯蓄型保険」のことです。
学資保険は、高校入学や大学入学など、大きな出費がある時に「祝い金」や「満期保険金」として、まとまったお金を受け取れるため、ライフイベントに備える保険として活用されています。
また、学資保険は、貯蓄だけでなく保障機能も兼ね備えており、契約者に万一のことが起きたら保険料の支払いが免除されて、子どもの教育資金が確保される安心感も得られます。
一方で、学資保険は、返戻率によって受取総額が変わるため、加入時期が早いほど有利になり、家計への負担を抑えながら、効率的に資金を増やせる可能性が高いです。
さらに、学資保険は、リスクを抑えながら確実に資金を準備できる保険として注目されており、銀行の積立や投資商品と比較して受取時期が明確で、計画を立てやすいことから人気があります。
学資保険とは、子どもの成長に合わせて、確実に資金を積み立てられる保険商品であり、教育資金の不安を減らしながら、将来の教育費を無理なく蓄える有効な選択肢です。
祖父母が孫のために学資保険を契約できるのか

祖父母が孫のために学資保険を契約できるのかについては、多くの保険会社で可能とされています。
学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備するための貯蓄型保険ですが、契約者が必ずしも親である必要はなく、祖父母が契約者として保険料を支払う形でも加入できます。
祖父母が孫のために学資保険を契約する場合は、被保険者として孫を登録し、保険料を支払う形になります。
満期保険金や祝い金は、孫のために設定された口座や名義で受け取ることができるので、教育費の準備を祖父母の意思で行うことができます。
また、契約時には、被保険者である孫の同意は不要ですが、契約内容や受取方法について、親の了承を得ておくことが望ましいとされています。
孫の学資保険を一括払いすることは可能なのか

多くの保険会社では、契約形態として孫の学資保険を一括払いすることも可能で、総支払額をまとめて納めることができます。
孫の学資保険を一括払いする場合は、祝い金や満期保険金があらかじめ確定したり、分割払い(月々の支払い)に比べて、返戻率が高く設定されるケースが多く、長期的に見て効率的に教育資金を増やせます。
さらに、孫の学資保険を一括払いした際には、契約者(祖父母)に万一のことがあっても、契約は有効であり、予定通り満期や入学時に資金を受け取れるため、教育費の確実性を確保できます。
孫の学資保険を一括払いするメリット

孫の学資保険を一括払いするメリットは、契約時に保険料をまとめて支払うことで、将来の教育資金を効率良く準備できるところです。
本来、学資保険は、子どもの進学に備えて、計画的に資金を積み立てる保険商品ですが、一括払いを選択することで、分割払いにはない複数の利点を得ることができます。
ここからは、孫の学資保険を一括払いするメリットについて、わかりやすく解説していきます。
返戻率が高くなる
返戻率とは、支払った保険料の総額に対して、満期時や各種祝い金として受け取れる「金額の割合」を示す指標であり、この数値が高いほど資金効率に優れた契約です。
例えば、分割払いは、年月をかけて少しずつ保険料を支払うため、資金の運用開始が遅くなり、返戻率が低めに設定される傾向があります。
一方で、一括払いは、まとめて保険料を支払うため、保険会社が早い段階から長期的な資金運用を行えるので、契約者に対してより高い返戻率を提供できます。
また、一括払いでは、支払い回数が一度で済むため、総支払額が抑えられ、結果として受取額とのバランスが良くなります。
保険料の割引がある
分割払いは、毎月または毎年の入金を待つ必要があるため、保険会社にとって資金の確保や、運用が不安定になりがちです。
しかし、一括払いであれば、契約初期に全額入金されるため、保険会社の運用コストが抑えられて、その分を契約者への割引として還元できる仕組みになっています。
孫の学資保険を一括払いする際は、総支払額の軽減だけでなく、返戻率の向上にも繋がるので、受取金額の割合が高くなり、効率的に教育資金を積み立てることが可能です。
払い忘れ(滞納)の心配がない
一括払いは、以後の支払い管理や手続きが不要になるため、毎月の口座引き落としや振込の手間がなくなり、家計管理の負担も軽減できます。
また、一括払いは、払い忘れや残高不足による滞納リスクを完全に回避できるので、支払いに対する心配がありません。
特に、祖父母が契約者になる場合は、高齢になっても毎月支払い手続きを行う必要がないため、将来的な心配をせずに済みます。
さらに、一括払いは、契約者(祖父母)に万一のことがあっても、保険料の支払いが完了しているため、孫の教育資金が予定通り受け取れます。
相続税の課税対象を生前に減らせる
相続税の課税対象を生前に減らせることは、資産管理と将来の税負担軽減を考える家庭にとって、大きなメリットになります。
支払い済みの保険料は、契約者の財産から除外され、相続税の課税対象を減らすことが可能です。
これは、現金や預金のまま財産を残す場合に比べて、続時に課税される財産が減少し、結果として相続税の負担を軽減できます。
さらに、保険契約を通じて孫に資産を移転することになるため、教育資金を確保しながら計画的に資産を移すことができます。
また、一括払いは、分割払いとは異なり、支払いが完了した時点で資金の移転が完了するので、相続税の対策にもなります。
孫の学資保険を一括払いする際のデメリット
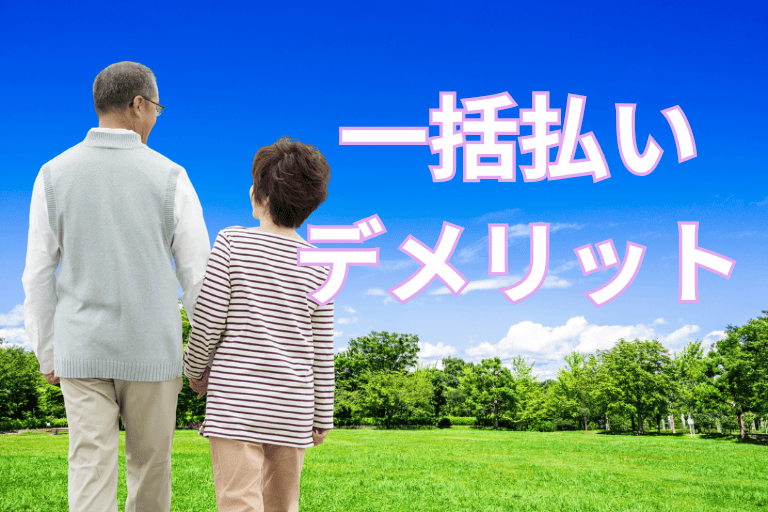
学資保険を一括払いする際は、契約時にまとまった資金を支払う必要があるため、家計への負担が大きくなります。
学資保険は、教育資金を計画的に積み立てるための保険ですが、一括払いを選択すると支払い額が高額になるため、生活資金や老後資金とのバランスを考えることが大切です。
ここからは、孫の学資保険を一括払いする際のデメリットについて、わかりやすく解説していきます。
まとまった資金が必要になる
学資保険の一括払いは、契約時に数十万円から数百万円を支払わなければならず、十分な貯蓄がなかったり、その他の出費が重なるタイミングで、家計の負担になる可能性があります。
特に、祖父母が契約者になるケースでは、先に老後資金や生活費を確保してから、一括支払いを行った方が安心感があり、無理のない範囲で資金を準備することが大切です。
特に、一括払いは、支払った金額を保険会社に長期間預ける形になるので、急な出費や予期せぬトラブルに対応しにくい点が懸念されます。
分割払いであれば、毎月少しずつ支払えるため、残りの資金を生活費やほかの投資に活用しやすく、自由に使えるお金が一気に減ることを避けられます。
生命保険料の控除を1度しか受けられない
生命保険料の控除とは、生命保険や学資保険などの払い込み保険料に応じて、所得税や住民税が軽減される制度で、多くの方が節税対策として利用されています。
しかし、一括払いを選択した場合は、保険料が契約時にすべて計上されるため、控除が受けられるのは支払った年の1回のみとなり、毎年の節税効果を得ることができません。
控除が1度しか適用されないことは、分割払いや年払いと比較した際に、大きなデメリットになります。
例えば、分割払いであれば、毎年保険料を支払うため、そのたびに、生命保険料の控除対象にすることが可能です。
特に、所得税や住民税の負担が大きい世帯では、この控除を毎年受けられるメリットが大きく、節税機会を失ってしまう点について、慎重に考慮しなければなりません
インフレに対応できない
学資保険は、将来の学費を計画的に積み立てるための保険商品ですが、一括払いだと契約時に受取額が固定されるため、物価の上昇が続いた場合に、実質的な受取価値が目減りする可能性もあります。
本来であれば、インフレ時には、物価の上昇に合わせて、資産の価値も増やす運用が望ましいのですが、一括払いで支払った保険料は受取時まで引き出すことができず、運用方法も保険会社に委ねられます。
その結果、学資保険を一括払いするケースでは、長期間にわたって保険料が運用されるものの、支払った金額が固定されるため、物価の上昇スピードに保険の運用益が追いつかず、実質的な資産価値が目減りする恐れがあります。
そのため、学資保険の一括払いは、契約後にインフレが進行し、物価や教育費が上昇してしまうと、受け取る満期金では十分に教育費をまかなえない可能性が高いのです。
孫の学資保険を契約する際の注意点
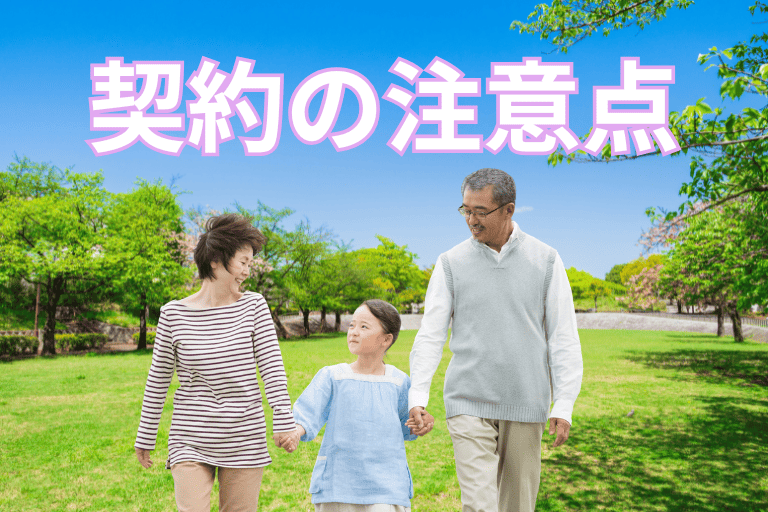
孫の学資保険を契約する際は、教育資金を確実に準備するためにも、契約前にいくつかのポイント確認しておくことが大切です。
ここからは、孫の学資保険を契約する際の注意点について、わかりやすく解説していきます。
祖父母の年齢や健康状態の確認が必要
祖父母の年齢や健康状態ついては、契約の可否・保険料・保障内容に直結するので、契約前に確認しておく必要があります。
多くの学資保険では、契約者の年齢に上限が設けられており、年齢が高くなるほど加入が難しくなったり、保険料が割高になる傾向です。
そのため、孫の学資保険を契約する際には、希望する保険会社の契約条件を事前に確認し、無理のない支払い計画を立てることが重要です。
加えて、学資保険は、貯蓄性の高い商品ですが、契約者に対して簡単な健康告知を求める場合もあります。
持病や通院歴がある場合は、告知内容によって加入を断られる可能性があるため、正確に申告しなければなりません。
健康状態によっては、審査に時間がかかったり、契約が難しくなったりする場合もあるので、早めの準備がスムーズな契約に繋がります。
- どのプランに加入できるのか
- 何歳まで支払うことになるのか
- 持病や通院歴の告知について
110万円を超えると贈与税の課税対象
日本では、年間110万円までの贈与は非課税となるため、110万円以内であれば税金はかかりません。
しかし、祖父母が110万円を超える孫の保険料を支払った場合は、その超過分が贈与税の対象になる可能性があるため、注意が必要です。
(保険金 − 基礎控除110万円)× 税率 − 控除額 = 贈与税
また、学資保険は、契約者と被保険者・受取人の関係によって、贈与税の課税対象になるかどうかが変わります。
- 誰が契約者か
- 誰が保険料を負担しているか
- 誰が満期金を受け取るのか
親権者からの同意が必要
学資保険は、未成年者を被保険者とする契約であるため、孫であったとしても、親権者の同意なしに契約をすることが原則できません。
なぜならば、学資保険は、子どもに関わる財産や権利に影響する契約なので、親権者の同意を得ることが法的に定められているからです。
保険会社によっては、契約手続きの段階で、親権者の署名や承諾書の提出必要になるため、事前に必要書類を確認しておくとスムーズに契約できます。
孫との同居や扶養の証明が必要
学資保険は、未成年を被保険者とする契約であるため、保険会社によっては「契約者と孫が同居をしているか」や「契約者が孫を扶養しているか」について、証明を求めることがあります。
この確認は、契約の正当性を担保すると共に、将来的に保険金の受取や、税務上のトラブルを防ぐために重要です。
- 住民票
- 扶養控除等(異動)申告書
- 所得証明書
加入年齢によって保険料が高額
学資保険は、契約者や被保険者の年齢にあわせて、保険会社がリスクを計算するため、加入時の年齢が高くなるほど、保険料が割高になる傾向です。
特に、祖父母が契約者になる場合は、加入年齢が高いと長期にわたる保険料の負担が増え、家計に影響を及ぼす可能性があるので、慎重に検討する必要があります。
また、学資保険は、同じ保険内容でも加入時期によって保険料に差が生じるため、早めに加入をすることで、月々の保険料を抑えながら、長期的な積み立てが可能です。
祝い金と満期金が税金(課税)の対象
学資保険は、教育資金の準備に役立つ一方で、祝い金や満期金を受け取る際の税金が複雑で、契約形態によって課税される税金が異なります。
学資保険では、契約者・被保険者・受取人の関係によって、所得税・贈与税・相続税のいずれかが課税される可能性もありますが、原則として元本部分(支払った保険料の総額)には税金がかかりません。
例えば、契約者が祖父母で受取人が孫の場合は、祝い金や満期金が祖父母から孫への贈与とみなされ、贈与税の課税対象になることがあります。
また、契約者が親で受取人が子どもの場合には、満期金の利息部分が雑所得になり、所得税の対象になるケースもあります。
孫の学資保険を検討する際は、契約者と受取人の設定を慎重に行い、必要に応じて税理士やFP(ファイナンシャルプランナー)に相談することで、より確実で安心した契約が可能です。
祖父母が死亡した場合
一般的に、契約者が死亡した場合には、その時点で保険の契約が相続財産として扱われ、相続人が新たに引き継ぐための手続きを行う必要があります。
相続手続きには、戸籍謄本や相続関係を証明する書類が必要となり、手続きが複雑になることも多いため、家族間で事前に話し合っておくことが望ましいです。
また、一部の学資保険では、契約者が死亡した場合に「保険料払込免除特約」が適用され、以後の保険料が免除されながら、満期金や祝い金を予定通り受け取ることができます。
しかし、この特約は、全ての契約に自動で付帯しているわけではなく、加入時に設定が必要な場合もあるため、契約前に必ず確認すべきです。
保険料払込免除特約が付いていない契約では、契約者が死亡すると、家族が保険料の支払いを続けなければならず、家計への負担が大きくなることがあります。
特に、祖父母が高齢で持病がある場合は、契約が途中で継続できなくなるリスクを考慮し、誰が保険料を支払って、誰が契約を継続するのか明確にしておくことが大切です。
孫のための学資保険をプロが無料でご紹介
孫の学資保険にかかる税金の種類

孫の学資保険にかかる税金の種類については、受取人・契約者・保険料負担者の関係や、受取方法によって「所得税」「贈与税」「相続税」が適用されるため、契約前に正しく理解しておく必要があります。
| 学資保険の給付金を受け取る人 | 税金の種類 |
|---|---|
| 契約者 | 所得税 |
| 孫または孫の親 | 贈与税 |
| 別の相続人 | 相続税 |
受取額から払込保険料と特別控除(最高50万円)を差し引いた残額の半分が課税対象(一時所得)
※年金形式で受け取る場合は雑所得
暦年課税の基礎控除110万円を超える部分に贈与税がかかる可能性あり
孫の学資保険についてまとめ

本記事では、祖父母が孫のために学資保険を契約できるのかについてや、保険料を一括払いする際の「メリット」と「デメリット」を詳しく解説してきました。
祖父母が孫のために学資保険を検討する際は、親権者の同意が必要であったり、祝い金と満期金が税金の対象になるのかなど、いくつかの注意点を念頭に置いておく必要があります。
お孫さんの学資保険を検討中の方は、35社以上の保険会社を取り扱っていて、保険業界のプロフェッショナルが多数在籍している「保険のぷろ」までご相談ください。
保険のぷろでは、お孫さまにおすすめの学資保険をランキング形式でご紹介しています。







