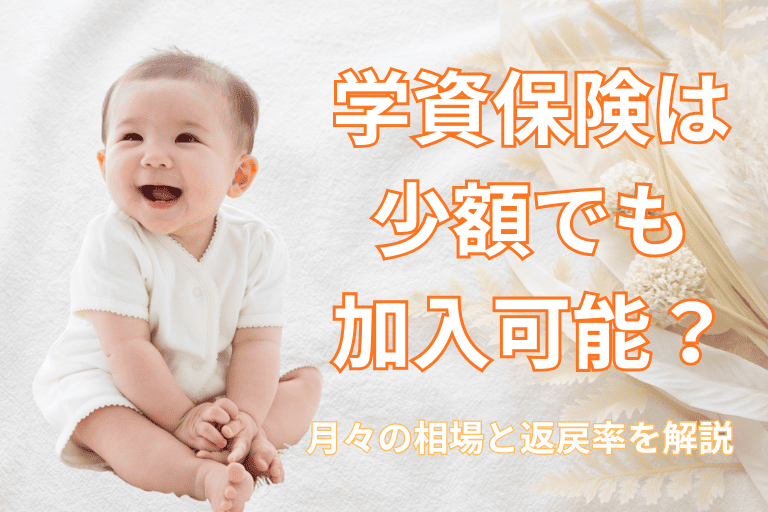
近年、日本では、所得制限なしで公立高校の授業料無償化が進むなど、教育の支援制度が拡充してきています。
一方で、お子さまがいるご家庭では、習い事や塾代の高騰が続き、将来の資金準備について、不安を抱える親御さんも少なくありません。
学資保険は、定期的な積立によってお金を貯められるため、将来の教育費に対する悩みを解消しやすく、少額から契約することも可能です。
本記事では、少額でも契約可能な「子どもの学資保険」について、詳しく解説していきます。
子どもの学資保険は少額でも加入可能

子どもの学資保険は、家計に負担をかけず、少額から加入できる保険商品であることから、昨今人気があります。
学資保険は、月々の保険料を自由に設定できる商品が多いため、無理のない範囲で、計画的に教育資金を積み立てることができます。
特に、少額の学資保険は、月2,000円前後からスタートできるプランもあり、出費がかさむ子育て初期でも安心して加入できる点が魅力です。
平均的な月々の保険料
現在の学資保険では、月々の保険料が5,000円〜15,000円前後が平均的な相場で、家計の状況に合わせて柔軟にプラン設定が可能です。
また、学資保険の平均的な保険料は、加入する年齢や満期時の受取額によっても変動するため、あらかじめ理解しておく必要があります。
例えば、出生直後に加入した場合は、積立期間が長くなるので、同じ満期金でも月々の保険料を低く設定できます。
一方で、入園・入学のタイミングで加入した場合は、積立期間が短くなるため、平均よりも月額保険料が高くなる傾向です。
このように、平均的な月々の保険料は、加入時期によっても大きく変わるので、平均額を基準に月々の保険料をシミュレーションし、家計に負担をかけない現実的なプラン設計が大切です。
保険料払込期間
保険料払込期間とは、保険料を支払う期間のことで、支払期間の長さや支払方法によって、月々の負担や満期時の受取金額に大きく影響します。
そのため、学資保険の保険料払込期間は、家計の負担を最小限に抑えながら、教育資金を効率的に準備するための重要ポイントです。
学資保険には、保険料払込期間が複数存在し、18歳払込・10歳払込・短期払込タイプなどが用意されており、家庭のライフプランに合わせて選択できます。
特に、払込期間を長く設定した場合は、月々の保険料を抑えやすく、家計への影響を最小限に抑えることが可能です。
- 積立期間が長くなる
- 月々の保険料の負担が少額
- 家計に無理なく教育資金を準備
- 契約者の収入状況やライフプランも踏まえて検討
一方で、払込期間を短く設定した場合は、返戻率が高くなる傾向で、完済後は満期を待つだけです。
- 早期に保険料を完済
- 保険料の負担が短期集中
- 早めに支払いが終わる安心感
- 返戻率の高さから人気
満期学資金の平均額
満期学資金とは、満期を迎えた際に受け取れるお金のことで、子どもの入学や進学資金として活用されます。
学資保険は、家計に負担がかからずに少額から加入可能で、月々の保険料や払込期間に応じて満期額が変動します。
一般的に、満期学資金の平均額は、100万円〜300万円程度とされており、家庭の資金計画に応じて、無理なく設定することが可能です。
例えば、学資保険は、月々5,000円から始める少額プランでも、長期にわたって積立を行うことにより、100万円前後の満期金を準備できます。
一方で、月額1万円以上の短期払込は、返戻率が高くなり、満期学資金が200万円以上に達することもあります。
また、多くの学資保険は、満期金を一括で受け取るだけでなく、入学時や進学時に分割して受け取れるプランがあるため、必要なタイミングで学資金を準備できます。
返戻率と利率の関係
返戻率とは、満期や入学時に受け取れる割合の数値で、契約者が支払った保険料に対して、100%を超えると支払額よりも多く受け取れます。
一方で、利率とは、保険会社が資金を運用する際の「利回り」のことで、利率が高ければ高いほど、同じ保険料でも満期時に受け取れる金額が増えるため、効率的な資金運用が可能になります。
例えば、短期払込で早めに保険料を払い終えると、満期まで利息が効率よく加算されるので、返戻率が向上します。
逆に、長期払込では、月々の負担が少額であることから、返戻率がやや低めになるため、家計とのバランスをみながら判断することが必要です。
- 保険料の5%が加算されるため少額からでも効率よく運用可能
- 少額でも利率や返戻率の高い商品を選ぶと十分な学資金を確保できる
返戻率の計算方法
返戻率(%)= 受取総額(祝い金 / 満期保険金)÷ 払込保険料の総額 × 100
保険料払込免除付帯の有無
保険料払込免除とは、契約者である親(祖父母)が「死亡」または「高度障害状態」になった際に、以降の支払いが免除される保障のことです。
この保障が付帯されている学資保険では、親(祖父母)に万一の事態が起きても、保険契約がそのまま継続され、満期時には学資金を受け取ることができます。
払込免除が付いた学資保険であれば、保険会社が残りの保険料を肩代わりするため、子どもの教育資金が確実に確保されます。
この点は、学資保険が単なる貯蓄よりも優れているところです。
一般的に、払込免除が付帯されているプランは、付帯なしに比べて月々の保険料が高くなったり、返戻率も若干低くなる傾向ですが、万一を考えれば十分なメリットがあります。
子どもの教育にかかる費用

子どもの教育にかかる費用は、幼稚園から大学まで長期間にわたって発生し、学校の種類によって負担額が大きく異なります。
幼稚園の入学から高校卒業
| 公立 | 私立 | |
|---|---|---|
| 幼稚園(3年) | 230,000円 (総額 690,000円) |
500,000 (総額 1,500,000) |
| 小学校(6年) | 320,000 (総額 1,920,000円) |
930,000 (総額 5,580,000) |
| 中学校(3年) | 480,000 (総額 1,440,000円) |
1,300,000 (総額 3,900,000) |
| 高校(3年) | 520,000 (総額 1,560,000円) |
1,000,000 (総額 3,000,000) |
※文部科学省調査などの一般的な平均額をもとに算出
大学入学から卒業
| 入学金 | 授業料 | 施設費など | 4年間の総額 | |
|---|---|---|---|---|
| 国立 | 282,000円 | 535,800円 | 50,000円 | 2,676,200円 |
| 公立 | 390,000円 | 540,000円 | 80,000円 | 2,930,000円 |
| 私立(文系) | 260,000円 | 900,000円 | 120,000円 | 4,240,000円 |
| 私立(理系) | 260,000円 | 1,200,000円 | 150,000円 | 5,260,000円 |
※文部科学省調査などの一般的な平均額をもとに算出
子どもの学資保険を少額で加入するメリット

子どもの学資保険を少額で加入するメリットは、家計への負担を抑えながら、教育資金を計画的に準備できるところです。
学資保険は、子どもに必要な教育費をサポートする商品ですが、一括払いする必要がないため、少額で加入することによって、月々の保険料を抑えつつ、無理なく長期的な積立をスタートできます。
子どもの学資保険を少額で加入する際のデメリット

子どもの学資保険を少額で加入する際のデメリットは、家計の負担を抑えられる一方で、将来の教育資金が不足しやすい点です。
少額で学資保険に加入する際は、将来の教育費を考慮しながら、必要に応じた貯蓄方法を組み合わせるなど、計画的な資金準備が必要になります。
ここからは、子どもの学資保険を少額で加入する際のデメリットについて、詳しく解説していきます。
想定よりも満期金が少ない
子どもの学資保険を少額で加入する際のデメリットは、積立総額が小さくなることで、受け取れる学資金が想定よりも少ない可能性が高いことです。
学資保険は、長期間にわたって資金を積み立てる商品であり、月々の支払額が低ければ低いほど、積立総額も小さくなるため、満期金で学資金を賄えないリスクがあります。
返戻率が低い
子どもの学資保険を少額で加入する際のデメリットは、返戻率が期待よりも低くなる可能性があることです。
少額で加入した場合は、月々の保険料を低く設定できるものの、払込期間が長くなることが多く、結果として効率の良い資産形成が難しくなるケースもあります。
そのため、少額の学資保険は、返戻率が低いと、長期間運用していても実質的な増え方が小さく、資金準備の効果を十分に得られません。
保障内容を変更する際に制限がある
子どもの学資保険を少額で加入する際のデメリットは、保障内容が制限されやすく、変更する時に制限がつく場合もあります。
例えば、少額プランでは、受取額を高くするプランに変更できないケースがあり、新たに加入し直さなければなりません。
また、途中加入の場合は、返戻率が下がることもあるため、結果として効率的な資金準備が難しく、別の貯蓄方法を追加する必要性が生じてきます。
インフレによる影響を受けやすい
子どもの学資保険を少額で加入する際のデメリットは、インフレリスクに対応できず、物価の影響を受けやすい点です。
教育費は、物価の上昇と共に増加する傾向があり、契約時には十分と思える受取金額でも、進学時に不足してしまうことがあります。
少額の積立では、物価上昇分に追いつかない可能性が高く、貯蓄や投資で不足分を補うケースも多くみられます。
学資保険を契約する際の注意点

学資保険は、長期間にわたって積み立てる商品であることから、返戻率が高いか低いかで、将来受け取れる満期金が異なります。
仮に、返戻率が100%を下回る場合は、実質的に損(元本割れ)をしてしまう可能性があるため、複数社のプランを慎重に比較し、効率よく教育資金を増やせる商品を選ぶことが大切です。
ここからは、学資保険を契約する際の注意点について、詳しく解説していきます。
短期間での解約
学資保険は、長期間にわたって教育資金を積み立てる保険商品のため、加入から数年以内に解約すると、支払った保険料に対して、戻ってくる金額が大幅に少ない場合があります。
特に、加入初期は、保険会社の諸経費が多く差し引かれることから、短期間での解約は大きな損失に繋がりやすいので、注意する必要があります。
そのため、加入前には、家計に無理のない保険料で設定できているか、ライフプランに沿った払込期間になっているかを確認することが大切です。
育英年金(養育年金)付き商品
育英年金は、契約者である親が死亡または高度障害になった際に、毎月一定額の年金が子どもに支払われる仕組みで、学資金だけではカバーしきれない日常生活費や教育費の補填として役立ちます。
特に、一人親家庭では、経済的なリスクに対する備えとして人気があり、子どもが成長する過程で必要な資金を安定的に確保できる点が魅力です。
しかし、育英年金が付帯される場合は、月々の保険料が通常の学資保険よりも高くなる傾向があり、家計に無理のない範囲で支払えるかをシミュレーションする必要があります。
育英年金付きの商品を選ぶ際には、教育資金を効率的に準備することを優先するのか、保障を優先するのかを明確にして、家庭のライフプランに沿った選択を行うことが大切です。
契約者によって保険料が変わる
学資保険の保険料は、契約者の年齢・性別・健康状態によって、大きく変動することがあります。
一般的に、保険料は、契約者の年齢が若いほど安く抑えられて、年齢が上がるほど高くなる傾向です。
また、学資保険の保険料は、男女によって異なる場合もあるため、どの契約者名義で契約するかを慎重に検討する必要があります。
さらに、学資保険の契約者選びでは、契約者の健康状態(持病や病歴)によって、加入時に告知が必要なケースも存在します。
告知内容によっては、保険料が割増になる場合や、加入自体が制限されることもあるため、家族の健康状態を確認しておくことが大切です。
月々の保険料を安くするポイント

月々の保険料を安くするポイントは、学資保険の選び方や契約条件を工夫して、少額で加入することです。
学資保険は、長期間にわたって支払いを続ける必要があるため、毎月の保険料が高いと家計への負担が大きくなります。
効率的に教育資金を積み立てるためには、月々の保険料を抑えつつ、長期的に無理なく継続できる設計が重要です。
ここからは、月々の保険料を安くするポイントについて、詳しく解説していきます。
同じ保険会社で他の商品と組み合わせる
多くの保険会社では、複数の商品(生命保険や医療保険など)を同時に契約することで、まとめ割や家族割を提供しています。
この仕組みは、学資保険を単体で契約するよりも、月々の保険料を抑えられて、家計に無理のない支払い計画を立てることが可能です。
また、同じ保険会社で他の商品と組み合わせることは、割引によって保険料が安くなるだけではなく、契約管理を一元化できるため、契約内容や支払管理をまとめて確認できます。
さらに、保険会社によっては、契約件数に応じて返戻率や特典が優遇されるケースもあり、長期的に家計への負担を軽減する効果も期待できます。
できるだけ早いうちに加入する
学資保険は、長期にわたって教育資金を積み立てる保険であるため、契約者の年齢が若ければ若いほど、保険料が安くなります。
そのため、月々の保険料を安くするためには、子どもが出生する前(妊娠中)に加入したり、生まれてすぐや幼児期に加入することで、少額ずつ積み立てることが可能です。
オプションを付けない
学資保険にオプションを付けない選択は、家計にやさしく、教育資金を計画的に積み立てるための基本戦略です。
学資保険は、医療保障・死亡保障・育英年金など、オプションを付けられる商品もありますが、これらのオプションを追加すると、保険料が高くなる可能性があります。
教育資金の積立が主な目的であれば、オプションを外して、返戻率を重視したシンプルなプランを選ぶことで、月々の支払い負担を抑えつつ、家計に無理のない効率的な運用が可能です。
医療保障や死亡保障などが必要な場合には、学資保険とは別に「生命保険」や「医療保険」でカバーすることにより、保険料を抑えながら家族全体の保障を確保できます。
払込期間を長くする
学資保険は、子どもの教育資金を計画的に準備するための長期積立型保険であり、払込期間の長さによって、月々の保険料が大きく異なります。
特に、子育て初期は、教育費以外にも、生活費や住宅ローンなど支出が重なる時期であるため、払込期間を長くしながら、家計の安定性を保てる積み立てが重要です。
一方で、保険商品によっては、支払い期間が長いと月々の負担が軽くなる分、返戻率が若干下がることもあるので、支払額と受け取る学資金のバランスを考えて選ぶことが大切です。
教育資金を効率的に準備したい場合は、返戻率の高いプランと払込期間の長さを比較して、メリットを活かした最適な設計にする必要があります。
少額から契約できるおすすめの学資保険一覧

学資保険は、子どもの進学費用を計画的に準備するための保険商品であり、少額から契約できるプランも増えています。
少額から契約できる学資保険を比較する際には、月々の保険料・払込期間・返戻率・保険商品の内容を確認し、理解してから契約することが大切です。
また、少額で支払う場合は、家計の状況に合わせて、月々の支払い額を調整できるプランを選ぶことで、無理なく長期的に積立を継続できます。
| 保険会社 | 商品名 | 子どもの年齢 | 保険料払込期間 |
|---|---|---|---|
| 太陽生命 | わくわくポッケ | 0歳〜12歳 | 10歳・12歳・15歳 |
| かんぽ生命 | はじめのかんぽ | 0歳〜12歳 | 要相談 |
| 明治安田生命 | つみたて学資 | 0歳〜6歳 | 10歳または15歳 |
| 東京海上日動 | 5年ごと利差配当付こども保険 | 0歳~9歳 | 18歳 |
| フコク生命 | みらいのつばさ | 0歳〜7歳 | 11歳・14歳・17歳 |
| 住友生命 | スミセイのこどもすくすく保険 | 0歳~9歳 | 12歳 |
少額から契約できる学資保険についてまとめ

本記事では、少額でも契約可能な「子どもの学資保険」について、詳しく解説してきました。
学資保険は、定期的な積立によってお金を貯められるため、将来の教育費に対する悩みを解消しやすく、少額でも契約することが可能です。
一方で、少額の学資保険には、デメリットも存在するため、月々の保険料を試算しながら、ライフスタイルに負担のないプラン選びが重要となります。
少額でも契約可能な学資保険を検討中の方は、35社以上の保険会社を取り扱っていて、保険業界のプロフェッショナルが多数在籍している「保険のぷろ」までご相談ください。
保険のぷろでは、少額でも契約可能な「おすすめの学資保険」をランキング形式でご紹介しています。







