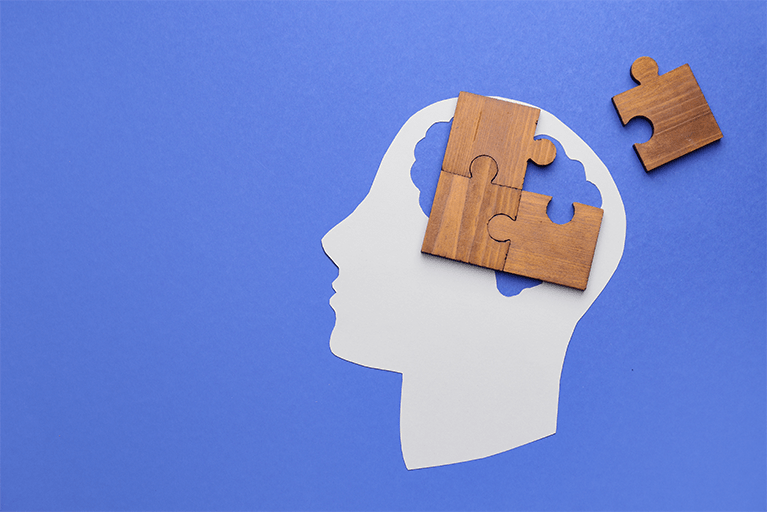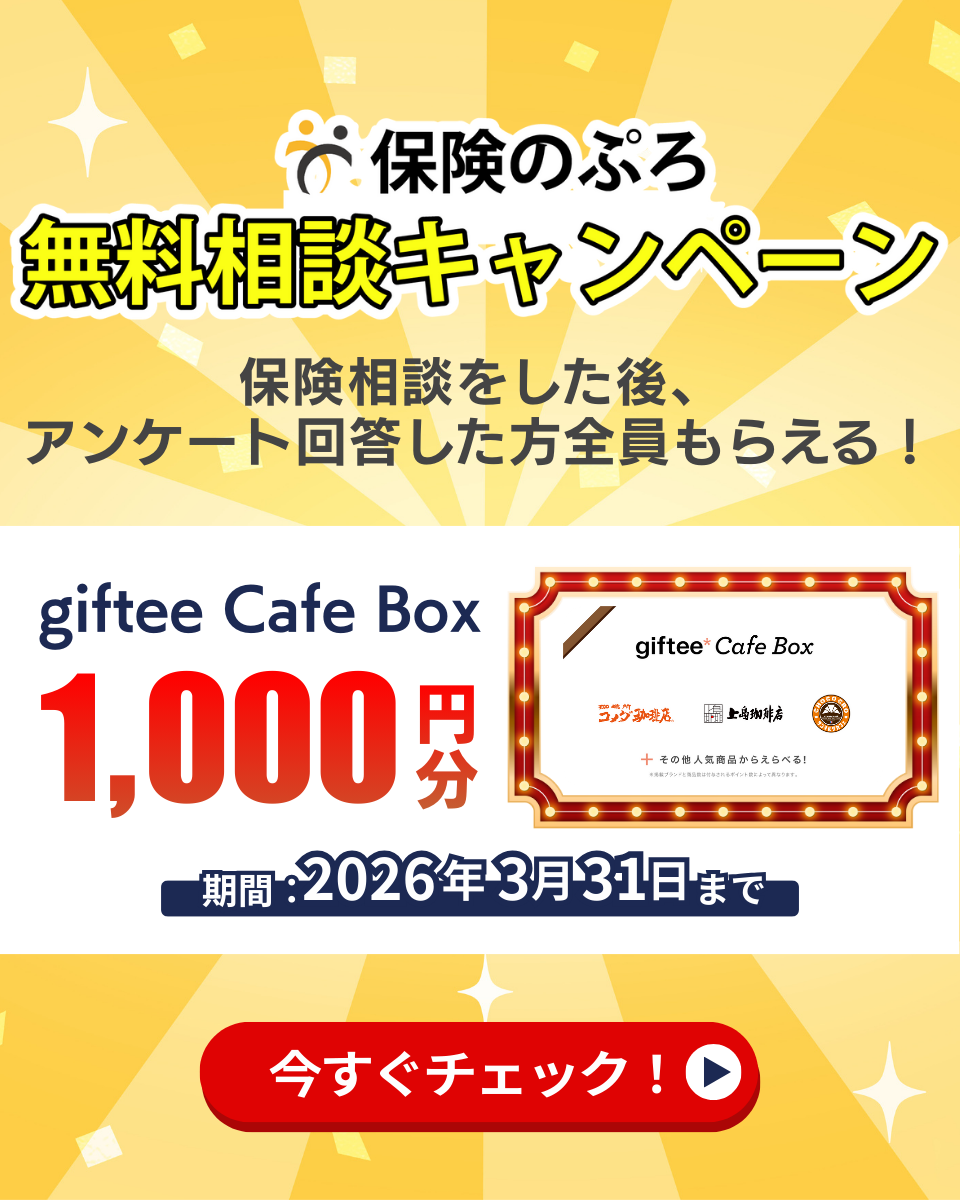なぜ生命保険はいらないという意見がある?その理由と必要性の高い人について解説
生命保険は契約者に万が一のこと(=亡くなること)があったとき、葬儀代や遺(のこ)された家族の生活費を賄うための保険です。
ただ、生命保険について調べていくうちに「生命保険は不要!」と目にしたことのある方も多いのではないでしょうか。
また、「万が一の出来事はいつ起こるか分からず、分からないものに対して保険料を払い続けるのが無駄」と考える人もいるかもしれません。
生命保険が必要か不必要なのかは、人によってそれぞれであり、ライフステージや家族構成、備えたいリスクに応じて検討していくことが重要になります。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、生命保険がいらないと言われる理由や、加入の必要性が高い人・低い人についてどこよりもわかりやすく解説します。
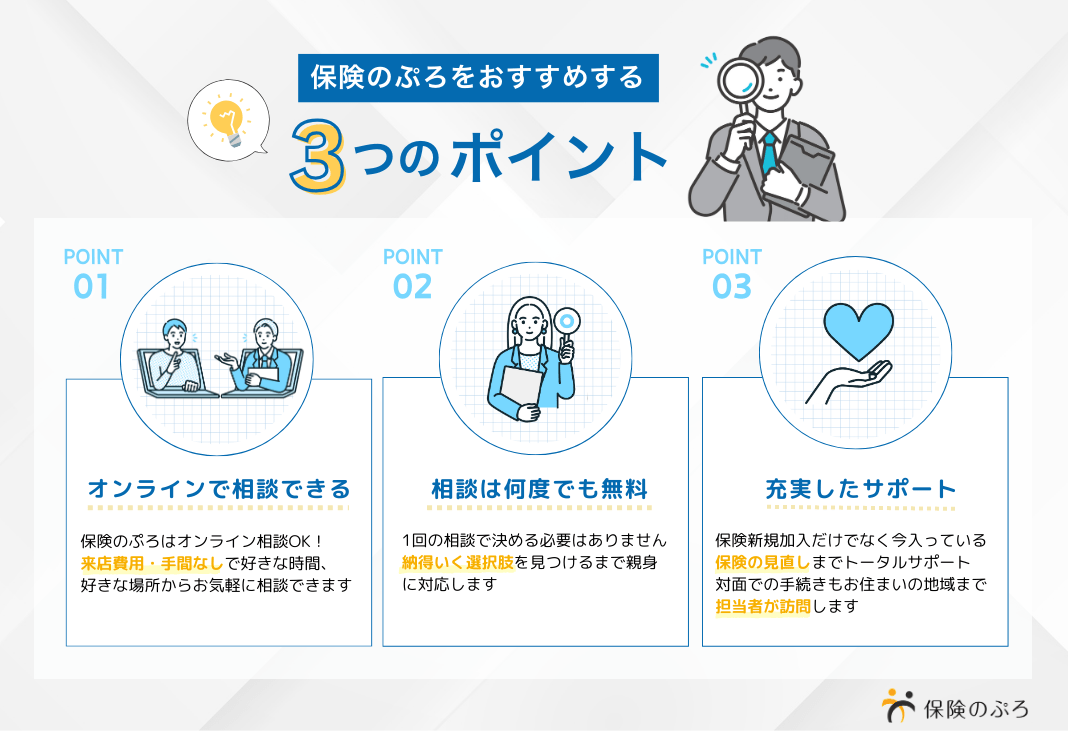
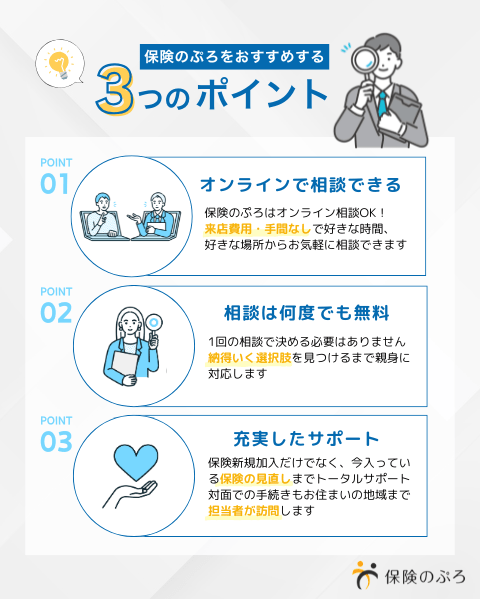
なぜ「生命保険はいらない」と言われているの?その理由とは

生命保険文化センターの調査によれば、2022(令和4)年度の生命保険加入率は男性が77.6%、女性が81.5%となっています。
これだけ多くの方が生命保険へ加入しているのにも関わらず「いらない」という意見があるのはなぜでしょうか?
その理由として以下の3つが挙げられます。
社会保障制度が整っているから
日本では、誰もが安心して医療を受けられるよう「国民皆保険制度」が採用されています。
国民皆保険制度とは、国民全員が何らかの公的医療保険に加入し、お互いを支え合う制度のことです。病気やケガで治療が必要になった場合には、この公的医療保険を利用することによって経済的負担を軽減することができます。
この制度によって全国民はかかった医療費のうち、原則3割負担で日本の高度な医療を受けることができ、さらに一定の額を超えれば、高額療養費制度(=超過分の払い戻し)の利用が可能です。
また、日本に住んでいる20歳〜60歳の方は国民年金に加入することが義務付けられており、この加入者が死亡してしまった場合、配偶者や子供は「遺族年金」を受け取れるという制度もあります。
このように、生命保険に加入しなくとも国からの保障が充実しているため、いらないと考える人もいます。
ただし、社会保障制度があっても自己負担がゼロになるわけではありません。一部の治療や入院は全額自己負担となるほか、遺族年金だけでは生活費を賄えない可能性があります。
現在のライフスタイルにどれだけの公的保障が適用されるかを理解した上で、生命保険の必要性について判断しましょう。
保険を使う機会が限られている
生命保険には、主に契約者が死亡したときに死亡保険金が支払われる死亡保険、病気やケガで入院・手術をしたときに保険金や給付金を受け取ることができる医療保険など、色々な種類があります。
これらの保険は、日常生活に潜む様々なリスクに備えることができますが、実際に自分が使う機会がないと考えている人も多いでしょう。
厚生労働省の「令和2年患者調査」によれば、人口10万人あたりの入院患者数は960人で、割合でいうと1%未満となっています。また、厚生労働省の「令和4年簡易生命表の概況」によると、40歳の死亡者数は1,000人につき0.97人、女性は0.60人です。
このように、統計から見ても入院する確率や死亡率は極めて低いため、生命保険の必要性を感じにくいと言えます。
ただし、年齢を重ねるとともに罹患率や死亡のリスクが高まることを頭に入れておきましょう。

守るべき存在が増えた方は生命保険の必要性がグンっと高まります。
十分な貯蓄があるから
普段から医療費や老後の備えのために貯蓄をしている方も、生命保険はいらないと考えます。
ただし、十分な貯蓄をしておいても万が一の時の支出額は予測できません。
公的保障の対象外である先進医療を利用したり、治療・入院が長期化したりすると、その額は想像以上に高額になることも。
そのため、すぐさま生命保険がいらないと判断せず、十分な資産形成ができているかを慎重に検討することをおすすめします。
生命保険に入らない場合のデメリット

では、生命保険に加入していないと、どのようなデメリットがあるのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
遺された家族が生活に苦しむ可能性がある
一家の大黒柱として家計を支える夫と、育児をしながらパートタイムで働く妻のケースで考えてみましょう。
夫が亡くなってしまった時、遺された妻の収入ではやりくりができず、貯蓄や遺族年金などで生活をしなければなりません。
たとえ妻が正社員として働きに出るとしても、小さな子供を家に残しておけず、ベビーシッターや保育費などを利用すると経済的負担は大きくなります。
子どもが大きくなった時には、教育資金の捻出が難しくなる場合もあり、進路を狭めてしまう可能性も考えられます。
病気やケガによる治療・入院が家計を圧迫する可能性がある
先述の通り日本の公的医療保険を利用すると、医療費負担は原則3割です。
ただし、以下のような項目は公的医療保険の対象外となるため全額自己負担となります。
- 差額ベッド代(個室や少人数部屋を希望する場合の費用)
- 先進医療※
- 入院中の食事代
- 自由診療 など
※例:がんを切らずに治療する「重粒子線治療」…約313万円
参考:厚生労働省「第127回先進医療会議資料 令和5年度実績報告」より算出
そのほか、付き添いやお見舞いで病院に行く際の交通費なども回数を重ねれば経済的負担は大きくなります。
老後の資金が不足する可能性がある
働きたくても働くことが難しい老後は、公的年金や貯蓄で生活費をカバーしなければなりません。自分や家族に介護が必要であれば、介護費用も用意しなければならず、生活が厳しくなる可能性があります。
そこで、生命保険と老後の資金が何の関係があるの?と疑問を抱く人も多いのではないでしょうか。
生命保険は死亡保険金や給付金だけでなく、満期保険金や解約返戻金を受け取れるものもあります。
満期保険金とは、あらかじめ設定した保険期間が満了した時に保険会社から支払われるお金のことです。解約返戻金とは、契約期間中に解約した際に受け取れるお金のことです。
それぞれの金額は保険会社や保険商品によって異なりますが、これらを活用することで老後の生活資金の一部を補うことができます。
生命保険へ加入するメリットはある?
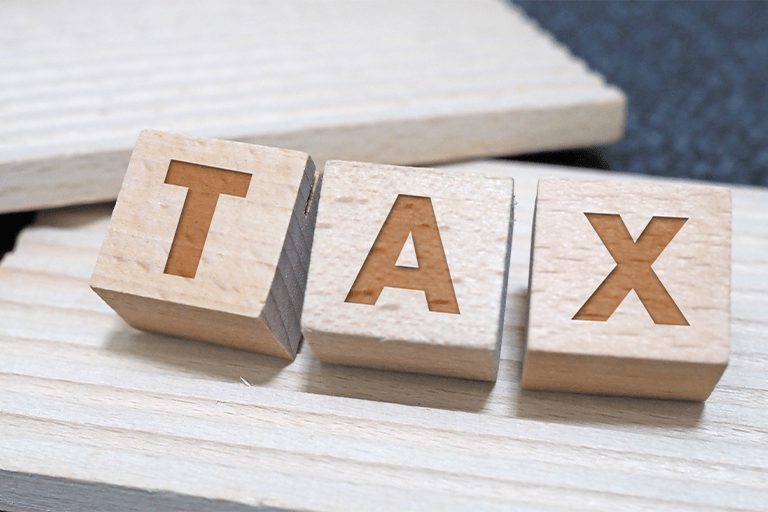
生命保険はいらないという意見もありますが、加入するメリットもいくつかあります。
様々なリスクにまつわる経済的負担を回避できる
生命保険に加入する最大のメリットは、日常に潜む様々なリスクに備えられるという点です。
生命保険(死亡保険)に加入していれば、一家の大黒柱に万が一のことがあっても、遺族は死亡保険金によって経済的負担を回避できます。
医療保険に加入していれば、病気やケガをした時に給付金を受け取ることができますね。特約を付加することによって、保障内容をさらに充実させることも可能です。
そのほか、病気や障害状態により働けなくなった時の生活費を保障する「就業不能保険」も近年注目を集めている生命保険です。
税負担を軽減できる
生命保険の保険料は、所得税や住民税の控除の対象となり、税負担を軽減できるメリットもあります。
この控除は年末調整や確定申告の際に適用され、払い込んだ保険料のうち一定額が課税される前の所得額から差し引かれるため、所得税や住民税の負担を軽減することが可能です。
生命保険の税金控除について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

生命保険の必要性が高い人の特徴
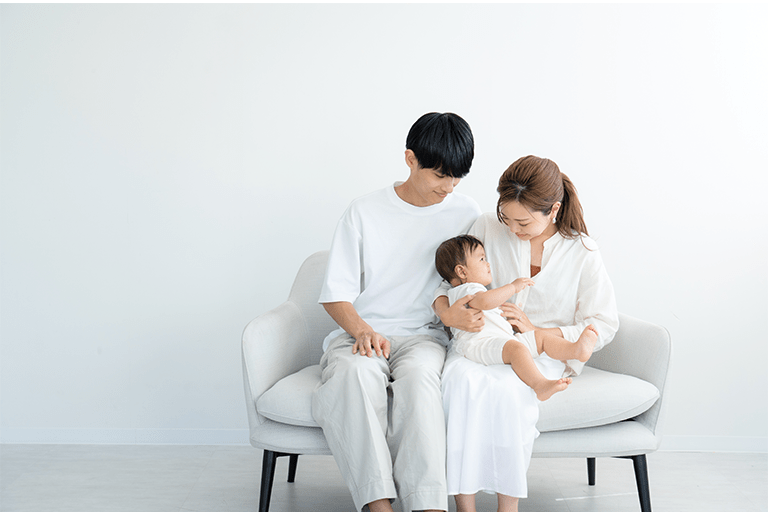
ここからは、生命保険の必要性が高い人の特徴を4つご紹介します。いずれかに当てはまる人は生命保険への加入を検討することをおすすめします。
守るべき存在がいる人=家族がいる人
配偶者や子どもなど、守るべき存在がいる人は生命保険の必要性が高いです。
家計を支える自分が死亡してしまった場合、遺族は収入が減少し、生活が困難になってしまいます。遺された家族の生活費や葬儀代を保障するためにも死亡保険への加入を検討すると良いでしょう。
また、扶養家族がいる場合、自身の病気やケガに対するリスクも考えなくてはなりません。
手術や入院で医療費負担が生じるほか、長期入院になった際には収入が途絶えることもあります。
公的保障を考慮しつつ、医療保険やがん保険、就業不能保険についても合わせて検討しましょう。
収入が不安定、貯金ができていない人
自分の収入が不安定で、病気やケガへの備えが足りないと感じている人も生命保険の必要性が高いです。
これは扶養家族がいる・いないに関わらず言えることですが、公的保険や高額療養費制度を利用しても、自己負担がゼロになるわけではありません。
公的保障の対象外となる費用が生じる上、働けなくなったことによる収入減少を考えると、十分な貯金がないうちは、医療保険やがん保険、就業不能保険へ加入することで安心を備えることができます。
老後資金を計画的に積み立てたい人
生命保険に加入すれば、保障を備えつつ資産形成をすることも可能です。
例えば、子どもが独立するまでは保障を備えておき、独立後には保険を解約して解約返戻金を老後資金として活用するやり方です。
老後のために貯蓄しようと思ってもなかなかできない人は、積み立て型の生命保険に加入して老後に備えるといった対策が必要となります。
自営業やフリーランスの人
自営業やフリーランスの人が加入する公的保障は、会社員や公務員が加入するものと比べて保障が少ないです。
会社員や公務員が加入する公的医療保険では、病気やケガで働けなくなった際に「傷病手当金」と呼ばれる給付金が支払われますが、自営業やフリーランスの人が加入する医療保険にはそのような制度がありません。
また年金制度にも違いがあり、会社員や公務員は国民年金と厚生年金の2種類を受け取ることができますが、自営業やフリーランスの人は原則国民年金のみです。
被保険者が死亡した場合に受け取れる遺族年金の支給額も少なくなる可能性があります。
そのため、生命保険で保障を手厚くしておく必要があります。
もしかしたらいらないかも?必要性が低い人の特徴

反対に生命保険の必要性が低い人の特徴もご紹介します。
独身の人
独身の人は扶養家族がいる人と比べて、生命保険の必要性が低いです。しかし、全く不要というわけではありません。
上記で解説した通り、病気やケガをした時の医療費や生活費を賄うだけの貯蓄がない場合は要検討です。
なお、年齢が若く病気のリスクが低いうちに保険に加入すれば保険料が安くなるため、将来結婚する予定などがある人は加入を検討することをおすすめします。
万が一の時のために十分な貯蓄がある人
自分が万が一死亡してしまったときの遺族の生活費や、病気やケガで入院・手術した時の医療費に対応できる十分な貯蓄がある人は生命保険の必要性が低いといえます。
生命保険は死亡、病気やケガの際の金銭的リスクをカバーしてくれるものです。
保険金や給付金を必要としないほど、十分に貯蓄がある人は生命保険に加入しなくても問題ないと判断できます。
記事まとめ

生命保険は、公的保障の充実度や保険を利用する機会が少ないこと、貯蓄があることを理由として「いらない」という意見が存在します。
しかし、生命保険の必要性はその人のライフスタイルや家族構成、家計状況によって変化するため、一概に「いらない」と判断することはできません。
自分でいらないと判断し、公的保険と貯蓄で賄おうとしていたら、予想以上に医療費がかかってしまい、加入しなかったことを後悔したというケースも考えられます。
「自分に必要かどうかわからない」「保険についてのプロに相談したい」という方は無料保険相談の利用がおすすめです!
本記事を提供する「保険のぷろ」でも無料保険相談を実施中です。オンラインで外出せず気軽に相談することができるのが最大のポイント!資料やパンフレットも画面共有で確認しながら相談することができます。
予約は30秒で完了しますので、ぜひご利用ください!