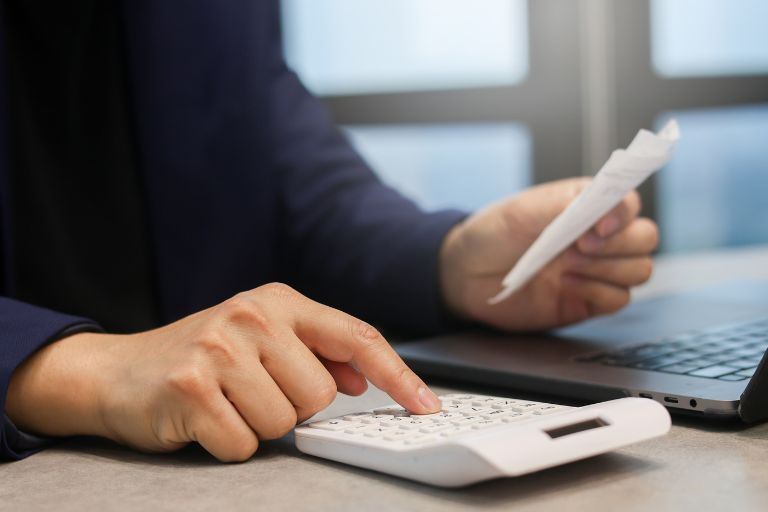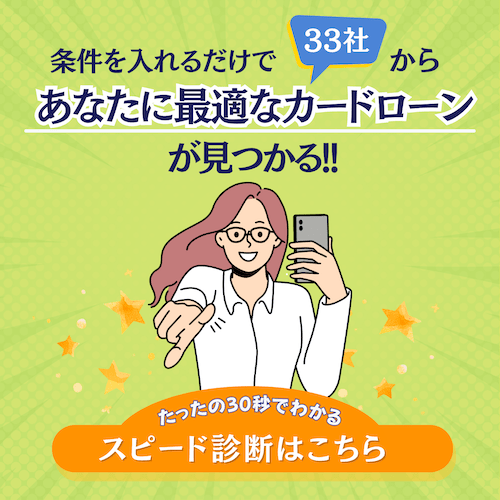職業訓練受講給付金の審査は受給条件が多く内容も厳しいので、難易度が高い
職業訓練給付金の受給は、ハローワークで職業訓練を受けている人が受給できる給付金です。
受給できれば職業訓練を受けている間、月10万円の給付金を受け取れますが、その審査については厳しいという評判が存在します。
実際には職業訓練給付金の審査は厳しいのでしょうか?
この記事では、職業訓練給付金の審査が厳しいのかどうかや、受給資格の詳細、給付金の審査で落ちる人の特徴についてお伝えします。
職業訓練給付金とは

職業訓練給付金とは、ハローワークで職業訓練を受けている方が受け取れる給付金のことです。
ハローワークでの職業訓練中、仕事をしていないため収入がない場合が多く、生活に困る可能性が高くなります。
このような収入のない期間を支えるため、厚生労働省から給付金が支給されます。
職業訓練給付金の金額は月々10万円で、一定の条件を満たすことで職業訓練受講期間中に受け取れます。
ただし、職業訓練給付金の受け取りには審査が必要で、審査通過しなければ受給できません。
審査通過のためには厳しい基準が存在するため、給付金の需給が難しいと感じる場合があります。
職業訓練の種類
職業訓練には「公共職業訓練」と「求職者支援訓練」の2種類があります。
それぞれの制度の詳細は以下の通りです。
公共職業訓練
公共職業訓練は国や都道府県が実施する職業訓練です。
国や都道府県の施設で訓練を受ける施設内訓練と、委託された民間業者の施設で受講する委託訓練が存在します。
それぞれの特徴は以下の通りです。
| 施設内訓練 | 委託訓練 | |
|---|---|---|
| 訓練期間 | 2か月~2年 | 3か月~2年 |
| 主な入校時期 | 4月・7月・10月・1月 | 毎月 |
| 授業料 | 無料(※1年以上の講座はかかる場合あり) | 無料 |
| 主な訓練内容 | 機械・建築・造園・電気・ファッションなど | JAVA・WEBデザイン・介護・医療・財務など |
参照: 公共職業訓練について|東京労働局
雇用保険を受給している人が対象で、スキルや技術を習得した後に細やかな就職支援を受けられます。
受講できる講座の種類は多岐にわたり、一例として以下のような講座が存在します。
- 電気工事
- 介護
- 医療・調剤事務
- 総務・経理事務
- デザイン
- プログラミング
これらはあくまで一例で、ほかにも様々なコースが存在します。
それらのコースから好きなものを選択し、3か月~2年の期間で就職に役立つスキルや知識を習得していきます。
受講料については、1万円~2万円のテキスト代のみは自己負担になりますが、その他は完全無料です。
参照: ハロートレーニング(職業訓練)について|東京労働局, ハロートレーニング
求職者支援訓練
求職者支援訓練は、主に雇用保険を受給できない方が受講できる職業訓練です。
ただし、令和4年7月1日からは、雇用保険を受給している場合でも、求職者支援訓練を利用できるようになりました。
訓練は基礎コースと実践コースに分かれ、希望の職業に就くために必要な知識を技術を基本から学べます。
訓練期間は2か月~6か月で、比較的短期間で就職に必要な知識や技術を身に着けられます。
公共職業訓練と同じく、講座の受講料は完全無料ですが、テキスト代は自己負担となります。
参照: 求職者支援訓練について|東京労働局, ハロートレーニング, 令和4年7月1日以降、雇用保険の受給資格者が「求職者支援訓練」の受講を開始する場合に、訓練延長給付や技能習得手当等を受給することができるようになります。
審査に必要な書類
職業訓練給付金の審査を受けるのに必要な書類は多く、以下のすべてをそろえる必要があります。
| 必要書類の種類 | 使える書類 |
|---|---|
| 番号確認書類 | 以下のいずれか マイナンバーカード/通知カード/マイナンバーカードの記載のある住民票 |
| 身元確認書類 | マイナンバーカード/運転免許証/精神障害者手帳/運転経歴証明書など |
| ハローワークから交付された書類 | 受講申込書/事前申し込み・事前審査書/職業訓練受講給付金要件申告書/職業訓練受講給付金通所届 |
| その他の書類 | 家族構成が分かる書類/収入証明書類/預金残高がわかる書類/給付金の振り込み先の通帳 など |
審査を受けるにはこれらの書類を用意し、ハローワークで提出する必要があります。
種類が多いので、漏れが無いようにしっかりと確認しながら準備しましょう。
参照: 求職者支援制度があります! 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
職業訓練給付金の審査は厳しい?

職業訓練給付金は受給するための条件が多く、審査は厳しいと感じる可能性が高いでしょう。
いったいどのような点が厳しいのでしょうか?
ここからは、職業訓練給付金の受給条件について詳しく見ていきましょう。
受給資格
職業訓練給付金の受給資格は、以下の4つの条件を満たすことです。
- ハローワークに求職の申し込みをしていること
- 雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者ではないこと
- 労働の意思と能力があること
- 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと
これら4つの条件をすべて満たしている場合のみ、給付金の審査に申し込みする資格を得られます。
ちなみに、「雇用保険受給資格者ではない」とは、雇用保険に加入できなかった場合や、失業給付受給期間中に再就職できなかった場合などを指します。
ほかには、自営業を廃業した場合や、就職が決まらずに学校を卒業した場合もこれに含まれます。
受給するための条件
職業訓練給付金の受給には条件が厳密に定められています。以下の7項目すべてを満たすことが受給資格となります。
- 本人の月収が8万円以下
- 世帯全体の月収が25万円以下
- 世帯全体の金融資産が300万円以下
- 現在の居住地以外に土地・建物を保有していない
- 全ての訓練実施日に出席している(やむをえない理由がある場合でも、8割以上の出席率が必須)
- 同じ世帯の人が同時に給付金を受給していない
- 過去3年以内に不正行為などにより特定の給付金を受けていない
このように、受給するためには多くの条件をクリアしなければいけません。
また、過去に職業訓練給付金したことがある場合は、前回の受給から6年以上経過しているのが審査通過の条件です。前回の受給が不正受給だった場合は、9年以上経過している必要があります。
ここまでに紹介した通り、給付金を受給するために満たすべき点が多く、一つでも満たしていないものがあれば、審査通過はできず給付金を受け取れなくなります。
特に、世帯月収については25万円以下である必要があるため、家族が多い場合にはかなり厳しい条件であるといえます。
このように、状況によってはクリアするのが非常に難しい条件が定められており、この点が審査が厳しいといわれる原因と考えられます。
参照: 求職者支援制度があります! 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
審査に落ちるパターン

職業訓練受講給付金の審査に落ちるパターンとして、以下のような状況が考えられます。
- 実家暮らしの場合
- アルバイトをしている場合
ここでは、一体なぜこれらが審査落ちの理由になってしまうのかについて解説していきます。
実家暮らし
実家暮らしだと職業訓練受講給付金の審査に落ちる可能性が高くなります。
給付金の受給条件に「世帯収入が25万円以下」というものがあるので、自分以外の家族がいるとどうしても審査に落ちやすくなるからです。
特に親や兄弟、配偶者など家族が複数人いる場合、世帯収入が25万円を超える可能性が多くなり、事前審査の段階で落ちやすくなるでしょう。
一人暮らしであれば、収入を25万円以下に抑えるのは比較的容易なため、この条件をクリアしやすくなります。
一方、実家暮らしだとこの条件をクリアするのは非常に厳しいため、審査落ちの大きな原因になる可能性があります。
アルバイトをしている場合
職業訓練を受けながらアルバイトをしている場合も、職業訓練給付金の審査通過が難しくなります。
アルバイトをすると、以下の2つの給付金の受給条件を満たせなくなる場合が多いからです。
- 雇用保険被保険者でない
雇用保険は「31日間以上の雇用契約」もしくは「週20時間以上の労働時間」のいずれの条件を満たすと加入義務が生じます。
アルバイトをするといずれかの条件を満たしてしまい、気がつかないうちに雇用保険の被保険者になり、審査落ちの原因になる場合があります。 - 月収が8万円以下である
アルバイトし週に複数日働くようになると、簡単に月収が8万円を超えてしまい、給付金の受給条件を満たせなくなります。
このようにアルバイトについても、厳しい条件が定められています。
これらの理由から、アルバイトをすると、相当気を付けない限り給付金の受給資格を失ってしまいます。
働くのであれば、雇用保険に入らなくてもいいように、長期契約ではなく単発のアルバイトを選ぶのがおすすめです。
また、働く時間は週20時間未満にし、月収は8万円以下になるように勤務日数を調節しましょう。
手続きの流れ

職業訓練給付金を受け取るための、手続きの流れは以下の通りです。
- 求職申込し説明を受ける
- 訓練コースを選択する
- 訓練の受講申し込み
- 訓練実施機関による選考を受ける
- 就業支援計画を作成する
- 訓練の受講開始
- 給付申請する
それぞれについて詳しく解説していきます。
求職申込し説明を受ける
ハローワークで求職申し込みを行います。この際に、職業訓練給付金の受給を希望する旨を申し出る必要があります。
訓練コースを選択する
職業訓練を受けながら適切な訓練コースを選びます。この際に、受講申込書などの必要書類を受け取りましょう。
訓練の受講申し込み
続いてハローワークの窓口で、記入・捺印した受講申込書を提出し訓練の受講を申し込みます。この際に、必要な添付書類を添えて事前申請に申し込みます。
訓練実施機関による選考を受ける
訓練実施機関による選考を受けます。選考内容は面接や筆記などになります。
就業支援計画を作成する
選考の結果が届きます。合格の通知が来た場合には、訓練開始日の前日までにハローワークで就業支援計画を受け取る必要があります。
就業支援計画の必要書類をハローワークでもらわないと、訓練の受講ができなくなり、職業訓練給付金の受給もできなくなります。
必ず訓練開始日までにハローワークを訪問し、書類を受け取るようにしてください。
訓練の受講開始
訓練開始日を迎えたらハローワークを訪問し、職業訓練を受講します。
職業訓練は複数回受講することになるので、そのたびに受付に給付金の支給申請をする必要があります。
参照: 求職者支援制度があります! 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
職業訓練給付金を受給する上での注意点

職業訓練給付金を受給する際には押さえておくべき注意点が存在します。4つの注意点をお伝えするので、押さえておきましょう。
毎月の職業訓練・指定来所日に出席し申請する必要がある
職業訓練給付金を受けるためには、訓練日には毎回出席し給付金を申請する必要があります。訓練中に欠席・遅刻・早退をしてしまうと、申請も漏れるので給付金が支給されなくなります。
そのため、職業訓練の日には遅刻することなく毎回出席し、訓練終了後には給付金の申請手続きをする必要があります。
さらに、ハローワークから指定される「指定来所日」にも、ハローワークに行く必要があります。いかない場合、職業訓練給付金の支給が停止される可能性が高くなります。
出席や申請についての支給条件は非常に厳しいため、審査通過のためには非常に重要といえます。
参照: 求職者支援制度があります! 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
訓練を欠席する場合には証明書類の提出が必要
訓練を欠席すると職業訓練給付金の給付がストップしますが、とはいえ健康上の理由などで訓練を休まざるを得ない場合もあるでしょう。
そういったときは訓練日程の変更が可能ですが、その場合には証明書類を提出する必要があります。
有効な証明書類は以下のいずれかになります。
- 医師または担当医療機関の証明書
- 医療機関または調剤薬局の領収
- 処方箋(写しで可)
- 就職セミナーなどの受講証明書(面接事業主の証明書・セミナー参加証)
- 電車などの遅延・事故を証明する書類(遅延証明書・事故証明書)
これらの書類をハローワークに提出し、やむを無い欠席であることを証明しない限り、職業訓練給付金を受け取れなくなってしまいます。
また、仮に書類を提出したうえでのやむをえない欠席であったとしても、訓練の8割以上の出席率がないと職業訓練給付金を受け取れなくなる点にも注意が必要です。
参照: 求職者支援制度があります! 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
職業訓練・指定来所日を複数回数欠席するとペナルティがある
職業訓練や指定来所日を複数回欠席すると、ハローワークからの支援が取り消され、職業訓練が打ち切られてしまいます。
その結果ペナルティとして、職業訓練給付金についても給付停止となり、すでに受け取った分に関しても返還を求められる場合があります。
過去に受け取った給付金について、すべて一括請求される恐れがあるので、訓練日や指定来所日には必ず時間通りにハローワークを訪問する必要があります。
職業訓練は欠席に関しては非常に厳しいので、可能な限りすべて出席できるようにすべきといえます。
参照: 求職者支援制度があります! 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
不正受給した場合もペナルティを受ける
虚偽の申告をし、本来は給付金を受け取れないにも関わらず不正受給すると、重大な違反行為となります。
この場合にもペナルティとして、職業訓練の打ち切りや給付金の全額返還を求められる可能性があります。
一例として、以下のような行為が重大な違反とみなされる可能性があります。
- 雇用保険の給付を受けていることを隠して申請した
- アルバイトで月8万円を超える収入を得ており、それを隠して給付金を受け取った
こういった行為により、不正受給をすると厳しいペナルティを受けることになり、やはり給付金の全額返還を求められる恐れがあります。
さらに悪質とみなされた場合、罰則の対象となる場合もあるので、不正受給は絶対にやめるようにしましょう。
まとめ

職業訓練受講給付金の審査は受給条件が多く内容も厳しいので、難易度が高いといわれる場合があります。
たとえば、雇用保険給付金の受給中やアルバイト収入が月8万円を超える場合には、審査通過できません。
しかし、条件を満たしていれば問題なく受給できるので、特に審査基準が厳しいと感じることはないでしょう。
受給したい場合には、この記事を参考に受給条件や申し込み方法を確認し、適切に手続するようにしましょう。