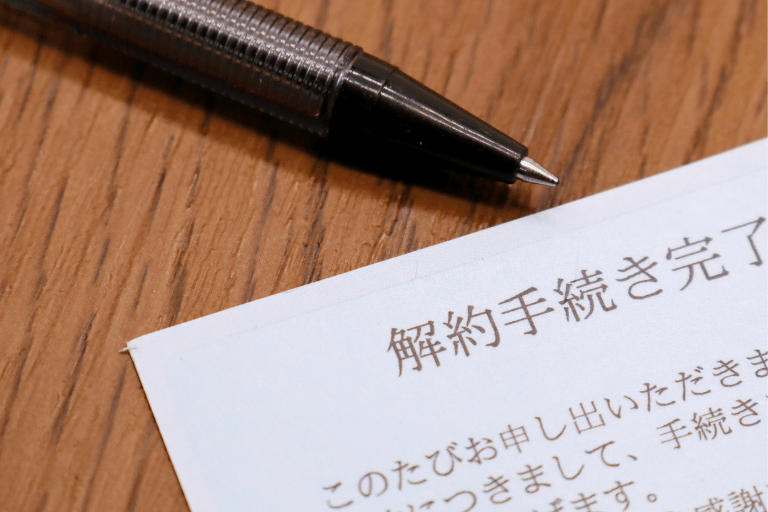地震保険とは?控除内容や注意すべき点について解説
近年、地震が増加しており、万が一に備えた地震保険への加入を検討する方も多いのではないでしょうか。
地震保険とは、単体では加入できない特別な保険であり、また完全復旧を目的とした保険ではないので、支払われる保険金額にも注意が必要となります。
そこで今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、地震保険とはどのような保険なのか、知っておきたい注意点と合わせて解説します。
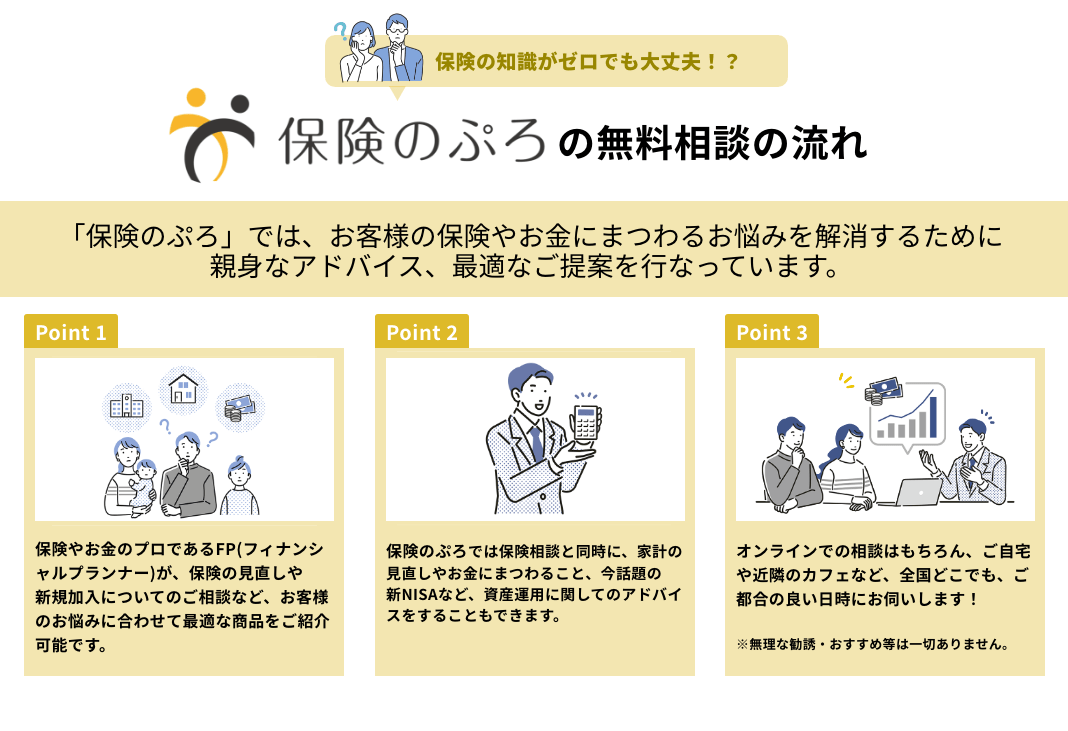
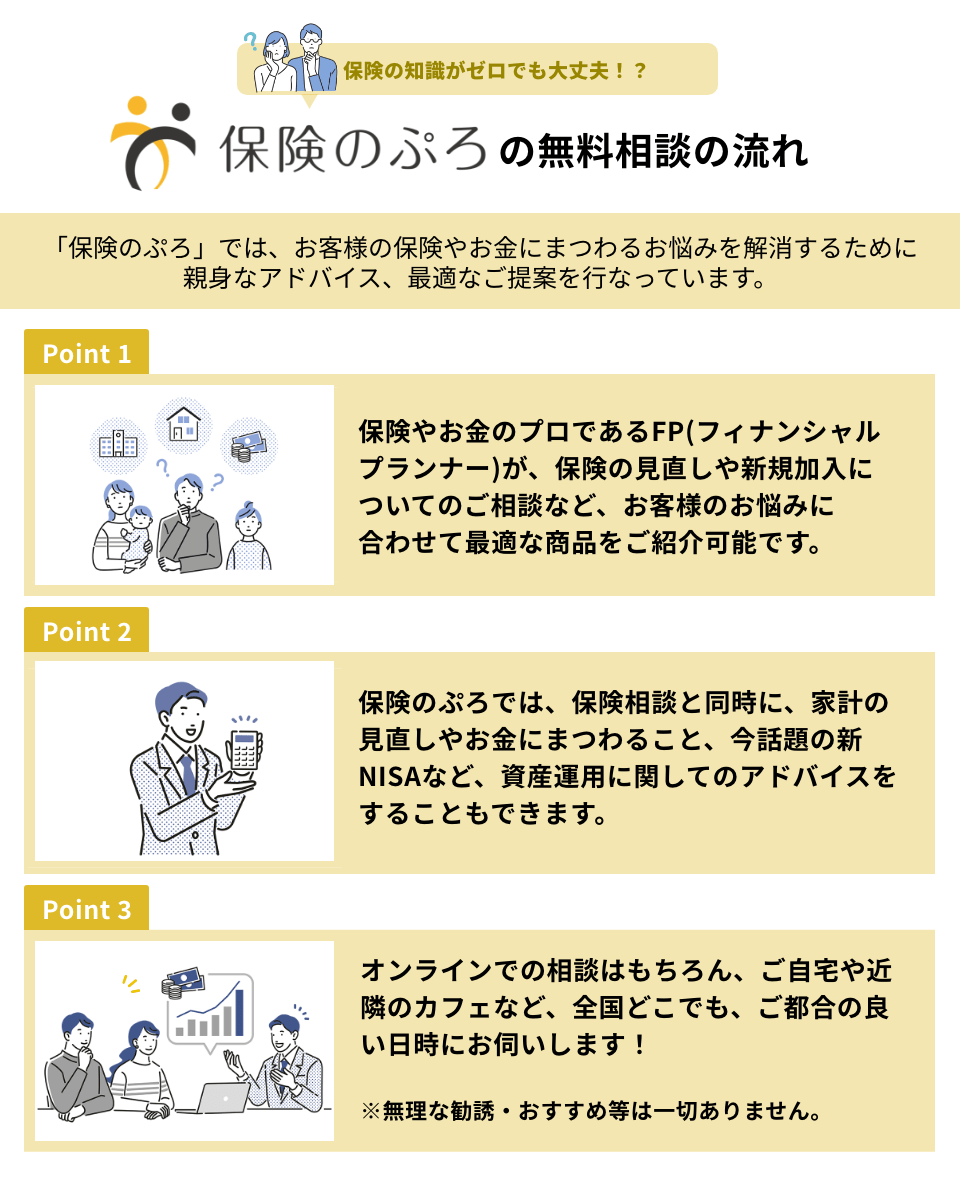
地震保険とは?
 まず、地震保険とはどのようなものなのかを解説します。
まず、地震保険とはどのようなものなのかを解説します。
国と保険会社が共同で運営
地震とは、いつどこで発生するのか予測ができないほか、地震発生時の被害は広範囲にわたり、被害総額も甚大なものとなるでしょう。
さらに、地震の影響で火災や津波、噴火が起こってしまった際には、被害の規模は測りし得ないものです。
そこで、国が「地震保険に関する法律」を定め、国レベルで補償をする地震保険を開始しました。
地震保険とは、損害保険会社を通じて契約された地震保険を政府が再保険し、政府と損害保険会社が共同で補償する仕組みです。
国と保険会社が共同で運営している公共的な保険商品なので、どの保険会社で加入しても、補償内容や保険料は同一となります。
火災保険とセットで考える保険
あとで詳しく解説しますが、地震保険とは火災保険で補償されない損害をカバーする保険です。
ここで重要なのが、地震保険単独で加入することはできません。
地震による損害を補償するには、火災保険とセットで加入しなければならないのです。
火災保険とはどのような補償なのかは以下の記事を参考にしてください。

地震保険の補償内容は?

では、地震保険の補償とはどのような内容なのかについてみていきましょう。
補償対象
地震保険の補償対象は、居住用の建物家財一式です。
住居として使用されない、工場や事務所等の建物は補償対象外となります。
保険金の額
地震保険では、損害を受けた居住用建物または家財の損害具合によって保険金が支払われます。
| 平成28年以前に保険開始 | 平成29年以降に保険開始 | ||
|---|---|---|---|
| 全損 | 地震保険の保険金額の100%(限度は時価額) | 全損 | 地震保険の保険金額の100%(限度:時価額) |
| 半損 | 地震保険の保険金額の50% | 大半損 | 地震保険の保険金額の60% |
| 小半損 | 地震保険の保険金額の30% | ||
| 一部損 | 地震保険の保険金額の5% | 一部損 | 地震保険の保険金額の5% |
全損、大半損、小半損、一部損とは、以下の基準で判断されます。
建物(全損、大半損、小半損、一部損の基準)
| 平成28年以前に保険開始 | 平成29年以降に保険開始 | 基準 |
|---|---|---|
| 全損 | 全損 | 地震等により損害を受け、主要構造部の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 |
| 半損 | 大半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合 |
| 小半損 | 地震等により損害を受け、主要構造部の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合 | |
| 一部損 | 一部損 | 地震等により損害を受け、主要構造部の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmを超える浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損・一部損に至らない場合 |
家財(全損、大半損、小半損、一部損の基準)
| 平成28年以前に保険開始 | 平成29年以降に保険開始 | 基準 |
|---|---|---|
| 全損 | 全損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の80%以上となった場合 |
| 半損 | 大半損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の60%以上80%未満となった場合 |
| 小半損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の30%以上60%未満となった場合 | |
| 一部損 | 一部損 | 地震等により損害を受け、損害額が保険の対象である家財全体の時価額の10%以上30%未満となった場合 |
参考:財務省「地震保険制度の概要」
保険料支払に関する情報

ここからは地震保険の保険料について解説します。
加入者全ての人に共通する保険料は、割引や控除の対象になります。よく読んで損をしないよう注意しましょう。
保険料の割引制度
地震保険は、築年数や耐震性能により、居住用建物及びこれに収容される家財に対し10%〜50%の割引が適用されます。
以下の4種類の保険料割引制度があります。(併用不可)
| 割引制度 | 割引率 | 概要 |
|---|---|---|
| 免震建築物 割引 |
50% | 対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「免震建築物」である場合 |
| 耐震等級 割引 |
耐震等級3: 50% 耐震等級2: 30% 耐震等級1: 10% |
対象物件が、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に規定する日本住宅性能表示基準に定められた耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有している場合 |
| 耐震診断 割引 |
10% | 対象物件が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法における耐震基準を満たす場合 |
| 建築年 割引 |
10% | 対象物件が、昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合 |
地震保険料は控除対象になる
地震保険の保険料は所得控除の対象となります。
地震大国である日本国民の地震災害に対する備えに係る自助努力を支援するために、地震保険料控除の制度が創設されました。
年末調整や確定申告を行い、支払い済みの地震保険料に応じて、一定の金額の控除を受けられるという仕組みです。
所得税は最高で5万円、住民税は最高2万5千円を総所得金額等から控除できます。
詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。
経過措置が適用される旧長期損害保険
平成18年税制改正で損害保険料控除が廃止されましたが、以下の要件を全て満たす損害保険料は地震保険料控除の対象となります。
- 平成18年12月31日までに締結した契約(保険期間または共済期間の始期が平成19年1月1日以降のものは除く)
- 満期返戻金等のあるもので保険期間または共済期間が10年以上の契約
- 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
参考:国税庁「地震保険料控除」
地震保険は入るべき?その必要性とは
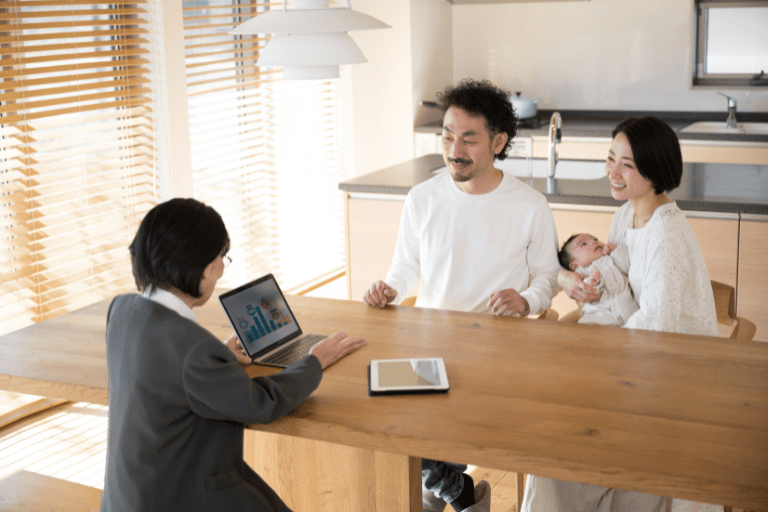
いつ発生するかわからない地震に対する補償は本当に必要なのでしょうか?
これから加入を検討する人にとっては、地震保険の必要性を十分に考慮して加入を検討したいですよね。
以下では、地震保険に加入することは必要なのか解説します。
近年増加する地震
日本は地震の発生源であるプレートが4つも集まる箇所に位置しており、活断層も全国各地に2000以上存在すると言われております。
そのため、2011年から2020年の間に起きたマグニチュード6.0以上の地震のうち全世界の約18%が日本周辺で発生したという記録もあるのです。
また、日本では、阪神淡路大地震・東日本大震災・熊本地震・能登地震などの大きな地震に限らず、地震の発生率は近年増加しており、地震による災害は測りし得ないものとなっています。
つまり、地震大国である日本に住む以上、いつ発生するかわからない地震に対する補償をしておくのは、自分の身を守るためであり、大切な備えであるのです。
地震動予測地図ウェブサイトや地震ハザードステーションなどで、自分の住む地域が近い将来地震に見舞われる可能性を確認し、津波の到達予想地域や木造住宅密集地などは特約などで補償を手厚くするなど、地域の特性に応じた地震保険に加入することをおすすめします。
火災保険のみでは地震による損壊は補償対象外
先ほどもお伝えしましたが、地震保険は火災保険の付帯する形で加入します。
火災保険とは火事や自然災害などによる被害を補償しますが、地震による被害は補償対象外です。
そのため、地震に対する補償を受けるには、地震保険への加入が必要なのです。
付帯率は7割
損害保険料率算出機構によると、2002年には3割程度だった地震保険の付帯率は、2022年の時点で約7割に増加しています。
将来地震が発生すると予想される地域や、直近で地震が発生した地域での加入率が高くなっており、全国的に地震保険のニーズが高まっていると言えるでしょう。
地震保険の注意点

以下では、地震保険に加入する際の注意点を解説します。
あくまでも経済的寄与の目的で補償
地震保険は支払われる保険金に限度があり、火災保険の保険金額の30~50%の範囲内で設定されます。
そのため、保険金だけで元通りに復元・立て直すことはできないのです。
これは地震保険の補償目的が、完全復旧ではなく、被害者の生活の安定への寄与を目的としているからなのです。
完全復旧に相当する保険金額をもらえなくとも、被害を受けた後の復旧費用に充てることができますね。
地震保険に加入しているからといって安心せず、一定の貯蓄を持っていることも地震に備えるために重要となるでしょう。
賃貸マンション等の場合は管理会社へ確認
通常、賃貸マンションなどでは、物件の契約と同時に火災保険も一緒に契約します。
物件の契約更新時期に合わせて2年契約、保険料は一括前払いというケースが多いようです。
しかし、マンションは共用部分と占有部分で対象となる保険が異なるので、管理会社等に問い合わせ、自分がどの部分の補償をつければ良いのかを確認しましょう。
まとめ

今回は、地震保険とはどのような保険なのか、補償内容や必要性について解説しました。
地震保険とは、火災保険に付帯する形で加入できる保険であり、被害者が経済的に安定できるように支援する仕組みです。
近年地震が増加している日本では、地震に対する唯一の保険として加入を検討する人が増加しています。
まだ地震保険に加入していない方は、自分の住む地域が受ける被害を想定し、家計に負担がない範囲で加入を検討すると良いでしょう。