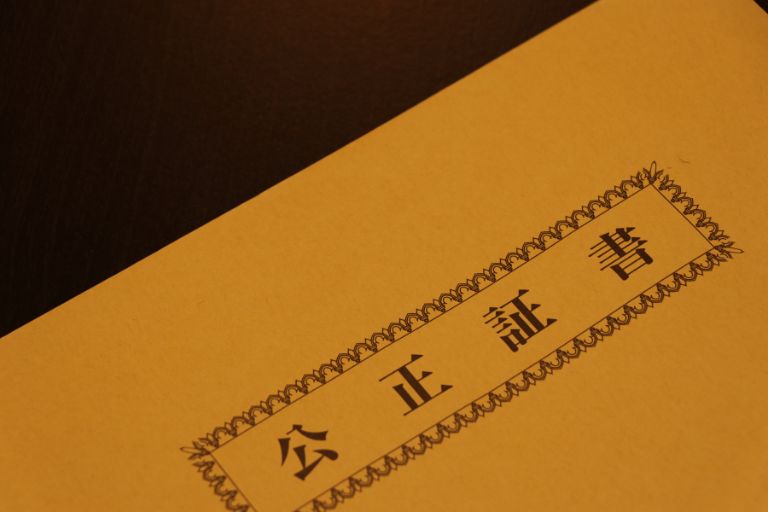
法律行為に関する書類を公文書化する「公正証書」について、その概要や費用を解説
「離婚することになったけど、元パートナーが慰謝料や養育費をちゃんと支払うか不安…」「借用書を作成したけど、もっとしっかりとした形式で書面を作りたい」などの悩みを抱えている人は少なくありません。
このような場合におすすめなのが、公証役場で作成する「公正証書」です。公正証書は、契約書や離婚協議書、遺言書などを公文書にし、内容の確実性を高める手続きです。
公正証書を作成すれば、万が一「その契約や取り決めが事実かどうか」の証明が必要になったとき、強力な証拠となります。具体的には、裁判で有利になったり、訴訟を起こさず差し押さえたりが可能です。
この記事では、公正証書の制度概要や費用などについて詳しく解説していくので、相続や離婚、各種契約を結ぶ人はぜひ参考にしてみましょう。
公正証書とは

公正証書とは、法律行為に関する書類を公文書化したものを指します。契約書や遺言などを公正証書にすれば、法的に高い証拠力を持たせることが可能です。
公正証書の作成は、全国にある公証役場に行き、公証人に依頼します。公証人は法務大臣によって任命された公務員のことで、経験豊富な法曹資格者(弁護士や検察官など)および同等の知識・経験がある者から選ばれます。
公正証書は原則20年(特別な事由があればそれ以上)、公証役場で保管されるため、改ざんや紛失の心配もありません。重要な法律行為を公正証書にすることで、法的トラブルがあったときに「取り決めの内容」について証明する手間が省けます。
公正証書にされることの多い法律行為
公正証書を作成する主なシーンとしては、次のようなものがあります。
- 任意後見契約※
- 遺言
- 贈与契約
- 離婚協議
- 金銭消費貸借契約
- 土地建物賃貸借契約
- 事業用融資の保証契約※
- 事業用定期借地権の契約※
- 分譲前のマンションの管理規約※
※公正証書の作成が必須
交渉証書を作成しておくと、内容が証明されるだけでなく、執行力を有するようになります。
例えば、相手方が遺言・離婚協議に従わない場合や、貸したお金の返済を滞納した場合、強制執行(差し押さえ)には裁判手続きが必要です。しかし、それらを取り決めたときの書類(遺言書・離婚協議書・金銭消費貸借契約書)を公正証書で作成しておけば、裁判を起こさなくても強制執行が可能になります。
作成の流れ

公正証書を作成するときは、次の流れで手続きを行います。
- 公正証書にする内容の取り決め(もととなる書面の作成)
- 必要書類の準備
- 公証役場で作成申し込み
- 公正証書案の作成
- 公証役場で最終確認・完成
まずは公正証書の内容について、大枠を取り決めます。遺言なら財産の承継先と金額、離婚協議なら財産分与の割合や養育費の支払いなどです。
続いて、公正証書作成に必要な書類を準備します。具体的な必要書類は申し込む内容によりますが、共通して必要なものは以下の通りです。
| 当事者が申し込む場合 | 代理人が申し込む場合 | |
|---|---|---|
| 当事者が個人の場合 | 次のうちいずれか1セット ・印鑑登録証明書と実印 ・運転免許証と認印 ・マイナンバーカードと認印 ・住民基本台帳カード(写真付き)と認印 ・パスポート、身体障害者手帳または在留カードと認印 |
・当事者本人からの委任状 ・当事者本人の印鑑登録証明書 ・代理人の確認資料(個人の当事者が申し込む場合の書類のいずれか) |
| 当事者が法人の場合 | 次のうちいずれか1セット ・代表者の資格証明書と代表者印およびその印鑑証明書 ・法人の登記簿謄本(登記事項証明書)と代表者印およびその印鑑証明書 |
・当事者法人の代表からの委任状 ・法人代表者の確認資料(代表者の資格証明書および代表印の印鑑証明書、もしくは法人の登記簿謄本(登記事項証明書)および代表印の印鑑証明書) ・代理人の確認資料(個人の当事者が申し込む場合の書類のいずれか) |
書類を準備したら、公証役場で公正証書の作成を申し込みます。公証役場は全国に約300か所あり、どこで手続きしても問題ありません。
病気などの事情がある場合、公証人に病院や自宅まで出張してもらうことも可能です。
手続きする公証役場を決めたら、事前に予約してから出向いて相談し、協議や資料確認などを経て公正証書案を作成してもらいます。
最後は当事者(もしくはその代理人)全員が来所し、内容を確認して書面に署名捺印すれば、公正証書の完成です。
公正証書作成の申し込みから完成まで、おおむね1~2週間程度かかります。ただし、契約内容が複雑なものや、事情調査に時間を要するものの場合、1か月以上かかるケースもあります。
代理人は専門家(弁護士・司法書士・行政書士)への依頼がおすすめ
公正証書の作成は代理人に依頼することも可能です。代理人を選ぶときに資格の限定はなく、未成年者や成年被後見人・被保佐人・被補助人などの「法的に代理人になれない人」以外なら誰でも依頼可能です。
しかし、公証役場の手続きも、もととなる遺言や各種契約の取り決めも、法律の専門知識が必要となります。間違いのない公正証書を作るなら、法律の専門家に依頼すべきです。
具体的には、以下のように状況次第で相談先を決めると良いでしょう。
- 相手方と交渉中や法的トラブルがある場合、その他全般…弁護士
- 不動産が関連する場合…司法書士
- 契約等でおおむね相手方と同意している場合…行政書士
弁護士なら法律問題や交渉業務全般を扱えるため、どのような内容でもほとんど対応可能です。ただし、費用はほかの専門家より高めになるため注意しましょう。
司法書士は主に不動産登記の専門家なので、遺言や離婚協議などで不動産が絡むときに向いています。
行政書士は、法的トラブルが絡まない書類の作成であれば対応できます。上記の専門家のなかではもっとも費用相場が安いので、内容が大筋で合意できている契約行為におすすめです。
公正証書を作成するには、公証役場への手数料が必要

公正証書を作成するときは、「公証人手数料令」という政令に定められた手数料が必要です。
手数料は、以下のように「目的の価額(公正証書の内容によって生じる利益の額)」に応じて決まります。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 1万1,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 1万7,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 2万3,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 2万9,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 4万3,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円+超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算 |
| 3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円+超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算 |
| 10億円を超える場合 | 24万9,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円を加算 |
利益の算定ができない場合(任意後見契約など)は、原則として500万円を目的の価額とみなします。
支払い方法は現金もしくはクレジットカードで、基本的には公正証書の正本を交付されるときに支払います。ただし、内容によっては予納が必要な場合もあるので、詳しくは公証役場で確認しましょう。
手数料の計算は「法律行為ごと」に行う
公正証書の手数料を計算するときは、法律行為ごとに目的の価額を算定します。
例えば、目的の価額が1,000万円超~3,000万円以下の場合、手数料は1万7,000円です。しかし、公正証書全体の記載金額が3,000万円でも、その内訳が「1,200万円の法律行為」と「1,800万円の法律行為」だった場合、手数料は「1万7,000円×2=3万4,000円」となります。
土地と建物を同時に売買するときなど、同時に2つ以上の法律行為が絡むケースでは、手数料の金額に注意しましょう。
手数料の加算やその他の費用について
公正証書の作成手数料は上記の通りですが、場合によっては以下の費用も公証役場に支払います。
| 公正証書が4枚を超える場合 | ・1枚ごとに250円の手数料を加算 |
|---|---|
| 遺言書の場合 | ・全体の財産が1億円以下の場合、1万1,000円の手数料を加算(遺言加算) |
| 公証人に出張が発生した場合 | ・日当…1日につき2万円(4時間以内のときは1万円) ・旅費…実費(は国家公務員等の旅費に関する法律に準ずる額) |
| 書類の送達が必要な場合 | ・実費 |
参照:公証人手数料令第19条、第25条、第42条、43条|e-Gov法令検索
なお、相談だけなら費用はかからないため、気軽に相談してみましょう。
公証役場の手数料とは別に、必要になる費用は?
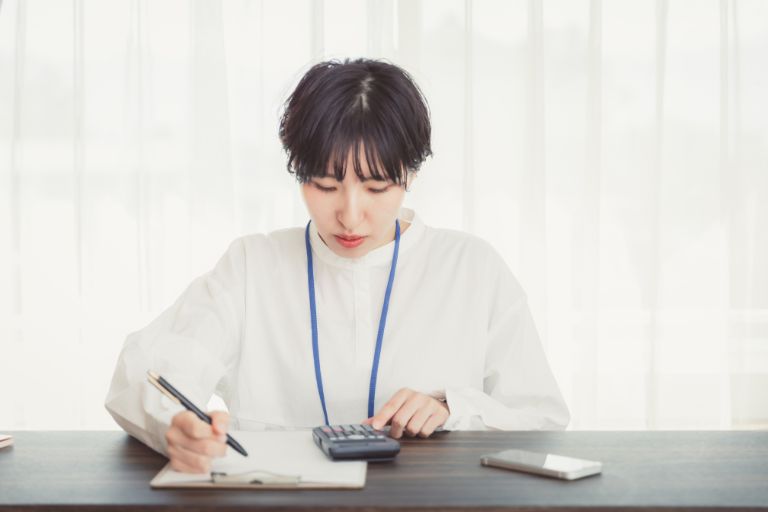
公証役場に支払う手数料は先述の通りですが、それ以外にも以下の費用が発生します。
- 必要書類等の取得費
- 印紙税(契約書の場合)
- 専門家への報酬(代理人を依頼する場合)
必要書類の取得費は印鑑登録証明書や登記事項証明書などで、1通数百円程度が目安です。
印紙税は、経済取引にかかる契約書などに課される税金で、書面に印紙を貼付して納付します。金額については、国税庁のWebサイトを参照しましょう。
専門家への報酬は、弁護士などに代理人を依頼した場合に発生し、おおむね3万円程度が目安です。事務所によって料金体系が異なるため、事前に見積もりをだしてもらいましょう。
記事まとめ

公正証書は、契約や遺言などの確実性を上げたいときに有効な制度です。費用は公正証書の内容にもよりますが、手数料や諸費用を合わせて数万円~30万円程度が目安です。
額面の大きい契約や遺言だと手数料の負担も大きくなりますが、トラブルになったのときの手間や損失を考えれば、支払う価値はあります。
書面の内容について法的トラブルを防ぎたい場合は、ぜひ公正証書の作成を検討してみてください。







