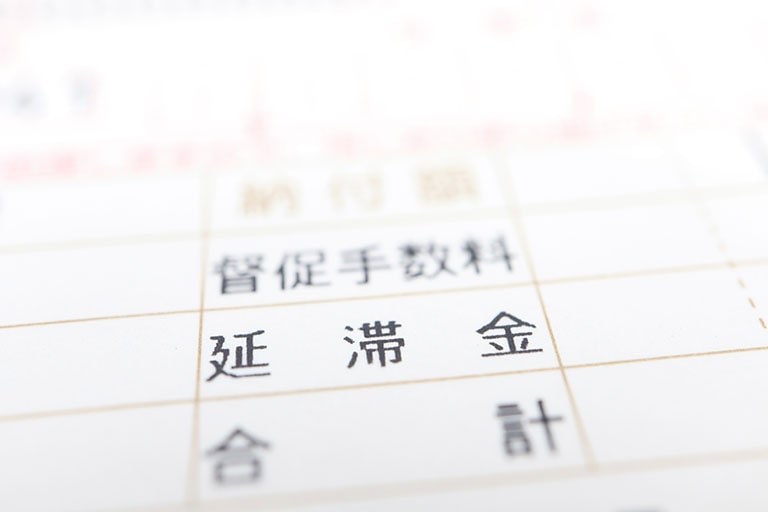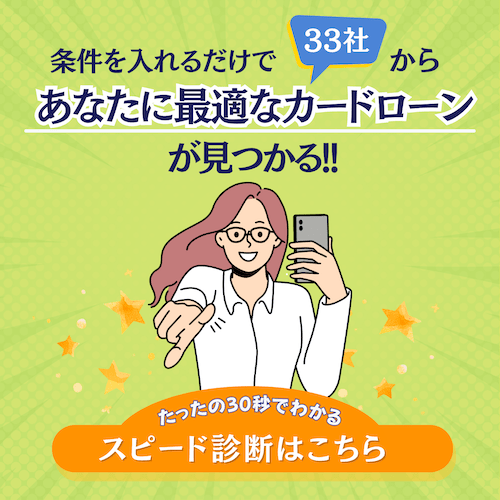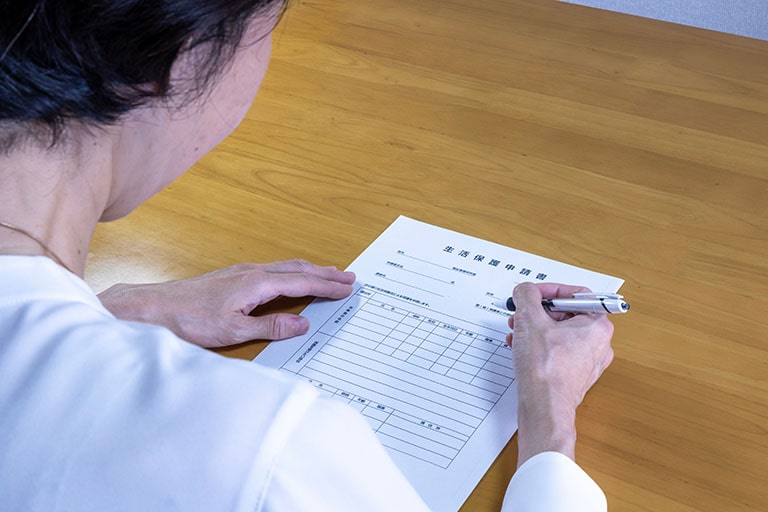
生活保護でもらえる金額の計算方法!受給の条件5つと扶助8種、注意点も解説
日本では、経済的な理由などが原因で、最低水準な生活を送ることが難しい方が受けられる生活保護という制度があります。
中には生活保護を受けることに対して恥や不安を感じている方もいるのではないでしょうか。
しかし、厚生労働省の調査によると2023年8月時点の生活保護受給者は202万人にのぼっており、日本人口の約60人に1人が生活保護の申請に通っています。
確かに生活保護といっても一概に良いとは言えず、デメリットもあるのは事実です。
本記事では生活保護を受給する条件や扶助の種類、もらえる金額、申請方法についてわかりやすく解説します。
生活保護を受給しようかまだ検討中という方の一助になれましたら幸いです。
生活保護とは?支給される8つの扶助

生活保護という制度について、厚生労働省の公式ページで以下のように述べられています。
資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。
引用元:生活保護制度|厚生労働省
生活保護制度でもらえる受給金額は、日本国憲法第二十五条の以下の理念に基づいて定められた最低生活費が基準になります。
第二十五条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
引用元:日本国憲法-衆議院
また、支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。
生活保護の扶助8種類
生活保護の中には、8種類の扶助があります。
以下、それぞれの扶助内容や付与される金額内容についてまとめました。
| 扶助8種 | 扶助内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 生活扶助 | 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費等) | (1)食費等の個人的費用 (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。 特定の世帯には加算があり。(母子加算等) |
| 住宅扶助 | アパート等の家賃 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 教育扶助 | 義務教育を受けるために必要な学用品費 | 定められた基準額を支給 |
| 医療扶助 | 医療サービスの費用 | 本人負担なし(費用は直接医療機関へ支払) |
| 介護扶助 | 介護サービスの費用 | 本人負担なし(費用は直接介護機関へ支払) |
| 出産扶助 | 出産費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 生業扶助 | 就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
| 葬祭扶助 | 葬祭費用 | 定められた範囲内で実費を支給 |
受給するための5つの条件

このような生活保護を受給できる金額を計算する前に、クリアしなければない条件を5つ解説します。
生活保護を受給したい方は、以下の条件に当てはまっているか確認してみてください。
条件1:収入が国が定める最低生活費を下回っていること
生活保護を受給する上での第一条件として、収入が厚生労働省の定める最低生活費を下回っていることです。
参議院の公式ホームページでも、生活保護の受給資格について以下のように述べています。
保護の要否の判定は、基準及び程度の原則18により、厚生労働大臣の定める基準(いわゆる保護基準)によって、最低生活費を計算し、これとその者の収入とを比較して、その者の収入だけで最低生活費に満たない場合に、生活保護が必要と判定される。
引用元:参議院
つまり、生活保護は収入が少なく困窮な人ほど受給しやすい仕組みになっているのです。
働いている人は、あなたの収入が最低生活費を上回っていないか、確認しましょう。
ここで注意が必要なのが、収入といっても働いて稼いだお金以外にも、以下のようなものが含まれるため手放さなければならない可能性もあることです。
- 車
- 持ち家
- 申請者、またはその親族が居住していない土地
- 貯金
- 相続で得たお金
- 年金
- 保険金
- 払戻金のある保険(生命保険・医用保険・学資保険)
- 失業保険や退職金などの手当
- 仕送りまたは小遣い
- 物品の売却によって得たお金
- 公的融資制度または民間金融機関で借りたお金
- 融資を受けられるカードローン
条件2:持ち家や車などの資産を所有していないこと
条件1でも解説した通り、持ち家や車などの資産を所有している場合は、まずそれらを売却した金額を生活費に充てることが求めらます。
アパートに住んでいる人や社用車であれば自分の所有物ではないので資産扱いされませんが、購入した住居や自家用車の場合は売却が必要です。
上記のような資産を全て現金に換算しても、生活費が最低基準を下回っている場合にのみ生活保護を受給できます。
例外:所有が認められることも
しかし、例外で持ち家や車の所有を認めてもらえる場合もあります。
以下が持ち家や土地の所有を認められた事例です。
- アパートなどに引っ越すよりも、自宅に住み続けたほうが費用がかからない
- 古い家のため価値がつかず、逆に取り壊しに必要な金額の方が高い
- 重度の障害が理由で住居を変更すると症状に影響がでるケース
ただし、生活保護費用を債務の返済にあてることは禁じられているため、住宅ローンが残っている家の場合は売却を求められます。
以下、車の所有が認められた事例になります。
- 地方に住んでいて自動車がないと日常生活を送ることが困難な場合
- 家族や申請者が障害や病気を患っていて公共交通機関による移動が困難
- 公共交通機関の料金が高額になる場合
自家用車は持ち家よりも必要であると判断される状況が多いため、少額であればろ
条件3:怪我や病気で働けず経済的に困難なこと
生活保護を受給するための3つ目の条件として、精神病も含めた病気や怪我が原因で働けず、経済的に困難なことです。
ただし、自己申告だけでは信憑性が低いため、医師の診断書を求められるケースが多くあります。
また、怪我や病気以外にも、乳幼児を育てているシングルマザーや親族の介護をしている人など、あなたが元気でも働けない事情がある場合も生活保護の対象に入ります。
しかし子供が成長したり、介護が不要になれば生活保護の対象からは外れることを覚えておきましょう。
条件4:公的ローンや公的扶助の対象外であること
生活保護は、ローンもその他の扶助も受けられない程金銭的に困っている国民のための最終セーフティーネットです。
そのため、公的ローンや公的扶助など、他の社会保障制度から支援を活用する必要があります。
主に、以下のような手当てを受けられないか確認しましょう。
- 雇用保険失業給付
- 求職者支援制度
- 生活福祉資金貸付
- 住居確保給付金
- 母子父子寡婦福祉資金
また、年金にも以下の3種類存在します。
- 老齢年金
- 障害年金
- 遺族年金
上記のような手当てを受けても生活が苦しい場合は、生活保護の申請を考えてみてはいかがでしょうか。
条件5:三親等以内の親族から支援を受けられないこと
生活保護の申請をすると、その条件の一つである3親等以内の親族から支援を得られないのか、「扶養調査書」によって確認されます。
そして親族に扶養してもらえる金額は、条件4で紹介した公的扶助と同様に生活保護よりも優先されます。
ここでいう親族とは、配偶者と3親等以内の親族のことで、具体的な関係性を以下まとめました。
- 両親
- 別居中の配偶者
- 祖父母
- 子ども
- 兄弟姉妹
- 孫
- 叔父叔母、めい、おい
DVや虐待を受けていた場合は調査を省略可能
配偶者からDVを受けていた人や、親や子どもなどから虐待・暴力を受けていた人などは、福祉事務所に相談してみましょう。
例外的に扶養調査を省略してもらえます。
また、自分の現在の住所も知られたくない人もいるのではないでしょうか。
その場合は、ケースワーカーに相談すれば相手に伝えられる心配もありません。
生活保護費用の金額はいくらもらえる?計算方法

これまで解説した条件に当てはまる場合、生活保護費用の金額はいくらもらえるのでしょうか。
受給できる生活保護費用の金額は、厚生労働省が定める最低生活費からあなたの収入を差し引いた差額分になります。
そのため、働くことができず収入が一切ない方は最低生活費の金額全て受給できる仕組みになってます。
また、介護者の有無や片親で子育てしているなど、それぞれの状況によって受給できる金額が増えるので、人によって異なります。
ただし、加算扶助を受けられたとしても、生活保護費が最低生活費を超えることはありません。
最低生活費はいくら
では、生活保護で受給できる金額を計算するのに重要な最低生活費について確認しましょう。
最低生活費の金額は、世帯人数や年齢、住んでいる地域の等級によって変化します。
なぜなら、住んでいる地域によって物価や家賃など、最低限度の暮らしをする上で必要な金額が変わってくるからです。
例えば東京八王子市や、埼玉県の川口市などの都心部は最も高い「1階級地ー1」に分類されます。
以下、生活保護基準における級地区分の一部を例としてまとめました。
| 級地区分 | 市区町村(一部) |
|---|---|
| 1級地ー1 | 東京23区、川口市、さいたま市、横浜市、川崎市、鎌倉市、藤沢市 |
| 1級地ー2 | 札幌市、江別市、仙台市、所沢市、蕨市、戸田市、青梅市、武蔵村山市 |
| 2級地ー1 | 函館市、小樽市、旭川市、青森市、盛岡市、秋田市、福島市、山形市 |
| 2級地ー2 | 日立市、土浦市、塩伽市、名取市、足利市、長岡市、小松市 |
| 3級地ー1 | 敦賀市、小浜市、大野市、富士吉田市、都留市、飯田市、須坂市、高山市 |
| 3級地ー2 | 「3級地ー2」までに該当しない市町村 |
あなたがお住まいの地域の正確な金額を把握されたい方は、あなたの地域の福祉事務所にいいくと教えてくれます。
最低生活費の計算方法
本記事の最初に生活保護の扶助を8種類ご紹介しましたが、主になるのは生活扶助と住宅扶助です。
生活扶助は以下のように第1類と第2類に分けられます。
- 第1類:食費や衣類などの個人的費用
- 第2類:水道光熱費などの世帯に共通してかかる費用
上記2つの生活扶助と住宅扶助を合わせた金額が、あなたが受給できるおおよその最低生活費になります。
最低生活費の金額計算式は以下の通りです。
生活扶助(第1類)+生活扶助(第2類)+住宅扶助+その他の扶助=最低生活費
生活扶助第1類は、世帯全員の第1類基準額に逓減率(世帯人数によって割合が異なる)を乗じて計算します。
もちろん、教育扶助や介護、医療などにも当てはまればそれらも追加されます。
ケース別の加算額一覧
以下、あなたの状況によって加算される保護費と、そのおおよその金額をまとめました。
| 加算 | 対象者 | 金額 |
|---|---|---|
| 妊産婦加算 | 妊娠している女性 | 8,200円前後 |
| 母子加算 | 18歳以下の児童を1人で育ててる | 20,000円前後 |
| 障がい者加算 | 身体障害者障害等級が1〜3級の人 | 26,000円前後 |
| 介護施設入所者加算 | 介護老人保健施設に入居している人 | 9,880円前後 |
| 冬季加算 | 寒冷地に住んでいる人(11月〜3月) | 〜24,260円前後 |
| 在宅患者加算 | 在宅で療養している被保護者 | 13,020円前後 |
上記のような条件に当てはまる人は、通常の保護費に換算された金額を受給できます。
子供がいることが条件の母子加算や児童養育加算などは、その世帯の子供の人数によって加算額が変わります。
加算額は地域によって異なるため、正確な加算金額を知りたい人は、あなたが住んでいる市区町村の福祉事務所で確認してみてください。
【計算例】世帯・地域別の受給金額を計算してみた
以下の資料を基に、世帯・地域別の受給金額を計算してみましたので、是非参考にしてみてください。
引用元:生活保護制度の概要等について(厚生労働省社会・援護局保護課)
3人世帯の場合【33歳・29歳・4歳】
以下では、夫婦2人と子供1人の3人世帯の場合の金学を級地区分べつに計算しました。
| 級地区分 | 生活扶助 | 住宅扶助(上限) | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 1級地-1 | 158,760円 | 69,800円 | 228,560円 |
| 1級地-2 | 153,890円 | 44,000円 | 197,890円 |
| 2級地-1 | 149,130円 | 56,000円 | 205,130円 |
| 2級地-2 | 149,130円 | 46,000円 | 195,130円 |
| 3級地-1 | 142,760円 | 42,000円 | 184,760円 |
| 3級地-2 | 139,630円 | 42,000円 | 181,630円 |
高齢者1人世帯【68歳】
以下は、68歳の高齢者が一人暮らしをしていた場合に受給できる生活保護費の金額です。
| 級地区分 | 生活扶助 | 住宅扶助(上限) | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 1級地-1 | 77,980円 | 53,700円 | 131,680円 |
| 1級地-2 | 74,690円 | 34,000円 | 108,690円 |
| 2級地-1 | 70,630円 | 43,000 円 | 113,630円 |
| 2級地-2 | 70,630円 | 35,000円 | 105,630円 |
| 3級地-1 | 67,740円 | 32,000円 | 99,740 円 |
| 3級地-2 | 66,300円 | 32,000円 | 98,300円 |
子供2の母子家庭3人世帯【30歳・4歳・2歳】
以下、母子家庭で4歳と2歳の子供が2人いる家族の生活保護金額をまとめました。
| 級地区分 | 生活扶助 | 住宅扶助(上限) | 合計金額 |
|---|---|---|---|
| 1級地-1 | 190,550 円 | 69,800円 | 260,350円 |
| 1級地-2 | 185,750円 | 44,000円 | 229,750円 |
| 2級地-1 | 179,270円 | 56,000円 | 235,270円 |
| 2級地-2 | 179,270円 | 46,000円 | 225,270円 |
| 3級地-1 | 171,430円 | 42,000円 | 213,430 円 |
| 3級地-2 | 168,360円 | 42,000円 | 210,360円 |
申請は福祉事務所へ!手続きの流れ

続いて、生活保護の方法について5つのステップに分けて解説します。
① 福祉事務所で相談
生活保護を利用したい方はまず、あなたが住んでいる地域の福祉事務所の生活保護担当、もしくは自治体の担当窓口に相談してみましょう。
福祉事務所の生活保護を担当する窓口には、ケースワーカーと呼ばれる生活保護担当者がいます。
ここでは、生活保護制度について詳しく説明してくれます。
また、生活保護以外の年金や各種手当、医療費助成など、他の自立支援の方法がないかも確認されます。
② ケースワーカーによる家庭訪問
他に利用できる公的制度があれば、指示に従って改めて申請の手続きをおこなってください。
生活保護の申請をおこなうことで話しが進んだ場合は、手続きに必要な書類を記入して提出します。
生活保護の申請時に記入する書類は、以下のとおりです。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 生活保護申請書 | 世帯全員分の名前や職業、保護を受ける理由について。 |
| 資産申告書 | 不動産や自動車、生命保険などの保有資産や負債について。 |
| 収入・無収入申告書 | 給料や年金などの収入金額について。収入がない場合は無収入の理由。 |
| 一時金支給申請書 | 引っ越しにかかる費用など、支給してもらいたい費用について。 |
| 同意書 | 勤務先や金融機関などに収入について調査することへの同意。 |
一時金支給申請書は、家賃が住宅扶助の上限を超える場合や住居がない場合に記入する書類です。
引っ越しの予定がなければ、記入する必要はありません。
③ 扶養調査や関係機関への調査
上記の書類を全て揃え生活保護の申請をすると、本当に生活保護を必要としているのか調査されます。
主に以下のような内容の調査が行われます。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
ここで安心していただきたいのが、正当な理由もなく申請自体を却下されることはないという点です。
申請が却下されるのは、あくまでも調査を終えそれ相応の理由がある場合に限ります。
④ 生活保護の可否判定
これらの調査が全て終わり、生活保護の申請が通ると、自宅に「保護決定通知書」が送られてきます。
ケースワーカーからも電話または訪問による報告がありますが、トラブルを避けるために必ず書面を受け取り、大切に保管してください。
生活保護の判定は、早くて2週間、遅くても1ヶ月以内に行われることが生活保護法によってさだめられています。
第三項の通知は、申請のあつた日から十四日以内にしなければならない。ただし、扶養義務者の資産及び収入の状況の調査に日時を要する場合その他特別な理由がある場合には、これを三十日まで延ばすことができる。
引用元:生活保護法
申請から30日を過ぎても結果が出ない場合は、生活保護法で定められている期間から超過している旨を伝えて催促しましょう。
できるだけ早く生活保護を受給するためには、事前に必要書類を揃えておくことも大切です。
⑤ 受給開始
上記5つのステップが完了すれば、生活保護の受給が開始されます。
ほとんどの自治体は毎月5日に生活保護費が支給されますが、地域によっては1日や3日のところもあるようです。
また、生活保護が開始されるまでの生活費がない人は、社会福祉協議会の臨時特例つなぎ資金貸付を利用できる場合もあるため、確認してみてください。
生活保護を受ける注意点・デメリット

最後に生活保護を受給する上で注意すべき点やデメリットについて3つのポイントに分けて解説します。
受給中はローン・クレジットカードなど禁止
生活保護受給中には、各種ローンの組み込みやクレジットカードの使用が禁止されています。
これは、生活保護費が自立を目指すための支援として設計されているため、借り入れの返済に充てることが許されていないからです。
また、生活保護の基本方針として、「必要最低限の生活を維持する」という考えがあるため、高価な物品やサービスの購入にローンやクレジットカードを利用することは適切ではありません。
不正受給は支給停止に直結!逮捕のリスクも
生活保護の申請時および受給中は、現状を正確に申告する必要があります。
収入の増加や世帯人数の変更などがあれば、それを報告しなければなりません。
これを怠ると「不正受給」と見なされ、生活保護費の一部または全額の返還を求められることがあります。
悪質なケースでは、支給の停止や告訴される可能性もあります。
贅沢はできない?全ての収入をケースワーカーに報告
生活保護受給者は、最低限度の生活を送ることが求められ、贅沢品の所有や海外旅行などは制限されます。
例えば、マイカー、ブランド品、高価な貴金属などの保有は禁じられています。
海外旅行を計画する場合も、旅行の目的、日程、費用などについて事前に届出が必要です。
これらの制限は、生活保護の目的である「最低限の生活維持」に沿ったものです
まとめ:正確な受給金額を知りたい人は福祉事務所へ

生活保護は、条件を満たせば国民の誰でも受けられる権利であり、困窮している国民の最後のセイフティーネットのような役割を果たしています。
みんなの税金で生活するのは申し訳ないと感じたり、金銭的に困っていることを恥じる人もいますが、手遅れになってからではもう遅いです。
もし受給条件をクリアしているのであれば、まずは福祉事務所へ相談に行ってみましょう。
生活保護は最低限の生活をし続けるためではなく、あなたの生活を立て直すための助け船でもあるため、有効に活用することをおすすめします。