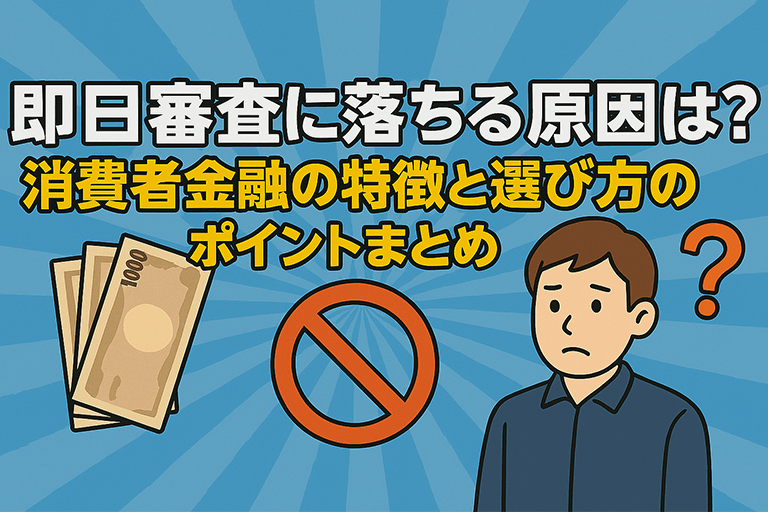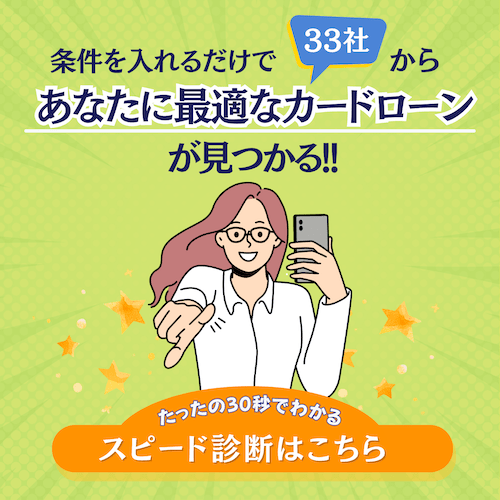消費者金融と差し押さえの関係性を解説
「消費者金融からの借り入れを滞納してしまったら、差し押さえを受けるのでは…」
と不安に感じている方も多いでしょう。
実際、滞納を続けると法的手続きを経て、給与や預貯金、不動産などの財産が差し押さえられる可能性があります。
しかし、すぐに差し押さえが実行されるわけではなく、適切な対応を取ることで回避できるケースも少なくありません。
本記事では、差し押さえの対象となる財産や滞納から強制執行に至る流れ・期間を解説します。
さらに、差し押さえを避けるための対策についても紹介しているので、冷静に対応するための参考にしてください。
消費者金融の返済を滞納すると差し押さえになる
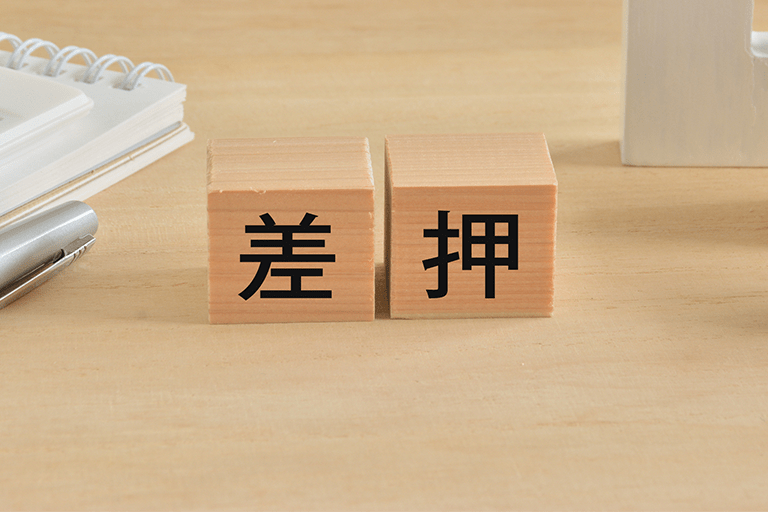
消費者金融の借金を長期間滞納すると、最終的に財産の差し押さえに至る可能性があります。
差し押さえとは、借金を返済しない場合に裁判所の命令によって財産を強制的に取り上げる法的手続きであり、対象財産は給与や預貯金、不動産などです。
消費者金融の借金を滞納すると、以下の流れで差し押さえに進むことがあります。
- 支払いの遅延
消費者金融から催促の連絡が入る - 長期滞納
数か月以上滞納すると債権回収会社へ債権が譲渡され、督促が強化される - 裁判所への訴訟提起
消費者金融が裁判所に支払い命令(支払督促)を求める - 差し押さえの決定
裁判所の命令後も支払いがない場合、給与や預貯金が差し押さえられる
滞納を続けると差し押さえに発展するリスクが高まるため、早めに消費者金融と相談して返済計画を見直すことが重要です。
差し押さえの対象財産

差し押さえの対象となる財産は債務者が所有する資産のうち、現金化しやすいものが中心です。
具体的には、以下のような財産が該当します。
- 債権(銀行口座の預貯金、給与、生命保険の解約返戻金など)
- 動産(現金、有価証券、車両、宝石、高級時計など)
- 不動産(土地や建物など)
特に、金融機関が差し押さえを行う際には銀行口座や給与債権が対象となりやすく、銀行口座の差し押さえが行われると引き出しができません。
また、給与の差し押さえには一定の制限があり、手取り額の4分の1までが対象となる場合もあります。
差し押さえの対象にならない財産
すべての財産が差し押さえの対象となるわけではありません。
生活に最低限必要なものや法律で保護されている財産は差し押さえが禁止されており、以下のような財産は対象外です。
- 生活必需品(衣類、寝具、家具など)
- 66万円以下の現金
- 年金受給権
- 児童手当・生活保護費の受給権
- 実印や位牌などの祭祀に関する物品
- 職業上必要な道具
また、給与の差し押さえには上限があり、手取り額が44万円未満の場合、4分の3は差し押さえの対象になりません。
消費者金融の滞納から差し押さえまでの流れと期間

消費者金融の借金を滞納すると、以下のような流れで手続きが進みます。
- ①滞納、消費者金融からの督促(1日~)
- ②一括請求通知、法的手続きの開始(~2か月程度)
- ③裁判所からの通知(~2か月程度)
- ④訴訟(~5か月程度)
- ⑤強制執行の申立て、差し押さえ(~6か月程度)
初期の段階で対応することで差し押さえを回避できる可能性があるため、状況を正しく理解しておくことが大切です。
ここでは、滞納から差し押さえまでの流れと期間を詳しく紹介します。
①滞納、消費者金融からの督促(1日~)
借金の返済期日を1日でも過ぎると消費者金融から電話や郵送で督促が始まります。
初期の段階では返済を促す内容が中心で柔軟な対応をしてもらえることが多いですが、放置すると遅延損害金が発生します。
遅延損害金の上限は年20%と高めに設定されており、滞納額や日数に応じて加算されていきます。
例えば、15万円を30日滞納すると約2,466円の遅延損害金が発生します。
この負担は滞納が長引くほど増え、借金総額が膨らむ原因となるため、できるだけ早く対応することが重要です。
②一括請求通知、法的手続きの開始(~2か月程度)
滞納が1〜2か月続くと消費者金融から「一括請求通知」が届きます。
残りの債務を一括で支払うよう求めるもので、無視すると法的手続きに進む可能性が高まります。
通知は内容証明郵便で送られることが多く、債権者が法的手段を視野に入れている証拠ともいえます。
適切な対応をしない場合は裁判を起こされるリスクがあるため、弁護士や債務整理の専門家に相談し、早急に解決策を検討することが重要です。
③裁判所からの通知(~2か月程度)
一括請求通知に応じなかった場合は消費者金融が裁判を起こし、裁判所から「支払督促」や「訴状」が特別送達で届きます。
支払督促を無視すると2週間後に「仮執行宣言付支払督促」が発令され、そのまま差し押さえ手続きへ進む可能性があります。
ただし、支払督促が届いてから2週間以内に異議申し立てをすれば債務の減額や分割払いの交渉が可能になる場合もあるため、早急に弁護士へ相談し適切な対応を取ることが重要です。
④訴訟(~5か月程度)
裁判が進行すると債務者が裁判所に出廷し、借金の支払い義務について争うことになります。
債務者が反論しなければ、裁判所は消費者金融側の主張を認めて支払い命令を下すことが一般的です。
⑤強制執行の申立て、差し押さえ(~6か月程度)
裁判所の判決が確定すると消費者金融は強制執行の申立てを行い、差し押さえが実行されます。
消費者金融の差し押さえを避ける方法

ここでは、消費者金融の差し押さえを避ける方を紹介します。
消費者金融に支払延期や相談する
借金の返済が厳しくなった場合は消費者金融に相談し、支払延期や返済計画の見直しを依頼することが重要です。
多くの金融機関は一時的な延滞であれば柔軟に対応し、返済期日の延長や分割払いの調整に応じることがあります。
早い段階で相談すれば延滞利息の増加を抑え、法的手続きに発展するリスクを軽減できるでしょう。
債務整理を検討する
消費者金融からの督促が続き返済が困難な場合は、弁護士に債務整理を依頼するのも一つの方法です。
債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」などの種類があり、状況に応じて適切な方法を選べます。
また、弁護士に依頼すると「受任通知」が消費者金融に送られ、その時点で貸金業者からの督促や電話連絡が止まります。
精神的な負担を軽減しながら、冷静に解決策を探ることができるため、早めに専門家へ相談することが重要です。
転職や退職、無職で差し押さえは中止になる?
消費者金融による差し押さえは転職や退職、無職になることで一時的に止まることはありますが、完全に免れるわけではありません。
給与差し押さえが行われている状況で職を変えた場合、次のような影響が生じます。
退職時の差し押さえ
退職すると元の勤務先への給与差し押さえは終了しますが、退職金が支給される場合はその一部または全額が差し押さえの対象になることがあります。
転職後の給与差し押さえ
転職先が決まった場合、新たな勤務先の給与も再び差し押さえの対象となります。
債権者が裁判所を通じて「債務者の新しい勤務先」を特定し、改めて差し押さえの申し立てを行うことが可能なためです。
債務者が転職先を隠しても財産開示手続きにより明らかになるケースが多く、虚偽報告には刑事罰が科せられる可能性もあります。
無職の状態でも差し押さえは可能
無職の場合、給与の差し押さえはできませんが、預貯金や持ち家、自動車などの財産があれば差し押さえの対象になります。
特に貯金が一定額を超える場合は、債権者によって金融機関に対し差し押さえの手続きが取られることも少なくありません。
まとめ

消費者金融の借入を滞納すると、最終的に給与や財産が差し押さえられる可能性があります。
滞納が続くと「督促」「一括請求」「訴訟」を経て「強制執行」へと進むため、早めの対応が重要です。