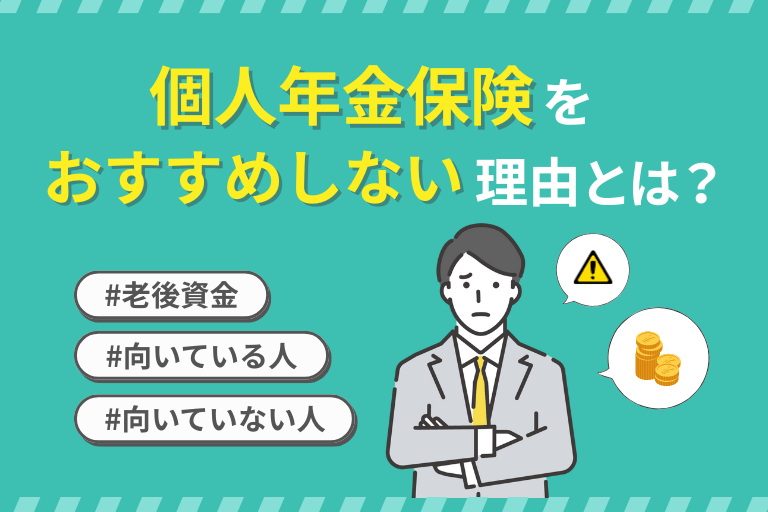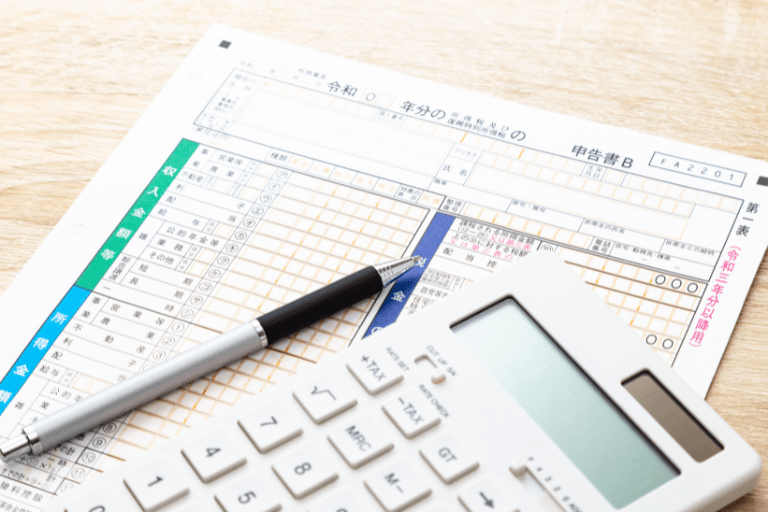個人年金保険とはどのような種類がある?老後に備えておきたい保障とは
老後の生活について考えたとき「現在の貯蓄や公的年金だけで生活を賄えるのか不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。
少しでも安心して老後の生活を送れるよう、今から計画をして資金を積み立てておくことはとても大切です。
そこで、老後の生活資金を準備するための一つの手段として個人年金保険が挙げられます。
本記事では、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、個人年金保険とはどのような保険商品なのか、その種類やメリット、デメリットについて解説します。
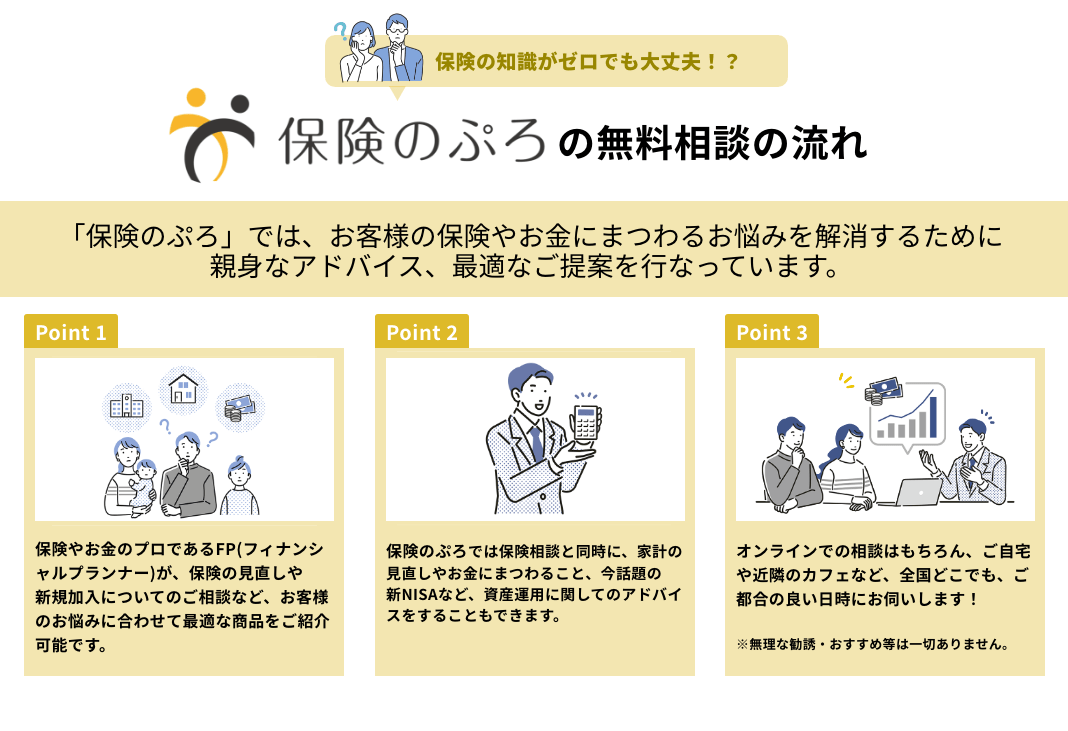
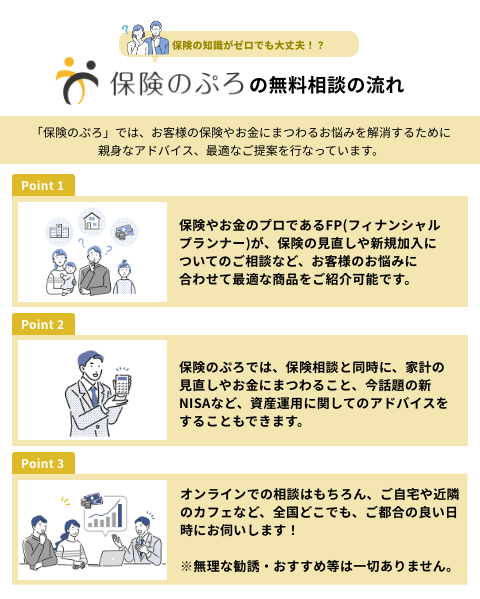
個人年金保険とはどんな保険商品?

個人年金保険とは、老後の生活資金を貯めるための生命保険です。
払い込まれた保険料を原資に、契約時に定めた年齢から月払いまたは一括で個人年金を受け取ることができます。
以下では個人年金保険の特徴や仕組みについて、具体的に解説していきます。
個人年金の受取方法により3種類に分けられる
個人年金保険は年金の受取方法によって「確定年金」「有期年金」「終身年金」の3種類に分類することができます。
以下では、それぞれの年金の種類とはどんなものなのか、その特徴や注意点を解説しています。
| 個人年金の種類 | 説明 | 被保険者死亡後の受け取り |
|---|---|---|
| 確定年金 | 被保険者の生死を問わず、契約時に決めた一定の期間に年金が受け取れる。 | 受け取りの期間が残っている場合、残りの年金または一時金が支払われる。 |
| 有期年金 | 生存している限り契約時に決めた一定の期間に年齢が受け取れる。 | 既払込保険料相当額または年金原資からすでに受け取った年金の合計額を差し引いた残額があれば一時金で受け取ることが可能。 ※生死に関わらず、一定期間年金が受け取れる保証期間付きのものあり |
| 終身年金 | 被保険者が生存している限り(一生涯)年金が受け取れる。 | 遺族に年金は支払われない※生死に関わらず、一定期間年金が受け取れる保証期間付きのものあり |
個人年金の運用方法により2種類に分けられる
また、個人年金保険は運用方法によって以下の2種類に分けることができます。
| 個人年金の種類 | 説明 |
|---|---|
| 定額個人年金保険 | 契約時に決めた予定利率で運用する。将来受け取れる年金額が確定しているが、インフレで大幅に物価が上昇した場合に、受け取れる年金の価値が目減りしてしまう。 |
| 変額年金型保険 | 契約者が選択した投資信託等で運用する。運用方法次第では、受取金額が払込保険料総額を上回ることもあるが、最低保証などがないために大きな損失を招く可能性もある。 |
【要チェック】保証期間とは
個人年金保険を検討する方が必ずチェックしなければならないのが保証期間です。
保証期間とは、契約時にあらかじめ設定した期間内に被保険者が死亡した場合でも、残りの保証期間に対応する年金または一時金を受け取ることができる期間のことです。
特に有期年金や終身保険は、この保証期間があるかないかで遺族が受け取れる年金の有無に影響するので、よく確認しましょう。
個人年金保険のメリット

老後資金作りの方法の一つである個人年金保険にはどんなメリットがあるのでしょうか?
個人年金保険の代表的なメリットとは以下のとおりです。
- 着実に老後資金を用意できる
- 年末調整・確定申告で個人年金保険料控除を受けて税金を安くできる
着実に老後資金を用意できる
個人年金保険の保険期間は、「保険料を払い込む期間(保険料払込期間)」と、「年金を受け取る期間(年金受取期間)」に分かれます。
保険料払込期間が終わって年金受取期間が開始すると、その後は契約時に定めた金額・期間で、個人年金を受け取れるので、着実に老後資金を用意することができるというメリットがあります。
例えば、保証期間付終身年金では、仮に被保険者が亡くなったとしても、遺族は残りの個人年金額または一時金を受け取れるので、商品の選択次第では、個人年金や一時金がムダになることはありません。
個人年金保険料控除を受けられ税金対策になる
1年間に払い込んだ個人年金保険料の全部または一部を、その年の所得から控除することができます。
控除を受けることで、所得税・住民税の対象となる課税所得が減るので、税金が安くなります。

ただし、控除を受ける際には「保険料の払込期間が10年以上あること」などの一定の条件があるので、年末調整や確定申告の際には注意が必要です。
以下に例として、個人年金保険料を年間8万円超支払った場合の個人年金保険料控除による軽減額を挙げておきます。
| 課税所得金額 | 所得税年間軽額 | 住民税年間軽減額 | 合計年間軽減額 |
|---|---|---|---|
| 330万円以上695万円未満 | 8,000円 | 2,800円 | 10,800円 |
| 695万円以上900万円未満 | 9,200円 | 2,800円 | 12,000円 |
| 900万円以上1800万円未満 | 13,200円 | 2,800円 | 16,000円 |
| 1800万円以上4000万円未満 | 16,000円 | 2,800円 | 18,800円 |
デメリットはある?

個人年金保険の代表的なデメリットとは以下のとおりです。
- 早期に解約すると元本割れのリスクがある
- インフレに弱い(インフレリスクがある)
- 払込保険料総額が数百万~1000万円以上と大きな金額がかかる
早期に解約すると元本割れのリスクがある
やむを得ない事情で個人年金保険を途中解約すると、解約返戻金が戻ってきますが、支払った保険料の総額よりも少なくなる「元本割れ」のリスクがあります。
特に、保険料の払い込みを開始してからあまり年数が経っていない場合は、解約返戻金がほとんどない場合もありますので、よく理解しておきましょう。
インフレリスクがある(インフレに弱い)
個人年金保険の保険料払込期間から年金受取期間を通じて物価が上昇、つまりインフレとなった場合に影響を受けてしまうというデメリットがあります。
インフレにより物やサービスの値段が上がっても年金の金額(価値)は契約通りなので、年金の価値が相対的に目減りしてしまうことになります。

個人年金保険が相対的にインフレの影響を受けてしまうことを理解しておきましょう。
払込保険料総額が数百万~1,000万円以上と大きな金額がかかる
個人年金保険は、払い込んだ保険料が年金の原資となるため、老後資金の足しにするにはそれなりに大きな金額の保険料を払い込む必要があります。
生命保険文化センターの調査によると、個人年金保険に加入している世帯が年間に支払っている保険料の平均は20万600円です。月額に直すと約1.6万円となります。
例えば、世帯主が40歳で個人年金保険に加入し、65歳まで平均である20万600円を毎年払い込んだ場合、その総額は618万円です。
毎月の保険料はさほど大きくなくても、総額ではかなりの大金と言えるでしょう。
個人年金保険の必要性とは?

これまで個人年金保険とはどのような保険なのかについて解説してきましたが、果たして私的年金を積み立てる必要はあるのでしょうか?
退職後は生活資金源が貯蓄または年金のみになるので、計画的に資金を形成する必要があります。
以下では、老後生活に必要な費用の目安と受け取れる年金額について解説します。
夫婦が老後に受け取れる公的年金は平均で約21万円
現在、厚生年金や国民年金を支払っている方の中には、将来具体的にどのぐらいの公的年金が受け取れるのか見当がついていない方も多いのではないでしょうか。
厚生労働省の「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、公的年金の平均年金月額は以下の通りです。
| 男子 | 女子 | |
|---|---|---|
| 国民年金 | 59,040円/月 | 54,112円/月 |
| 厚生年金 | 164,742円/月 | 103,808円/月 |
例えば、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、専業主婦への厚生年金の支給はありませんから、夫婦が受け取れる年金の合計は約27.7万円です。
また、自営業の夫婦の場合、国民年金のみの受給となるため、夫婦合計で約11.3万円となります。
老後に受け取れる年金額は公的年金への加入状況によって異なるので、自身が受け取れる年金の見込額を知ることが大切です。

年金見込み金額は、日本年金機構の「ねんきんネット」や毎年の誕生月に郵送される「ねんきん定期便」で確認することができます。
老後の家計支出の平均は約26万円
統計局の「家計調査報告 家計収支編」によると、消費支出の月平均額は27.7万円です。
また、生命保険文化センターの「2022(令和4)年度 生活保障に関する調査」によると、夫婦2人で老後にゆとりのある生活を送るには37.9万円必要であるという調査結果が出ています。
これらの生活費を先ほどの公的年金受給額に当てはめると以下のようになります。
| 夫婦の就業状況 | 年金受給額の合計 | 老後の平均生活費との差額 | ゆとりある生活費との差額 |
|---|---|---|---|
| 会社員と専業主婦 | 27.7万円 | ±0万円/月 | -10.2万円/月 |
| ともに自営業 | 11.3万円 | -16.4万円/月 | -26.6万円/月 |
上記の表から、老後の収入が公的年金だけとなると貯蓄を取り崩していくか、生活を切り詰める必要があることがわかるのではないでしょうか。
平均余命の伸びを考えると、これからリタイアする世代では老後生活が長期間にわたる可能性が高く、公的年金だけでは老後資金の不安が残ります。
公的年金に加えて、老後資金をいかに準備するかが重要になってきているといえます。
公的年金から得られる金額と老後の必要な生活資金とのギャップを解消するためには、計画的な貯金または私的年金などで資産計画をたて、将来を見据えた対策をしましょう。
まとめ

個人年金保険とは、老後の資金を着実に積み立て、公的年金や貯蓄で足りない分を補う私的年金のことです。
個人年金保険によってどの程度の期間の老後資金を用意したいか、および年金受取の確実性(被保険者が亡くなっても遺族が受け取れるかどうか)を考えて、プランを選択するのをおすすめします。
先に述べた個人年金保険の3つのタイプ、「終身年金」「確定年金」「有期年金」の特徴を押さえ、どれを選ぶのが自分にとってよりよい選択なのか、ぜひチェックしておきましょう。