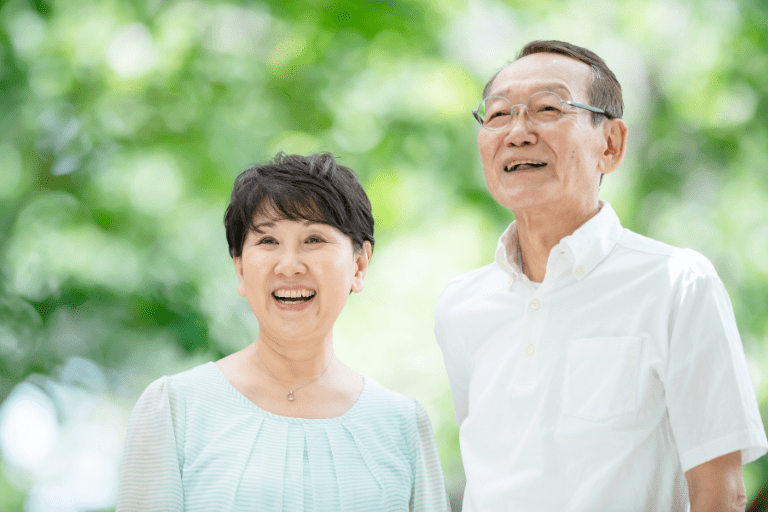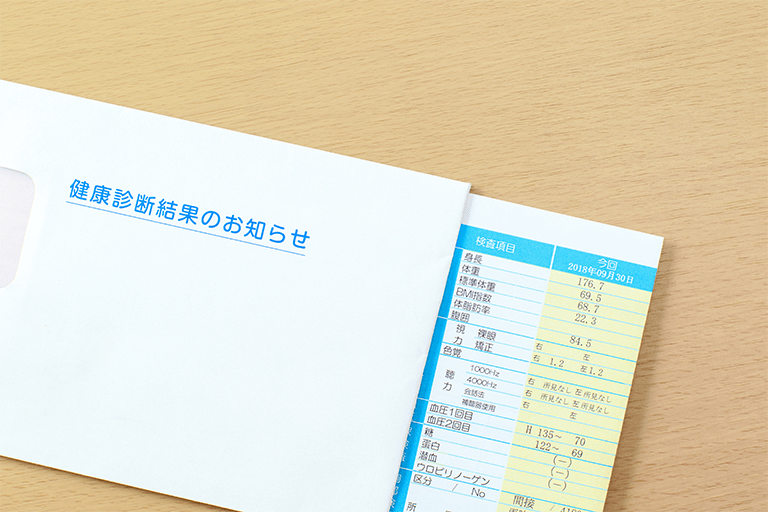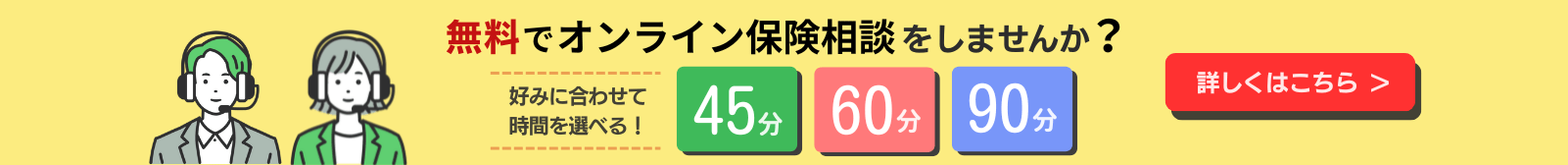大学生に医療保険は必要か?入らない場合や加入条件についても解説
進学によるライフステージの変化は、医療保険加入を検討すべきタイミングの1つです。
大学への進学を機会に「医療保険へ入るべきか」「どんな保障が必要か」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、大学生に民間の医療保険は必要かについて解説しています。
大学進学にあたり医療保険へ加入すべきか迷っている方、医療保険選びのポイントを知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
大学生に民間の医療保険は必要か?

大学生は年齢から考えると病気のリスクが低く「医療保険が必要か」は悩ましい問題です。
ここでは、大学生の民間医療保険加入率や医療保険に加入する必要性を解説します。
大学生の民間医療保険加入率
生命保険文化センター「令和4年度生活保障に関する調査」によると大学生が属する20歳代の民間医療保険加入率は以下のとおりです。
【医療保障に対する私的準備状況】
| 男性 | 32.8% |
|---|---|
| 女性 | 47.6% |
ただし、上記加入率は20歳代全体のデータであり、大学生に限って言えば、実際の民間医療保険加入率は上記データよりやや低いでしょう。
なお、医療保険加入率は全年代を通じて女性の方が高くなっており、男性より女性の方が病気やケガへの備えができていると言えます。
大学生が民間医療保険に入る必要性
大学生が民間の医療保険に入る必要性は家計状況や傷病歴などの条件によって異なります。
例えば以下の場合は、大学生であっても民間の医療保険に入る必要性が高いと考えて良いでしょう。
- 傷病歴やがあり健康面で不安を感じている
- 家族歴(血縁者の病歴)から考えて早めに医療保険へ加入したい
- 家計状況から医療費の支払いに不安を感じる
- サークル活動や部活動でケガのリスクが高い
- アルバイトで生計を立てている(入院時の収入減を医療保険で補てんできるため)
ただし、毎月の保険料負担が生活を圧迫しないよう、加入すべきか慎重に検討する必要があります。
大学生に起こりうるリスクと必要な保障

年齢から考えると、大学生は病気のリスクが低いのは事実です。
しかし病気によっては年齢に関係なく発症しやすいケースもあるため、大学生であってもリスクに備える必要があるでしょう。
ここでは大学生に起こりうるリスクと、必要な保障内容について解説します。
大学生にも高額な医療費がかかるケースとは
大学生にも高額な医療費がかかるケースとして、長期間の入院が挙げられます。
厚生労働省「令和5年 患者調査」によると、疾病による入院の平均日数は28. 4日です。
平均でみても病気やケガの際は入院日数が長くなる傾向があり、ある程度の医療費負担は必要と考えて良いでしょう。
傷病別では統合失調症や気分障害(うつ病や躁うつ病)など、若くても罹患しやすい病気で入院が長期化する傾向にあります。
【統合失調症・気分障害の平均入院期間】
| 傷病 | 平均入院日数 |
|---|---|
| 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 569.5日 |
| 気分障害(躁うつ病を含む) | 118.2日 |
出典 : 厚生労働省「令和5年 患者調査」
大学生は、がんや糖尿病、循環器系疾患の罹患率が低いものの、統合失調症や気分障害による入院に注意が必要と考えられます。
リスクに備えるために必要な保障内容
大学生がリスクに備えるためには、入院給付・手術給付を中心にしたシンプルな保障の医療保険がおすすめです。
大学生は長期入院や慢性疾患のリスクが低く、社会人になってから必要に応じて保障内容の見直しが可能なためです。
- 入院給付 : 1日あたり5,000円〜10,000円程度が目安
- 手術給付 : 手術1回あたり5万円〜10万円程度
保険会社にもよりますが、大学生であれば上記内容の医療保険に月額保険料1,000円〜2,000円程度で加入できます。
大学生が医療保険を選ぶときのポイント
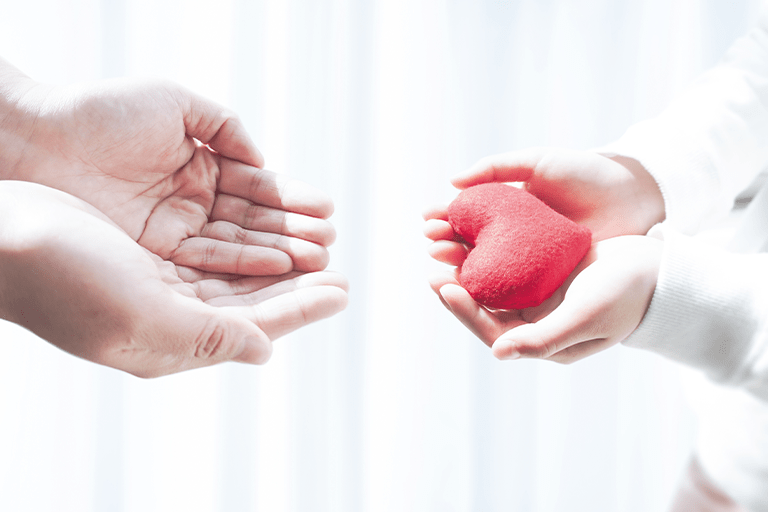
大学生は保険料に充てられる金額が限られる場合も多く、どの医療保険を選ぶか悩む方も多いでしょう。
ここでは、大学生が医療保険を選ぶときのポイントを解説します。
必要最低限の保障内容を選ぶ
大学生が医療保険へ加入する場合は、入院給付や手術給付を中心に必要最低限の保障内容を選びましょう。
給付金額を増やしたり、特約を充実させ過ぎたりすると保険料負担が大きくなり、生活を圧迫しかねないためです。
特に死亡保障特約や疾病特約(※)は保険料が高くなりがちなため、保障を追加するか慎重に検討する必要があります。
※がんや脳卒中、急性心筋梗塞など特定の疾病で一時金が支払われる特約
終身タイプの医療保険を選ぶ
大学生は契約年齢が低く保険料が安いため、同一保険料で一生涯同じ保障が受けられる終身タイプの医療保険を選ぶのがおすすめです。
一方、一定期間で契約更新が必要な定期タイプの医療保険では、契約更新のたびに保険料が上がり、高齢になると契約更新できない商品がほとんどです。
例えばA社の医療保険を20歳の時に同一の保障内容で契約した場合、終身タイプと定期タイプでは以下のとおり保険料が異なります。
| 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 終身タイプ | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 |
| 定期タイプ | 1,240円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,760円 | 5,580円 |
| 20歳 | 30歳 | 40歳 | 50歳 | 60歳 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 終身タイプ | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 | 1,740円 |
| 定期タイプ | 1,240円 | 1,580円 | 1,820円 | 2,760円 | 5,580円 |
定期タイプの医療保険は、特にリスクが高まる50代以降の契約更新時に保険料が高額になるため注意が必要です。
よくある質問
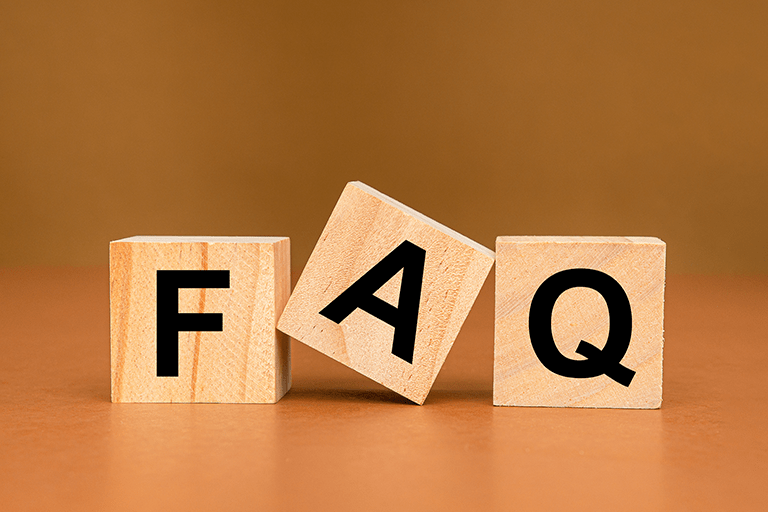
ここでは大学生の医療保険加入に関してよくある質問をまとめました。
医療保険に加入するか悩んでいる大学生の方は、ぜひ参考にしてください。
Q1.大学生は医療保険に入らないとどうなる?
日本は公的医療保険制度が充実しているため、医療費の自己負担割合は3割です(7歳〜69歳の場合)。
民間の医療保険に入らない場合でも、医療費が大きな負担になるケースは少ないと考えて良いでしょう。
また医療費が高額になった場合でも、高額療養費制度によって自己負担額は一定金額に抑えられます。
例えば入院や手術で100万円の医療費がかかった場合でも、実際の自己負担額はおよそ8万7千円程度で済みます。
自己負担額=80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
※世帯年収約370万円~約770万円の場合
ただし医療費のうち入院時の差額ベッド代(個室や少人数部屋を希望する際の費用)や一部費用は公的医療保険適用外のため全額が自己負担になります。
公的医療保険対象外の治療や処置が必要な場合、民間の医療保険に加入していないと自己負担額が大きくなる点には注意すべきでしょう。
出典:厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」
Q2.大学生の医療保険の加入条件は?
大学生が医療保険に加入する場合でも特別な加入条件はありません。
18歳以上であれば親権者の同意なく加入できる商品がほとんどです。
ただし加入時には健康状態の告知が必要で、既往歴や病気の治療状況によっては加入できない場合があります。
既往歴のある方は、加入しやすい引受条件緩和型医療保険(※)もあるため、健康状態に不安がある方は、保険会社に相談すると良いでしょう。
※告知項目を限定して加入条件を緩和した医療保険
Q3.社会人になってから医療保険に入るのは遅い?
社会人になってから医療保険に入っても、遅くはありません。
社会人になると、以下の理由から医療保険の必要性が高まるためです。
- 経済的に独立するため医療費を自分で支払う必要がある
- 生活環境の変化でストレスが増えるほか、生活習慣病のリスクが高まる
- 通勤中や仕事中のケガなど社会人特有のリスクが高まる
ただし、大学生のうちに医療保険へ加入すると保険料が安く、傷病歴や持病など健康状態の告知で有利になる可能性もあります。
大学生のうちに加入する場合は、保険料負担を考慮して無理のないプランを選ぶのがおすすめです。
記事まとめ:次のページでは18歳におすすめの医療保険をご紹介
大学生に医療保険が必要かどうかは、家計の状況や傷病歴などの条件によって異なります。
病気やケガの際にかかる医療費から「入らない場合はどうなるか」「家計への負担はどうか」を考え慎重に判断すべきでしょう。
本記事をお届けした「保険のぷろ」では、無料で医療保険の加入相談を承っています。
「必要な保障内容は?」「自分に最適な商品は?」などお悩みの方は、ぜひ「保険のぷろ」へご相談ください。
また次の記事では、大学へ入学する18歳の方に向けて最適な医療保険選びを解説していますので、ぜひあわせてお読みください。