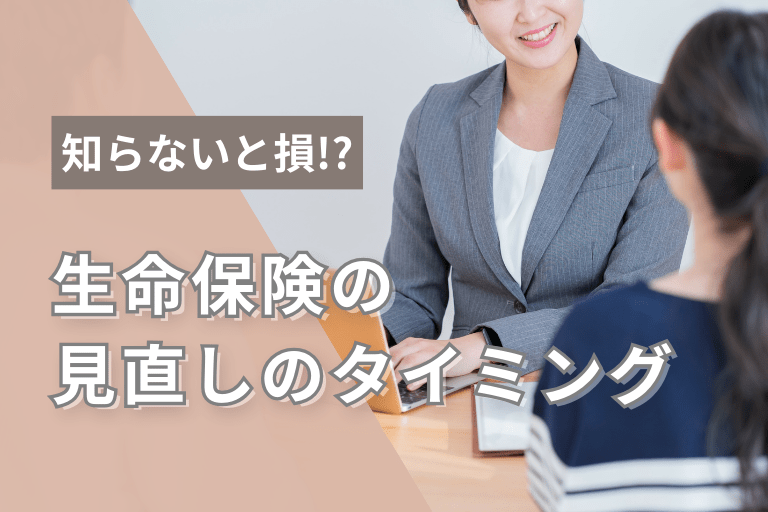生命保険における満期保険金の仕組みと受取時の税金について解説
生命保険に加入する際は、事前に生命保険の“満期”に関する基本知識を身につけておくことが大切です。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、生命保険における“満期”の定義と満期保険金を受け取れる保険の種類について解説します。
満期保険金の受け取りにかかる税金の仕組みもまとめているので、生命保険への加入を予定している方、また既に加入中の方もぜひ参考にしてみてください。
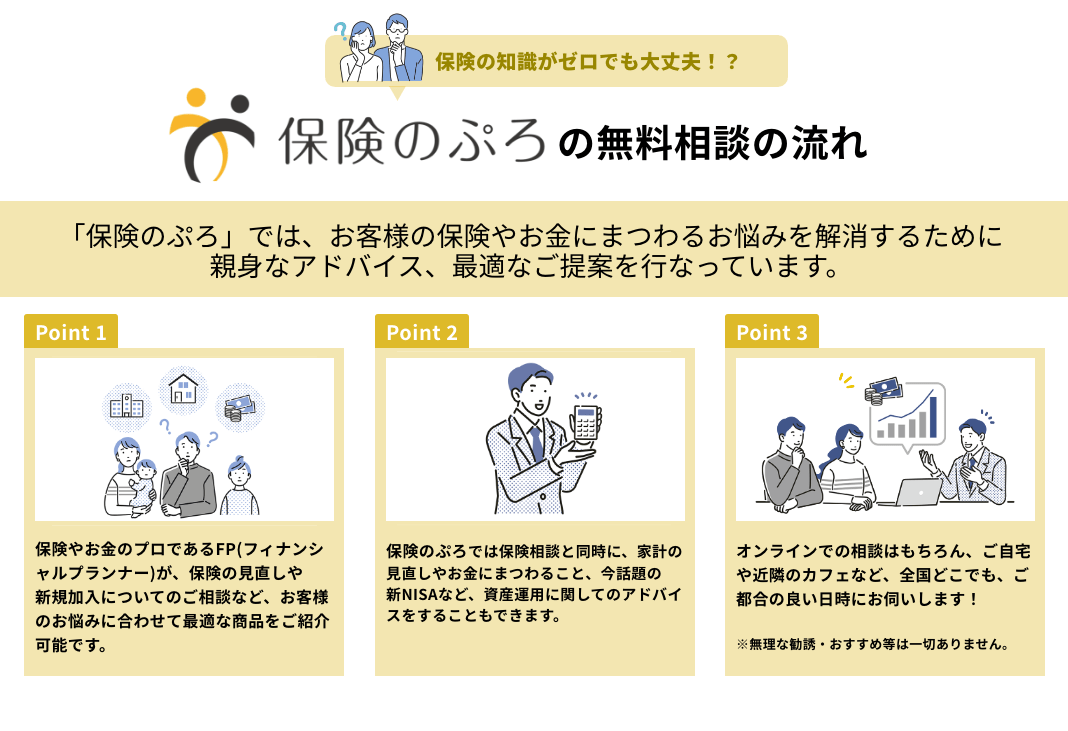
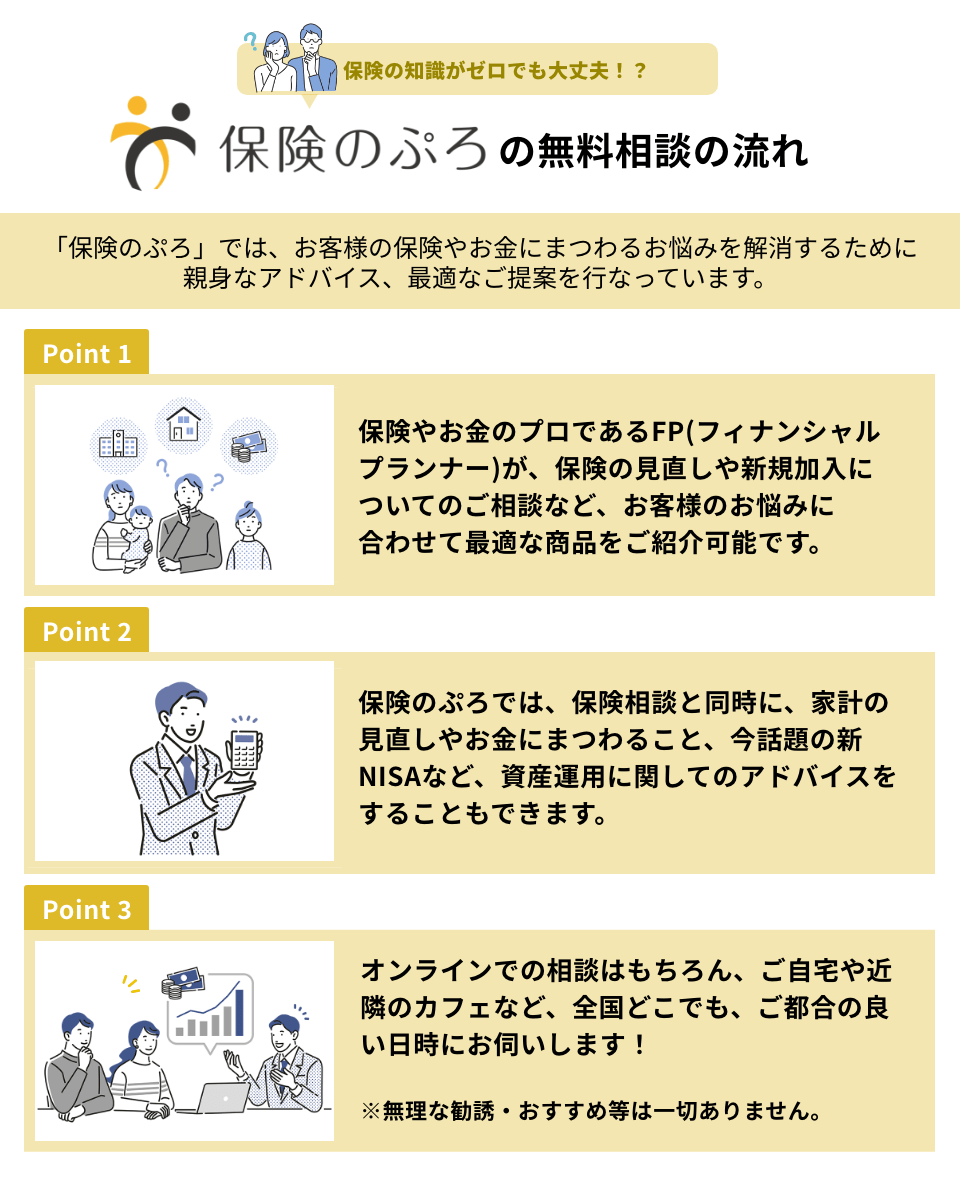
生命保険における「満期」の定義とは?

まずは、生命保険における“満期”の定義と満期保険金の仕組み・特徴を詳しく見ていきましょう。
また満期保険金と混同されやすい解約返戻金との違いについても解説していきます。
満期とは“保険期間が満了を迎えるタイミング”のこと
生命保険における“満期”とは、契約時に取り決めた保険期間が満了を迎えるタイミングのことです。
この“満期”の定義や対応については、契約している生命保険の種類によって以下のように異なります。
| 生命保険の種類 | 満期となる時期 | 満期保険金 |
|---|---|---|
| 掛け捨て型 | 保険期間が終了し、契約の更新が必要になるタイミング | なし |
| 貯蓄型 | 保険期間が終了するタイミング | あり |
| 終身型 | なし | なし |
掛け捨て型の生命保険は、保険期間が10年や20年といった単位で区切られており、保障を継続したい場合には満期のタイミングで契約を更新する必要があります。
基本的には契約更新または解約の2択になるため、満期を迎えても満期保険金を受け取ることはできません。
一方、貯蓄型の生命保険は満期と同時に保険料の払込も終了となるため、保険期間中に支払った保険料の金額に応じて満期保険金を受け取ることができます。
また終身型の生命保険は解約しない限り一生涯保障が続く商品であるため、そもそも満期という考え方がありません。
満期保険金と解約返戻金の違いは?
解約返戻金とは、生命保険の契約を途中で解約した場合に払い戻されるお金のことです。
| 保険金の種類 | 説明 |
|---|---|
| 満期保険金 | 保険期間が満期を迎えたときに受け取ることができるお金 |
| 解約返戻金 | 保険期間の途中で解約したときに払い戻されるお金 |
解約返戻金の金額は解約までに支払った保険料の金額に応じて決まりますが、運用経費等でその一部が差し引かれるため、支払った保険料よりも解約返戻金の方が少なくなるケースがほとんどです。
満期保険金は支払った保険料よりも多い金額を受け取れる場合があるため、基本的には途中解約をせずに満期まで契約を続けた方がお得だと言えるでしょう。
なお生命保険の種類によっては、保険料が安い代わりに解約返戻金が少ない(低解約返戻金型)もしくな無い(無解約返戻金型)ケースもあります。

生命保険を契約する際は、解約返戻金の有無やその種類についても確認しておくと良いでしょう。
満期保険金を受け取れる保険の種類

満期保険金を受け取ることができるのは、保険期間が定められている貯蓄型の生命保険に限られます。
続いて、貯蓄型の生命保険に該当する「養老保険」「学資保険」「生存給付金付定期保険」の3つの保険について、それぞれの特徴や違いを詳しく見ていきましょう。
養老保険
養老保険は、老後に備えてお金を積み立てるための生命保険で、死亡保障と貯蓄性を兼ね備えている点が特徴です。
保険期間中に被保険者が死亡または高度障害となった場合は死亡保険金(または高度障害保険金)を受け取ることができ、生存した状態で満期を迎えた場合は死亡保険金と同額の満期保険金を受け取ることができます。
掛け捨ての生命保険に抵抗のある方や、満期時にまとまった金額を受け取りたい方は養老保険の活用を検討してみると良いでしょう。
ただし、養老保険は死亡保障のみの生命保険と比較して保険料がやや高い傾向にあるため、加入を検討する際は満期保険金額と払込保険料の総額を比較し、元本割れが起こらないよう注意する必要があります。
学資保険
学資保険は、長期の積み立てによって子どもの教育資金を準備するための生命保険です。
満期の設定を子どもの入学や進学のタイミングに合わせることで、出費が増える時期にまとまった金額(満期保険金)を受け取れるのが特徴です。
また学資保険には、貯蓄を目的とした「貯蓄型」と、死亡保障や医療保障のついた「保障型」があります。
保障型の商品であれば、保険期間中に親(契約者)に万が一のことがあった場合、保障内容はそのままでその後の保険料の支払いを免除してもらえるというメリットがあります。
「子どもの将来のために資金を用意しておきたい」「自分に万が一のことがあっても子どもが困らないようにしたい」といった場合は、学資保険への加入を検討してみるのがおすすめです。
なお養老保険と同様、学資保険も商品によっては元本割れが起こる可能性があるため、契約前に満期保険金額と払込保険料の総額を比較し、メリットのある商品を選ぶようにしましょう。
生存給付金付定期保険
生存給付金付定期保険は、一定期間ごとに生存給付金を受け取ることができる生命保険です。
掛け捨ての定期保険をベースにしつつ貯蓄性も付加されているのが大きな特徴で、満期保険金とは別に、3年や5年といった期間ごとの生存給付金を受け取ることができます。
生存給付金があるため、一般的な掛け捨て型の生命保険と比較して保険料は高めに設定されていますが、掛け捨て型の生命保険に抵抗のある方や、定期的にまとまった金額を受け取りたい方にはおすすめの生命保険だと言えるでしょう。
満期保険金の受け取りには税金がかかる点に注意

生命保険の満期保険金を受け取った際には、所得税や贈与税といった税金がかかる点に注意が必要です。
“保険料の支払いを行う人”と“満期保険金を受け取る人”が同一かどうかによってかかる税金の種類や計算方法が変わってくるため、それぞれのケースを確認しておきましょう。
ケース①契約者と受取人が同じ場合:所得税
生命保険の契約者と受取人が同一の場合は、生命保険の満期保険金に対して所得税がかかります。
なお生命保険の満期保険金を一時金として受け取った場合は「一時所得」、年金形式で受け取った場合は「雑所得」として計算が必要となる点に注意しましょう。
契約者と受取人が同一かつ満額を一括で受け取るケース
生命保険の契約者と受取人が同一で、満期保険金を一時金として受け取るケースでは、満期保険金から保険料の払込総額と特別控除(50万円)を差し引いた金額の1/2に対して所得税が発生します。
課税所得=(満期保険金-払込保険料の総額-特別控除50万円)×1/2
満期保険金が「払込保険料の総額+特別控除50万円」以下の場合は税金がかかりません。
また給与所得者の場合、課税額が20万円以下であれば確定申告や年末調整を行う必要はありません。
所得税の計算に用いる税率は収入がいくらあるかによって異なるため、国税庁のHPで確認しましょう。
契約者と受取人が同一かつ満額を年金で受け取るケース
生命保険の契約者と受取人が同一で、満期保険金を年金として受け取るケースでは、年間の年金額からその金額に対応する払込保険料を差し引いた金額の1/2に対して所得税が発生します。
課税所得=(年間の年金額-年間の年金額に対応する払込保険料)×1/2
なお給与所得者の場合、課税額が20万円以下であれば確定申告を行う必要はありません。
所得税の計算に用いる税率は収入がいくらあるかによって異なるため、国税庁のHPで確認しましょう。
参考:国税庁 「No.2260 所得税の税率」
ケース②契約者と受取人が異なる場合:贈与税
生命保険の契約者と受取人が異なるケースでは、満期保険金およびその他の贈与額から贈与税の基礎控除額(110万円)を差し引いた金額に対して贈与税が課せられます。
課税所得=満期保険金+その他の贈与額-基礎控除110万円
満期保険金を含む年間の贈与額が「基礎控除110万円」以下の場合は税金がかかりません。
課税所得に対する贈与税の税率と控除額はそれぞれ以下の通りです。
| 基礎控除後の課税額 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 3,000万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | ‐ | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
参考:国税庁 「No.4408 贈与税の計算と税率」
生命保険を見直した方が良いケースとは

満期保険金を受け取ることができる場合でも、保険料の負担が大きくて家計を圧迫しているといった状況であれば途中解約を検討する必要があるでしょう。
最後に、生命保険の見直しや解約を検討すべきタイミングと注意点について詳しく見ていきましょう。
保険料の支払いが負担に感じる場合
生命保険の契約更新で保険料が上がったり、何らかの理由で収入が下がったりすることで、生命保険の保険料を支払い続けることが困難になる場合があります。
このような状況で無理に保険料を支払い続けると、家計が圧迫されて日常生活に支障をきたしてしまう可能性があるため、解約返戻金を十分に受け取れるタイミングで解約を検討してみるのも1つの手です。
また、保険料の払込を中止して、その時点での解約返戻金をもとに同じ保険期間かつより保険料の安い生命保険に切り替える「払済保険」の制度を活用するのも良いでしょう。

もし他の保険と部分的に保障内容が重複しているという場合には、双方の契約内容を見直して最適化するのもポイントです。
解約返戻金額が払込保険料を上回っている場合
貯蓄性のある生命保険の場合、満期よりも早い段階で解約返戻金が払込保険料の総額を上回るケースがあります。
すでに長期の払込を行っている場合や、満期まであまり遠くないといった場合には、一度解約返戻金の金額を確認してみると良いでしょう。
解約返戻金が払込保険料の総額を上回っているようであれば、無理に満期を待つ必要はないため、その時点で解約を検討してみても良いかもしれません。
記事まとめ

- 生命保険の“満期”とは、契約時に取り決めた保険期間が満了を迎えるタイミングのこと
- 養老保険・学資保険・生存給付金付定期保険等の貯蓄型保険は満期時に満期保険金を受け取ることができる
- 満期保険金には所得税または贈与税がかかる場合があるため申告漏れ等に注意が必要
満期保険金と解約返戻金は、生命保険の種類・プラン等によって条件や金額が様々であるため、契約前にしっかりと確認して、適切な保障を受けられるようにすることが大切です。
また満期保険金には税金がかかるため、自分の加入年齢が何歳かに関わらず、受取人や受取方法についてもじっくり検討し、なるべく税負担が少なく済むような契約方法を選択しましょう。