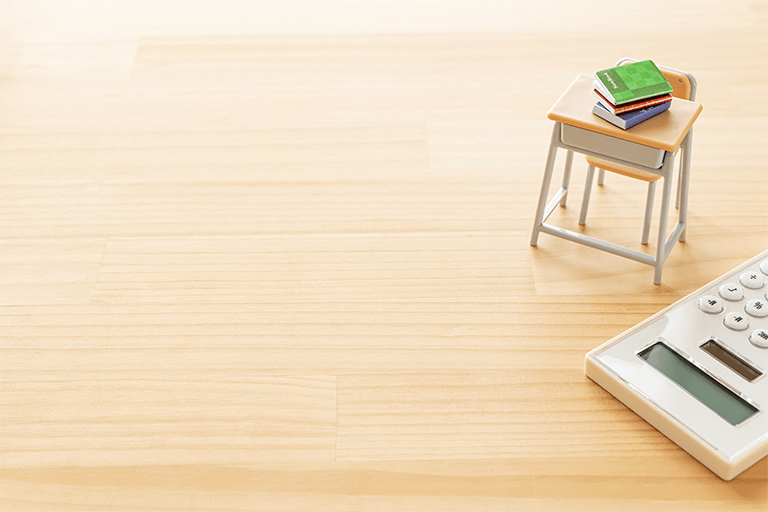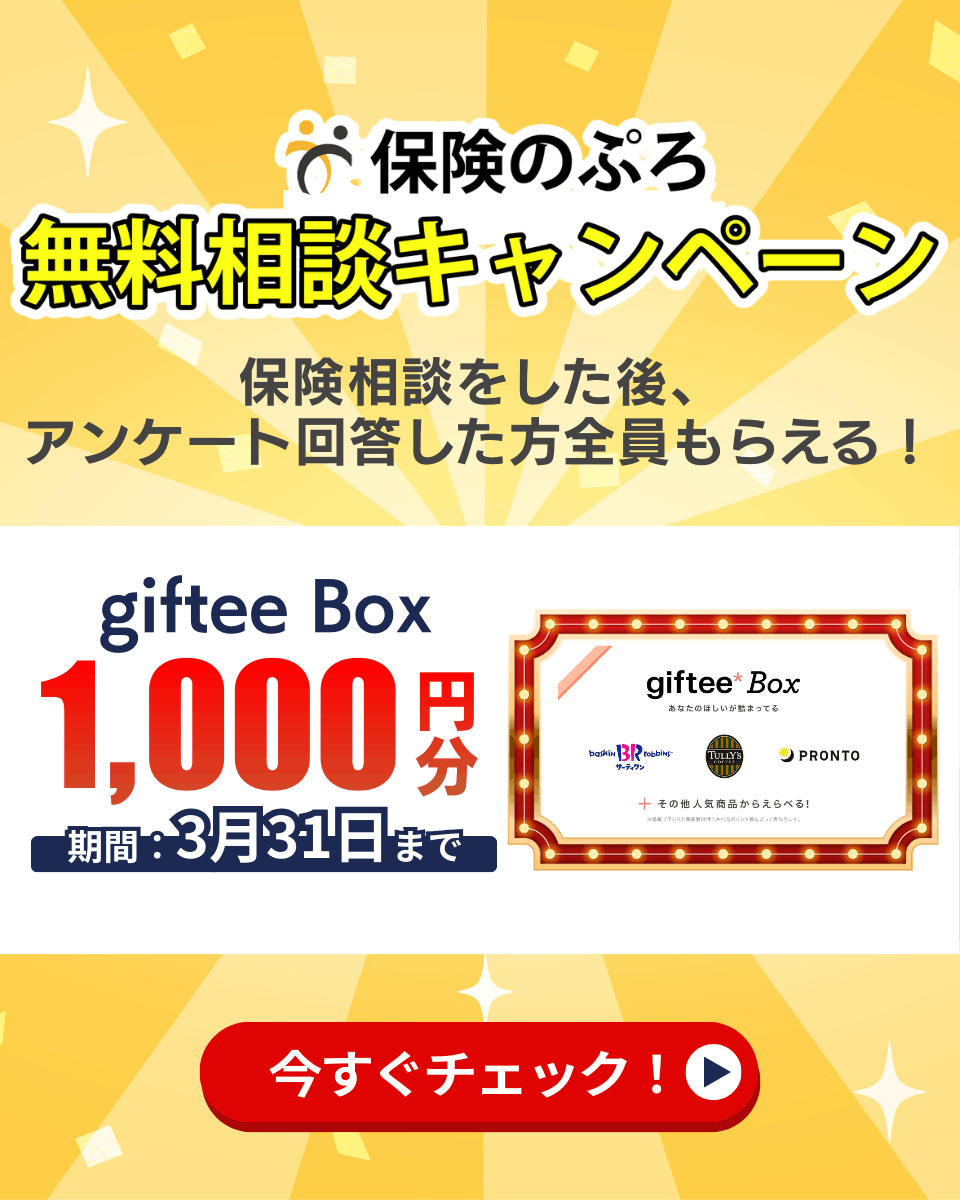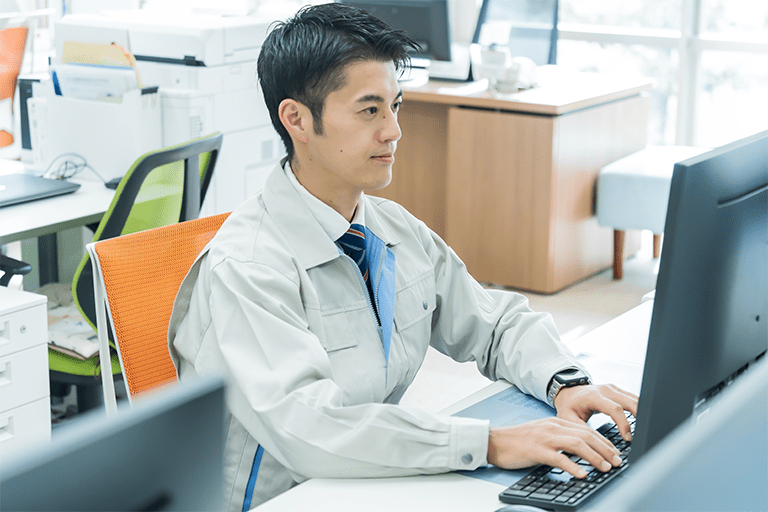
公務員に生命保険は必要ないって本当?必要性の高い人の特徴も紹介

公務員に生命保険は必要ない?
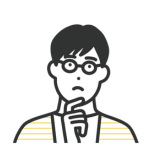
公務員で共済組合と生命保険のバランス悩んでいる
上記のように、公務員で生命保険に入るか、共済組合と生命保険のバランスをどうするか悩んでいる人もいるでしょう。
公務員に生命保険は不要との意見もあり、入るか悩んでいる人も少なくありません。
今回は、無料保険相談を行っている「保険のぷろ」が、公務員に生命保険はいらないと言われている理由を紹介します。
生命保険に入るべき人の特徴も解説しているので、保険に入るか悩んでいる人はぜひご覧ください。
導入:公務員が入っている「共済組合」について
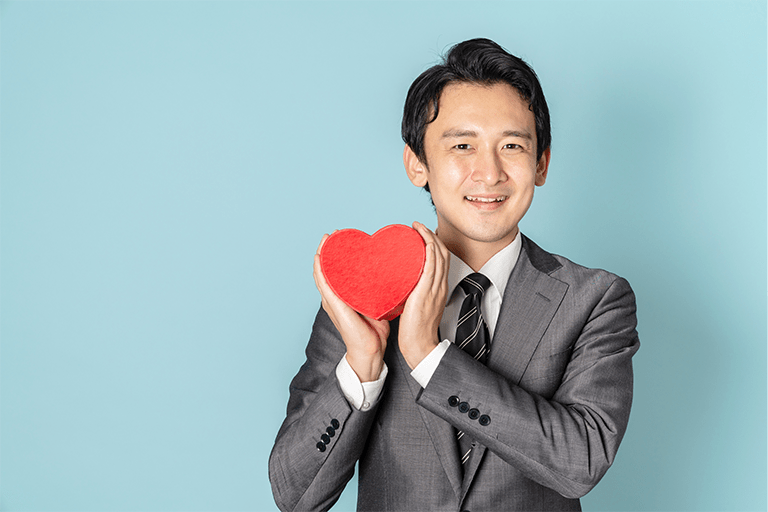
公務員が入っている「共済組合」とは、国民皆保険制度の1つです。
日本では、国民皆保険制度を採用しており、日本国民全員が公的保険に入っています。
なかでも「共済組合」は、組合員がお互いに費用を出し合い、相互サポートする制度です。
一般的に共済組合は健康保険に比べると、経済的負担が軽い傾向があります。
また、共済組合には「短期給付」と「長期給付」の2種類があり、違いは以下の通りです。
| 保障 | |
|---|---|
| 短期給付 | ・疾病・怪我・出産・死亡に対して給付を受けられる ・組合が独自で支給する給付もある |
| 長期給付 | ・退職後や障害状態、死亡時などに手当を受けられる |
短期給付が公的医療保険、長期給付は公的年金制度に近いイメージです。
公務員に生命保険は必要ないと言われる3つの理由
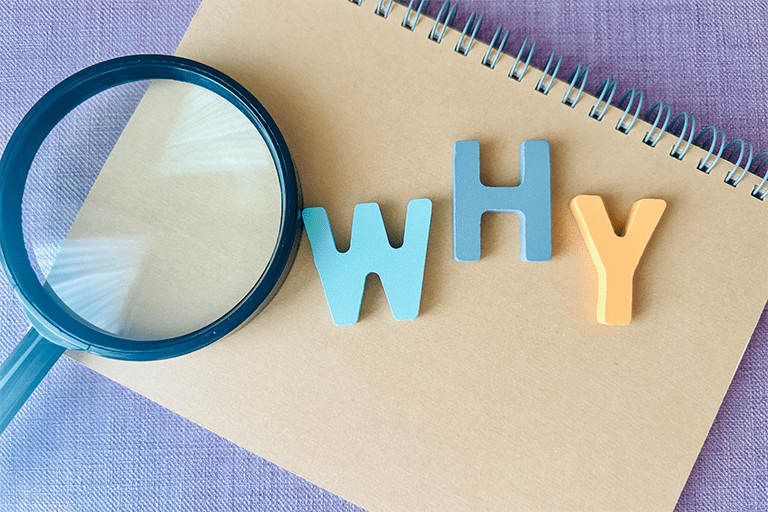
公務員は、疾病や怪我で休んだ際の保障が手厚かったり、団体保険に入れたりする点から生命保険は不要と言われています。
高額な医療費が必要になった場合、サポートを受けられるのも公務員の特徴です。
ここからは、公務員に生命保険は不要と言われている理由を3つ紹介します。
疾病やケガで休職した時の保障が手厚い
疾病やケガで休んでも、手厚い保障を受けられるのが、生命保険は不要と言われる理由の1つです。
公務員は疾病やケガで休むと、休暇開始から90日間は「疾病休暇」扱いになります。疾病休暇扱いになると、給与の全額が支給されます。
90日を超えて休暇を取得した場合でも、1年間は給与の80%の受け取りが可能です。
最低でも1年間は、給与を受け取れるため、疾病やケガをしても保障が手厚いとされています。
ただし、休暇取得2年目以降の給与支給はありません。会社員と同様に「傷病手当金」の給付金を受けられます。
高額な医療費への保障も手厚い
公務員は、高額な医療費への保障も手厚い傾向にあります。
基本的に、1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えても、会社員と同様「高額療養費制度」が適用されます。
さらに、医療費が所定の限度額を超えた場合、一部が返戻金として給付される「一部負担金払戻金」制度も特徴です。
たとえ、医療費が高額になっても、会社員に比べると手厚いサポートを受けられるのが公務員のメリットです。
団体保険に入れる
団体保険に入れるのも、生命保険は不要と言われている理由です。
団体保険とは、共済組合の組合が契約者となり、団体所属者を被保険者とする制度を指します。
団体割引によって個人で保険に入るよりも、安く入れるのがメリットです。
多くの公務員が団体保険に入っているため、民間の保険は不要と考える人も多い傾向にあります。
生命保険の必要性が高い人の特徴は?

配偶者や子どもがいたり、十分な貯蓄がなかったりする人は、生命保険の需要は高いと考えられます。
現状の公的制度だけではサポートが不十分だと、自己負担で医療費を支払わなくてはならないリスクもあるため、注意が必要です。
生命保険に入るのがおすすめな人の特徴を3つ紹介します。
配偶者や子どもがいる人(増える予定がある人)
結婚をしたり子どもができたりなど、今後家族が増える予定のある人は、生命保険の必要性も高まります。
公的保険制度以外の保険に入っていれば、万が一の際でも家族を支えられます。
求められる商品のサポート内容は、家族構成や収入、ライフプランによって異なるのが特徴です。
家族の数が多ければ多いほど、必要なサポートの需要も高まります。
自己負担に対応できる貯蓄がない人
怪我や疾病の際、自己負担に対応できる貯蓄がない人も、生命保険に入るか検討しておきましょう。貯蓄があれば、疾病やケガをした際でも、十分に対応できます。
しかし、貯蓄がないと自己負担で対応しなくてはなりません。
怪我や疾病で自己負担が必要な際に、貯蓄で対応できない方は、生命保険の加入を検討しておきましょう。
公務員からの転職を考えている人
会社員に転職を考えている人も、生命保険に入っておくと良いでしょう。
公務員であれば、疾病休暇により1年間は給与の80%以上を受け取れたり、高額医療に対する手当を受け取れたりします。
しかし、会社員になると疾病やケガに対する手厚いサポートは受けられません。
高額医療費制度や傷病手当などはあるものの、公務員より手厚いサポートは受けられないため注意が必要です。
会社員への転職を考えている人は、万が一の際に十分な手当を受けられるよう、生命保険に入るか検討しておくといいでしょう。
共済組合とのバランスの取れた保険の考え方
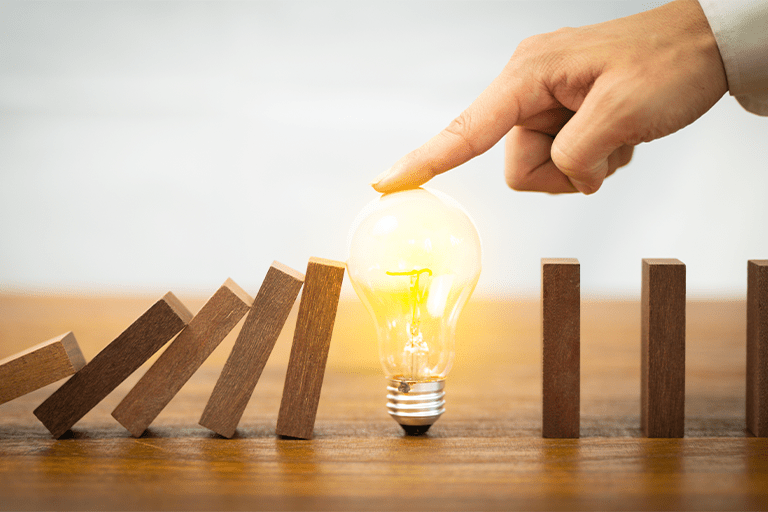
公務員で民間の保険に入る際は、共済組合と生命保険のバランスを考える必要があります。
公的保障で不足する部分を補ったり、サポート内容を見直す前提で選んだりしましょう。
ここからは、共済組合とバランスの取れた保険の考え方を紹介します。
公的保障で不足する部分を補う形で入る
公務員は、公的保障で不足する部分を補う形で民間の保険に入るのがおすすめです。
現状、十分な医療保障があり、問題なければ、民間の医療保険の必要性は低いと考えられます。
一方で、がんに対するサポートが薄いと感じている場合は、民間の医療保険でがんへのサポートを手厚くしておくと安心です。
共済組合や団体保険で十分なサポートを受けられるケースもありますが、不足していると、自己負担で医療費を賄わなくてはなりません。
不足部分を補うため、公的保障で不足している部分を明確にしたうえで、保険に入るか検討しましょう。
保障内容を定期的に見直す前提で選ぶ
団体保険や民間の保険は入った後も、ライフプランに合わせて見直しが必要です。
保険に入った当時は独身でも、配偶者や子どもができると、必要なサポートも変わってきます。
子どもが幼い頃は、万が一の事態に備えて死亡保険を手厚くしたとしましょう。
しかし、子どもが成人して自立した場合は、世帯が別になるケースも多いため、手厚い死亡保険の必要性は低くなります。
ライフステージによって必要なサポートは異なるため、共済保険と民間の保険で十分なサポートを受けられるか見直す前提で商品を選びましょう。
家計の状況に合わせて選ぶ
家計の状況に合わせて入る保険を選ぶのがおすすめです。
保険には「掛け捨て型」と「貯蓄型保険」の2種類があります。
掛け捨て型保険は、入った後に保険金は払い戻される可能性はありませんが、保険料は安いのが特徴です。
一方で貯蓄型保険は、毎月の料金は高いものの、途中解約時に支払った一部が「解約返戻金」として戻ってきます。
解約返戻金を老後資金として活用する方法もありますが、保険料で家計が圧迫されてしまっては意味がありません。
商品ごとのメリットやデメリットを踏まえ、家計に合った商品を選びしましょう。
記事まとめ

公務員は、公的保険制度で疾病やケガに対する手厚いサポートを受けられたり、団体保険に入ったりできるため、生命保険は不要と言われています。
しかし、配偶者や子どもがいたり、十分な貯蓄がなかったりする場合は、生命保険に入っておくといいでしょう。
また、会社員へ転職を考えている人も、今まで通りの金銭的なサポートを受けられなくなるため、生命保険に入っておくのがおすすめです。
共済組合と生命保険の両方に入る際は、共済組合で不足する部分を補える保険に入りましょう。
保険商品を選ぶ際は、家計やニーズに合った商品を適切に選ぶのも大切です。
「民間の保険は不要」と考えず、必要なサポートを今一度確認しておきましょう。