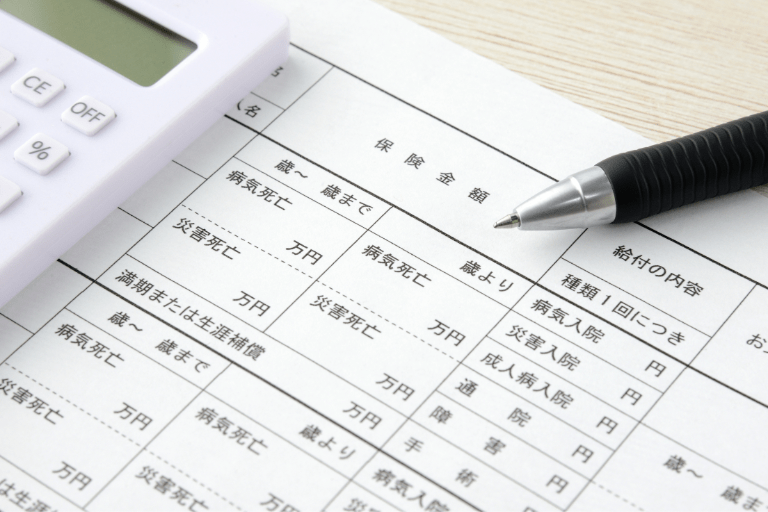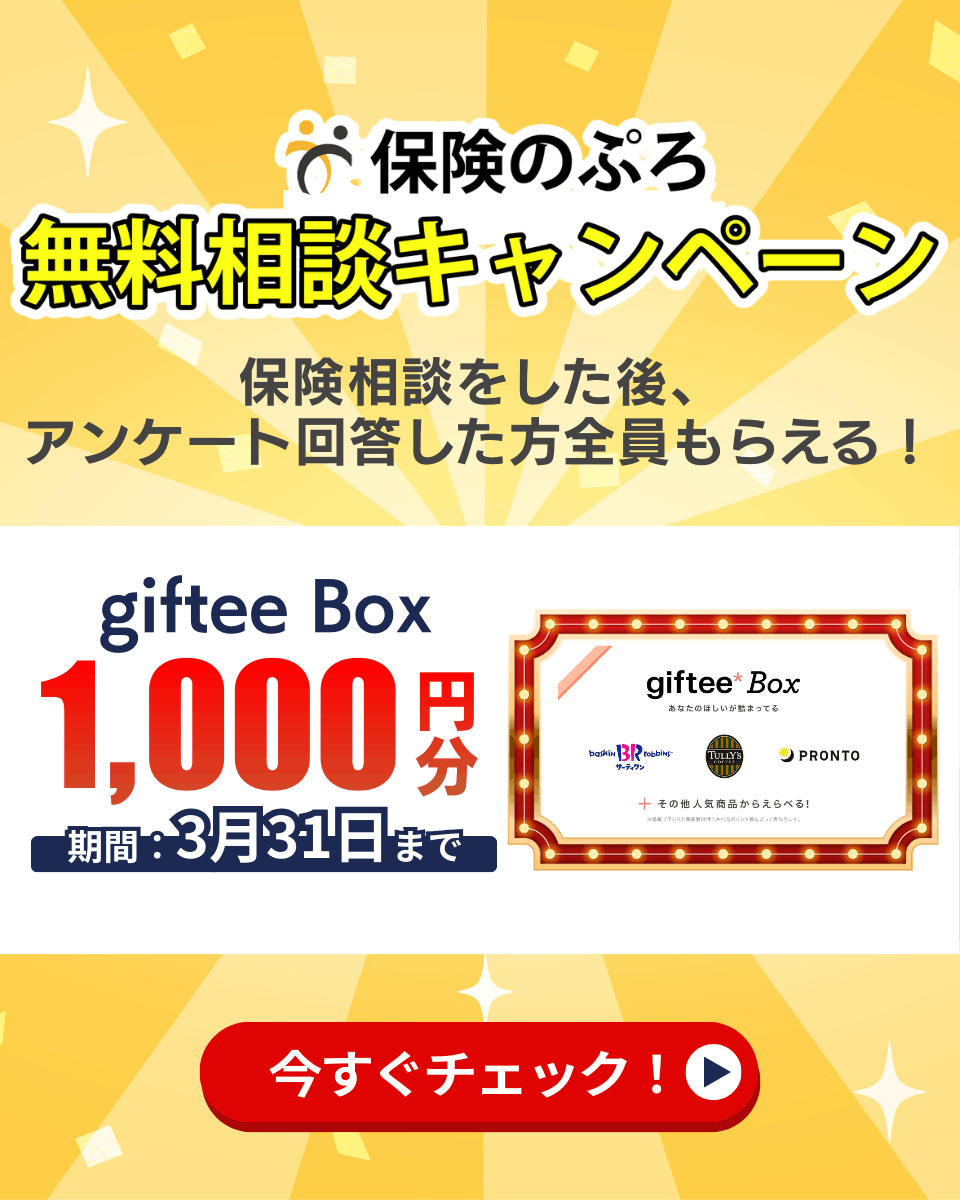生命保険受け取りにかかる税金の種類とは?控除や非課税枠、計算方法を解説
生命保険は、保険金や給付金を受け取る際に税金がかかる場合も多く、商品や契約内容により税金の種類が異なります。
「どの保険商品で税金がかかるのか」「税金を減らすためには」と疑問に感じる方も多いでしょう。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、生命保険受け取りの際にかかる税金について解説します。
所得税を軽減できる生命保険料控除や、相続税を軽減できる生命保険金の非課税枠もお伝えします。生命保険にかかる税金について気になる方は、ぜひ参考にしてください。
生命保険に関わる税金の基本
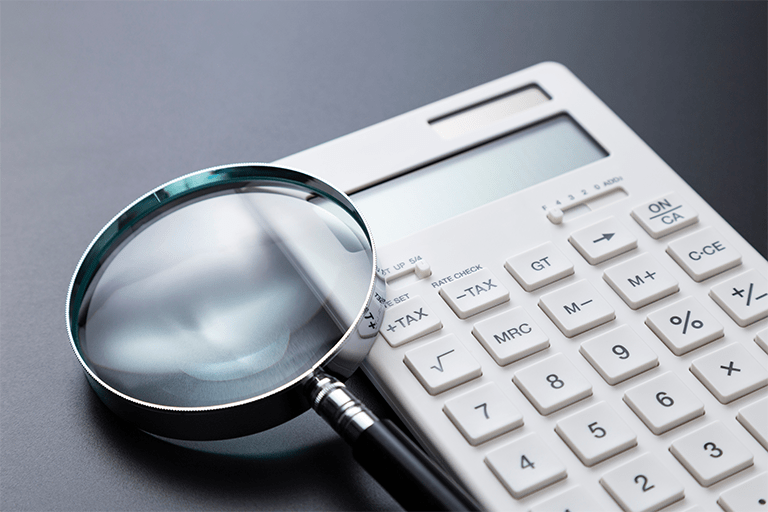
生命保険受け取りの際に税金がかかるかどうかは、保険商品の種類によって異なります。
ここでは、税金がかかる保険商品・かからない保険商品について解説します。
税金がかかる保険商品とは
ほとんどの生命保険商品は、以下のとおり保険金や解約返戻金に税金がかかります。
| 商品名 | 給付内容 |
|---|---|
| 死亡保険 | ・死亡給付金 ・解約返戻金 |
| 養老保険 | ・死亡給付金 ・満期保険金 ・解約返戻金 |
| 学資保険 | ・満期保険金 ・解約返戻金 |
| 個人年金保険 | ・年金(または一時金) |
また、上記保険商品でも、契約内容によって税金の種類が異なり、課税対象者も変わってきます。契約時には、税金の種類だけでなく、誰に納税義務が生じるか把握しておきましょう。
税金がかからない保険商品とは
生命保険のうち、医療保険やがん保険は給付金に税金がかかりません。
医療保険やがん保険の給付金は「身体の傷害に基因して支払いを受ける保険金」として、非課税扱いとなるためです。
第30条(非課税とされる保険金、損害賠償金等) 損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金
| 商品名 | 給付内容 |
|---|---|
| 医療保険 | ・入院給付金 ・手術給付金 ・特定疾病(三大疾病)給付金 など |
| がん保険 | ・診断給付金 ・入院給付金 ・手術給付金 ・抗がん剤治療給付金 ・放射線治療給付金<br> など |
ただし、医療保険やがん保険に特約で付加した死亡保険や生存給付金、健康祝い金は税金がかかります。
また被保険者(保険対象者)が亡くなり、遺族が未請求の保険金や給付金を受け取る場合は、相続財産として税金がかかるため注意が必要です。
【ケース別】生命保険にかかる税金の種類
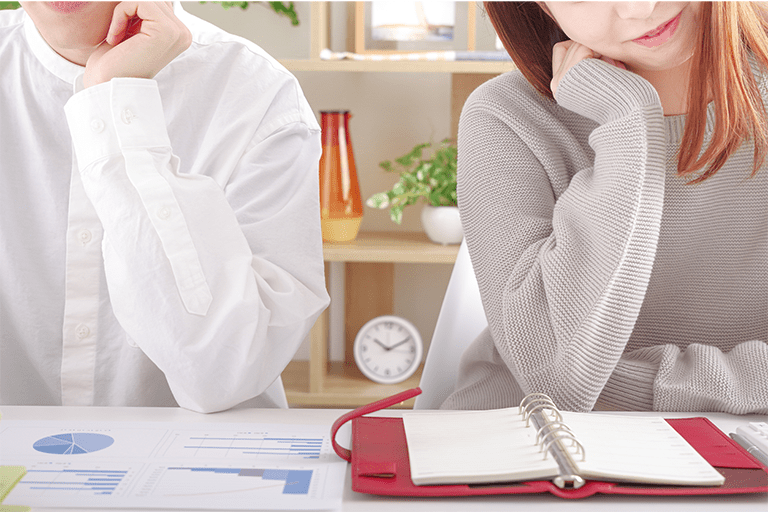
生命保険には、契約者(保険料負担者)と被保険者(保険対象者)、受取人の関係によって相続税・所得税・贈与税、いずれかの税金がかかります。
税金の種類により税負担が高額になる場合もあるため、加入する際は課税される税金の種類を押さえておくと安心です。
ここでは、契約ケース別に生命保険受け取りの際にかかる税金の種類を解説します。
契約者と被保険者が同一人物のケースでは相続税
契約者(保険料負担者)と被保険者(保険対象者)が同一のケースでは、受け取った生命保険金に相続税がかかります。
生命保険金は被保険者(保険対象者)の財産ではないものの、死亡を原因に生じる「みなし相続財産」とみなされ、相続財産と同様に扱われるためです。
【例】相続税がかかるケース
| 契約者 (保険料負担者) |
被保険者 (保険対象者) |
受取人 |
|---|---|---|
| 夫 | 夫 | 配偶者または子どもなど |
ただし、相続税は生命保険と他の相続財産を合算した金額が基礎控除額を上回った場合のみ課税されます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば亡くなった方に配偶者と子どもが3人いる場合、生命保険金を含めた相続財産が5,400万円を超えない限り、相続税はかかりません。
※基礎控除額=3,000万円+(600万円×4人)=5,400万円
契約者と受取人が同一人物のケースでは所得税
契約者(保険料負担者)と受取人が同一のケースでは、生命保険金は一時所得となり所得税がかかります。
支払った保険料と受け取った保険金の差額が利益とみなされるためです。
一時所得の金額 = 保険金額-支払った保険料-特別控除額(最高50万円)
【例】所得税がかかるケース
| 契約者 (保険料負担者) |
被保険者 (保険対象者) |
受取人 |
|---|---|---|
| 夫 | 配偶者 | 夫 |
ただし生命保険金を年金形式で受け取る場合は、雑所得として受け取った年ごとに所得税が課せられます。
所得の金額 = その年に受け取った年金額-年金額に対応する払込保険料
契約者と受取人が同一である場合、保険金の受け取り方によって税金の種類や計算方法、課税タイミングが異なる点に注意が必要です。
契約者、被保険者、受取人が全て違うケースでは贈与税
契約者(保険料負担者)と被保険者(保険対象者)、受取人が全て異なるケースでは贈与税が課税されます。
相続税ではなく贈与税が課せられるのは、契約者から受取人に「保険金受け取りの権利を贈与した」とみなされるためです。
【例】贈与税がかかるケース
| 契約者 (保険料負担者) |
被保険者 (保険対象者) |
受取人 |
|---|---|---|
| 夫 | 配偶者 | 子ども |
贈与税がかかる場合、保険料から控除できるのは基礎控除額110万円のみです。
贈与税の課税対象額 = 生命保険金 – 110万円(基礎控除額)
例えば、3,000万円の保険金を受け取るケースは、2,890万円が課税対象となります。
契約者・被保険者・受取人が全て違うケースでは、保険金が高額になると贈与税負担が大きくなるため注意が必要です。
死亡保険金の非課税枠とは?

生命保険の死亡保険金は非課税枠を利用できるため、相続税の軽減対策に活用できます。
死亡保険金の非課税枠とは、被相続人(亡くなった方)が残した死亡保険金のうち、一定金額まで相続税が非課税となる制度です。
※死亡保険金の非課税枠=500万円 × 法定相続人数
例えば法定相続人が4人いて3,000万円の死亡保険金を受け取る場合、2,000万円が非課税で、課税される金額は1,000万円となります。
※死亡保険金の非課税枠=500万円 × 4人=2,000万円
ただし非課税枠を利用できるのは、法定相続人が生命保険を受け取った場合のみです。
法定相続人以外を受取人に指定すると非課税枠の適用がなく、相続税を軽減できない点に注意が必要です。
税負担を軽減するポイント

生命保険は非課税枠や控除など税制の優遇を受けられるため、税負担の軽減に活用できます。
ただし契約内容や加入する商品によっては、税負担を軽減できない場合もあるため注意が必要です。
ここでは、生命保険を利用して税負担を軽減するポイントについて解説します。
保険料支払い時に「生命保険料控除」を利用する
生命保険は、保険料支払い時に生命保険料控除を利用すると税金(所得税・住民税)を軽減できます。
生命保険料控除とは、1年間に支払った保険料の一定額を年間の所得から差し引ける制度(所得控除)です。
例えば以下の場合に生命保険を活用すると、毎月支払う保険料が生命保険料控除の対象となり、税金負担(所得税・住民税)を軽減できます。
- 資産形成のために終身保険や個人年金保険を活用する
- 子どもの学費を貯めるために学資保険を活用する
生命保険料控除を受けるには、保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」を年末調整または確定申告で提出する必要があります。
生命保険料控除の金額は保険の契約時期や商品、年間保険料により異なるため、詳しくは保険会社へ確認してください。
贈与税は相続税や所得税に比べて税率が高いことに注意
生命保険は、以下のとおり契約形態(※)によって課税される税金の種類が異なります。
※契約者・被保険者・受取人の組み合わせ
| 保険料負担者 (契約者) |
被保険者 (保険対象者) |
保険金 受取人 |
税金の種類 |
|---|---|---|---|
| A | A | B | 相続税 |
| B | A | C | 所得税 |
| C | A | B | 贈与税 |
贈与税は相続税や所得税に比べて税率が高いため、税金負担の軽減を目的に生命保険を活用する場合は契約形態に注意が必要です。
例えば生命保険金1,000万円(基礎控除後の金額)を受け取る場合の税率は相続税が10%、所得税が33%、贈与税は40%です。
なお、子どもや配偶者へ資産を贈与する場合は、税金がかからない「贈与税の特例(※)」を利用できる場合もあります。
※住宅取得資金や教育資金の贈与など
「子どもや配偶者へ資産を贈与したい」「贈与税を軽減できないか」と考えている方は、税理士や税務署へ相談すると良いでしょう。
記事まとめ
生命保険は受け取る際に課税されるケースが多いものの、非課税枠や控除など税金の優遇を受けられるため、相続対策や贈与に活用できます。
ただし契約者や被保険者、保険金受取人の組み合わせによって、税金の種類や計算方法、税率が異なる点に注意が必要です。
税金面で不安がある方、税制の優遇をうまく活用したい方は、保険会社や保険代理店へ相談すると良いでしょう。
本記事をお届けした「保険のぷろ」では、無料で生命保険の加入相談を承っています。
生命保険への加入を検討している方は、ぜひ「保険のぷろ」へご相談ください。