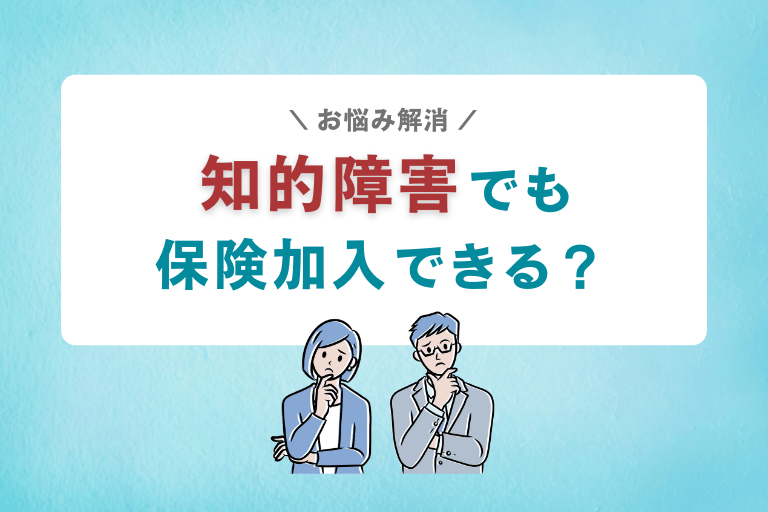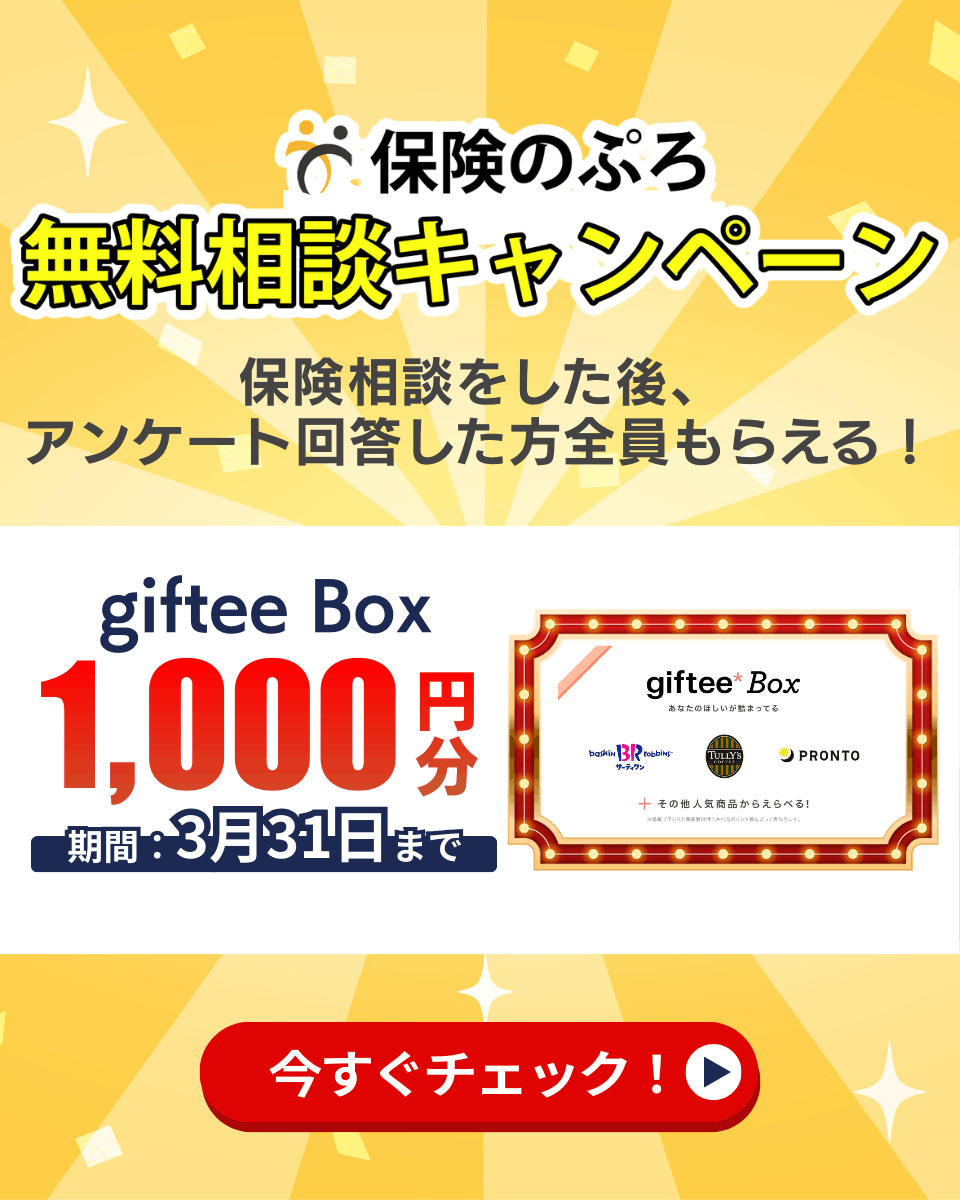生命保険が無駄と言われる理由、加入しない場合のリスクと選び方を解説
「生命保険は無駄だ」との意見を耳にしますが、本当に無駄なのか不安に感じていませんか。
生命保険は公的保障が整っていて、貯蓄や積立で備えられると考える方が「無駄だ」と考える方いるのが実情です。
しかし、自身に何かが起きたとき、遺された家族の生活や医療費、老後資金に不安を感じる方もいるでしょう。
今回は無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、生命保険が無駄とされる主な理由を解説します。本当に必要な保障を見極めるためのポイントを紹介するので、参考にしてください。
生命保険が「無駄」と言われる3つの理由
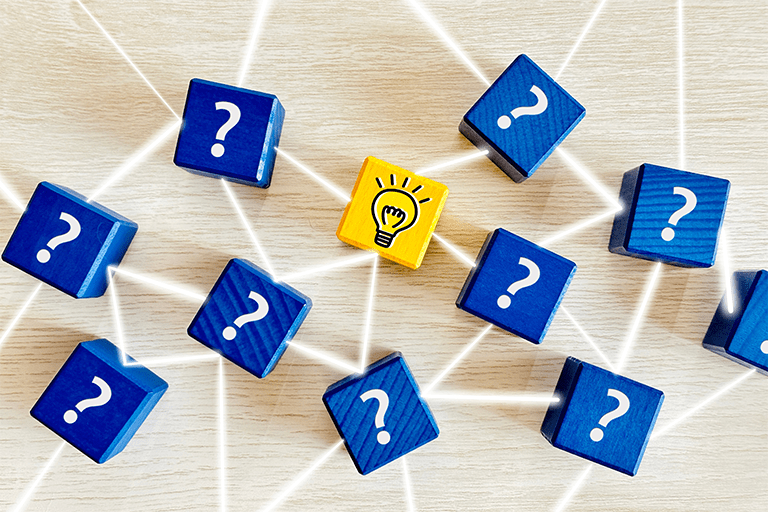
「生命保険が無駄」と言われる背景には、保障を取り巻く社会的な変化や、個人の備えに対する意識の変化があります。
ここでは、生命保険が無駄だと考えられる主な3つの理由を詳しく解説します。
公的保障が整っているから
公的保障が整っているため「生命保険は無駄」と言われる場合があります。
日本では、すべての国民が公的医療保険に加入する「国民皆保険制度」が導入されています。
「国民皆保険制度」とは、病気やケガで医療費が発生しても、自己負担は原則3割に抑えられる制度です。
また、一定の自己負担額を超えた場合は「高額療養費制度」で補助を受けられますが、公的保障だけで完全にリスクをカバーできるわけではありません。
医療費の自己負担がゼロになるケースはなく、遺族年金も子どものいない自営業者は受け取れないケースもあります。
制度の内容や限界を理解したうえで、自分や家族にとって生命保険は無駄なのかを判断しましょう。
治療費や入院費などを貯蓄で賄えるから
「治療費や入院費を貯蓄で賄えるなら生命保険は無駄」と言われるケースもあります。
生命保険は、病気やケガ、死亡などの事態に備えて、給付金や保険金を受け取れます。
しかし、日頃の貯蓄に加えて積立を活用している方にとっては、必ずしも加入が必要とは言えないのです。
予期せぬタイミングで発生する医療費は、想像以上に高額になる可能性もあるため注意が必要です。
保険金や給付金を受け取る可能性が低いから
保険金や給付金を受け取る可能性が低い場合「生命保険は無駄」と感じる方もいます。
「まだ若いし健康だから大丈夫だろう」と考え、給付をいつ受け取れるか分からないのに、保険料を支払うのはもったいないと感じるためです。
ただし若い方であっても、病気やケガのリスクがゼロとは言い切れません。
年齢別による入院率や死亡率を見ても、年齢が上がるほど数値は高まる傾向にありますが、若年層でも一定のリスクは存在しています。
以下のデータは、年齢階級ごとの入院受療率および死亡率になります。
| 入院受療率 | 死亡率 | |
|---|---|---|
| 20~24歳 | 141人 | 37.1人 |
| 25~29歳 | 198人 | 39.0人 |
| 30~34歳 | 246人 | 46.1人 |
| 35~39歳 | 257人 | 60.6人 |
| 40~44歳 | 273人 | 89.9人 |
| 45~49歳 | 345人 | 143.2人 |
※1年間で10万人のうち何人が該当したかを示す指標「人口10万対比」で算出している数値
参考:厚生労働省「令和2年(2020) 患者調査(確定数)の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kanja/20/dl/kanjya.pdf
参考:厚生労働省「令和3年(2021)人口動態統計月報年計(概数)の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai21/dl/gaikyouR3.pdf
さらに年齢を重ねたり病歴があったりすると、希望する保険に加入できなくなるケースもあります。
健康に不安が少ないうちに、将来へ備えて保険加入を検討する必要があるのです。
加入しない場合のリスクについて

「生命保険が無駄」と考えた方が生命保険に加入しない選択は、当然ながらリスクが伴います。
ここでは生命保険に加入しない場合、想定される主なリスクについて詳しく見ていきましょう。
自分が死亡した後、遺された家族が生活できなくなる可能性がある
「生命保険は無駄」と思い加入しないでおくと、自身が死亡したとき遺された家族が生活できなくなる可能性があります。
家族を失うと家計の収支バランスは大きく崩れ、遺された家族の生活が困難になる可能性が高くなります。
たとえ亡くなったのが収入のない専業主婦(主夫)でも、家事を担っていた分を家事代行サービスで補う必要が出てくる場合もあるでしょう。
公的年金制度の遺族年金は誰でも受け取れるものではなく、受給条件を満たさなければいけない点にも注意が必要です。
病気やケガの治療費・入院費が家計を圧迫する可能性がある
生命保険に加入しないと、病気の治療費や入院費が家計を圧迫する可能性もあります。
公的医療保険によって自己負担を軽減できるのは、あくまで保険が適用される範囲の医療費に限られます。入院時の差額ベッド代や食事代などは保険対象外で全額自己負担になるため、注意が必要です。
また、がん治療で保険適用外の先進医療を選ぶと、さらに高額な費用が発生する可能性があります。
治療期間が長引いたり、自由診療を希望したりする方は、医療費が家計に大きな負担となる場合も考えられます。
老後資金が足りなくなる可能性がある
生命保険は無駄と判断して加入を見送った場合、老後資金が足りなくなる恐れもあります。公的年金だけでは、老後の生活費を十分に賄えないケースが多いのが実情です。
さらに、年齢を重ねるにつれて医療費や介護費などの支出が増え、貯金が尽きてしまうリスクも考えられます。
一方で保険も預貯金にも頼れない状態では、老後の生活が不安定になる可能性が高まりまる点には注意してください。
今後加入したいときに健康状態で制限される場合がある
無駄だと思って生命保険に加入しないと、将来加入を希望した際に健康状態が理由で制限される場合もあります。
医療保険やがん保険に加入する際、健康状態に関する告知と保険会社の審査が不可欠です。体調や持病の状況によっては「入りたい」と思ったタイミングで生命保険へ加入できない可能性があるのです。
近年では、一定の告知項目を満たせば加入できる「引受基準緩和型」と呼ばれる保険もあります。
ただし持病で通常の医療保険に申し込めなかった方向けに設計されているため、以下のデメリットがある点も理解しておきましょう。
- 保険料が一般的な保険に比べて割高になる傾向がある
- 選べる特約が限られている
- 契約後しばらくのあいだは給付に制限がかかる場合がある
一般的な保険と比べて保障内容や条件に一定の制約があり、十分な補償を得られにくい点には注意が必要です。
無駄にしない生命保険の選び方
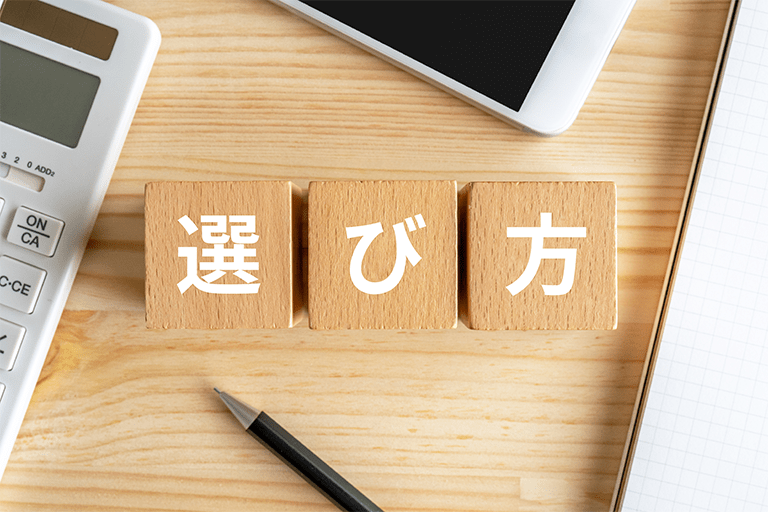
生命保険を「無駄だった」と感じる場合は、自身に合っていない保険を選んでしまったのかもしれません。
ここからは生命保険を有効に活用するために、押さえておきたいポイントを紹介します。
加入の目的を明確にする
生命保険を無駄にしないためには、まず加入する目的をはっきりさせる必要があります。
生命保険は予期せぬ事態が発生した際に、経済的な負担を最小限に抑えるための備えです。「どのような状況で誰がお金で困るのか」を明確にしないと、自身に合った商品を選べなくなる恐れがあります。
自身が死亡した際に家族の生活費を補いたい場合は、終身保険・定期保険・収入保障保険がおすすめです。
一方、病気やケガで長期間働けなくなるリスクに備えたいのであれば、就業不能保険や医療保険、がん保険などが選択肢に挙げられます。
加入目的を明確にすれば必要な保障が見えてくるため、不要な保険に加入してしまうリスクも抑えられます。
ライフステージごとに保障内容を見直す
生命保険が無駄だと感じないためには、以下のようなライフステージの変化に応じて保障内容を定期的に見直すことが重要です。
- 就職時
- 結婚時
- 出産・子育て
- 住宅購入時
- 子どもの独立後
- 老後・定年後
収入が安定し始めた段階で、医療費や不測の出費に備えた保険を検討しましょう。
また子どもが独立した後や老後には、医療・介護の備えを中心に保険を整えます。
老後や退職後など収入が減る時期には、医療費の負担は続くため、保障内容と保険料のバランスを見直す必要性が出てくるです。
保険は一度入ったら終わりではなく、ライフステージごとに「本当に必要な保障は何か」を見直すと、保障の重複を避け、無駄のない備えが可能です。
家計に負担のない保険料を設定する
無駄のない生命保険を選ぶ際は、家計に無理のない範囲で保険料設定が大切です。
手厚い保障でも、毎月の支払いが家計を圧迫するようでは、継続が困難になります。
毎月の支出に対して保険料が高すぎると、途中で解約せざるを得なくなったり、必要なときに保障を受けられなかったりするリスクが生じます。
反対に保険料が負担にならない範囲であれば、長く無理なく備えを続けられるでしょう。
自身のライフスタイルとバランスを考慮し、生活の妨げにならないような生命保険を選択しましょう。
生命保険はどんな人に向いている?

生命保険を無駄と考えるか、必要と考えるかは個人の家族構成や経済状況、ライフステージによって大きく異なります。
以下では、生命保険の必要性が高い人と低い人の特徴をそれぞれ解説します。
必要性が高い人の特徴
- 扶養家族がいる人
- 住宅ローンがある人
- 自営業・フリーランスの人
- 共働き夫婦でも家計が片方の収入に大きく依存している場合
生命保険の必要性が高い人は、自信がなくなることで誰かの生活に重大な影響が出る可能性がある人です。
例えば、配偶者や子供などの扶養家族がいる人は代表的なケースです。
また、自営業やフリーランスの人も公的な保障が会社員に比べて薄いため、自分で生命保険に加入してリスクに備える必要があります。
必要性が低い人の特徴
- 独身の人
- 十分な貯蓄・資産がある人
- 公的保障でカバーできると判断できる人
- すでに子どもが独立している高齢者
一方で、生命保険の必要性が低い人は、自分が亡くなっても経済的に困る人がいない人、別の手段でリスクに備えている人です。
特に、扶養家族のいない人は死亡保障の優先度は低く、必要だとしても葬儀費用などの最小限の備えで済む場合が多いです。
上記のような必要性の低い人が生命保険に加入しても、保険料支払いが無駄になったり、本来活用できたお金の機会損失などが生じる可能性があるため、十分に検討した上で判断するようにしましょう。
記事まとめ
生命保険が「無駄」と言われるのは、公的保障の充実や貯蓄で十分対応可能と考える方がいるためです。
しかし、加入しないと万が一の際に生活の維持が困難になったり、将来的に保険に加入したくても健康状態によって断られるリスクもあります。
生命保険を無駄にしないためには、加入目的の明確化やライフステージごとの保障内容の見直し、家計状況と合う保険設定が大切です。
自身で難しいと思ったら、気軽に保険会社やファイナンシャルプランナーなど、保険のプロに相談するのもおすすめです。
必要な保障を見極め、無理なく続けられる保険を選びましょう。