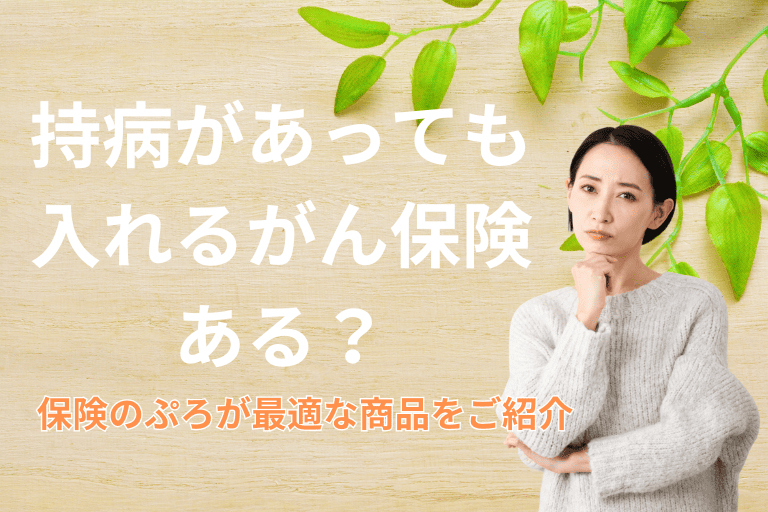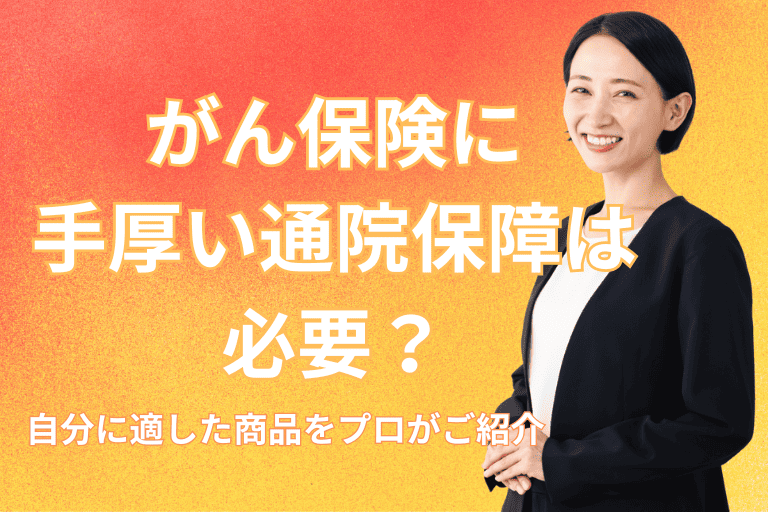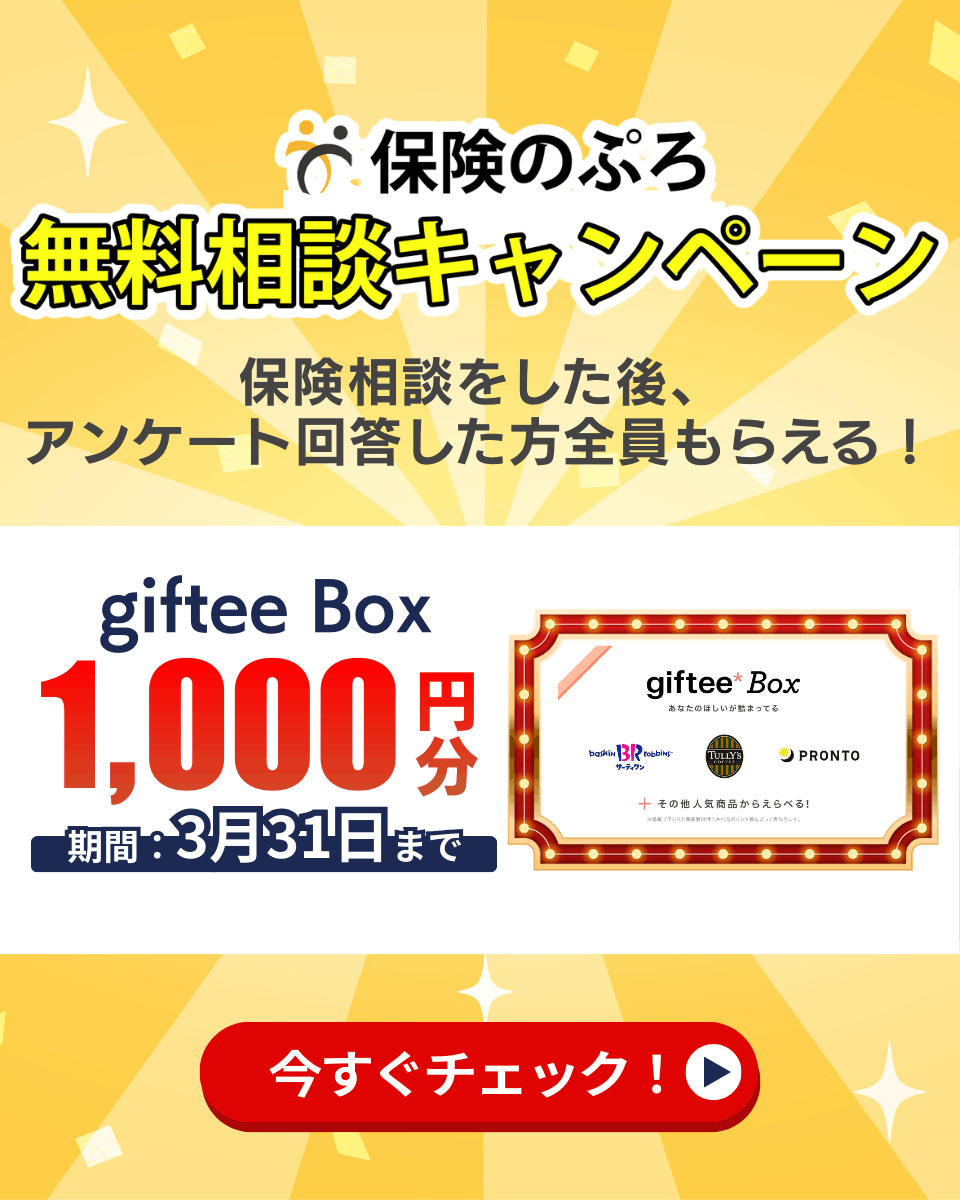がん保険は、加入者が将来的にがんを発症した際に、経済的なリスクを軽減するための保険なので、すぐに保障されない「免責期間」を設けられることが一般的です。
そのため、加入者は、すぐに保障を受けられない点を理解し、契約のタイミングや自身の健康状態に応じて備えることが大切です。
本記事では、がん保険を契約する前に知っておくべき「注意点」や「免責期間」を踏まえた上で、保険のプロが賢い保険選びをご紹介します。
がん保険がすぐに保障されない免責期間とは

がん保険の免責期間とは、契約をしてから一定の期間が経過するまで、保障が開始されない期間のことです。
多くのがん保険では、免責期間を90日間に設定しており、契約日または責任開始日から90日以内にがんと診断されても、保険金や給付金の支払い対象になりません。
免責期間は、保険会社が契約者の公平性を保ち、加入直後のリスクを防ぐために設けています。
免責期間中も保険料の支払いが必要
免責期間とは、契約をしてから一定期間が経過するまで、がんと診断されても保障の対象外となる期間を指します。
しかし、加入者は、保障されない免責期間であっても、契約はすでに成立しているため、保険料の支払い義務が発生します。
つまり、免責期間中は、給付金を受け取ることはできませんが、その間も通常どおり保険料を支払い続ける必要があります。
保障が開始するタイミング
がん保険の保障が開始するタイミングとは、契約を結んでから、一定の免責期間が経過した後に、保障が有効になる日です。
がん保険には、重要な日付である「契約日」と「責任開始日」があり、契約日から90日間経過した日または翌日(責任開始日)から、保険金の支払いが発生します。
また、保障が開始するタイミングは、契約日と初回保険料の支払い日で、異なる場合があります。
多くの保険会社では、初回保険料を支払った日または翌日が「責任開始日」となり、そこから90日間の免責期間をカウントします。
そのため、契約者は、契約書類や保険証券に記載されている日付を確認することで、保障がいつから有効になるのかを把握できます。
免責期間の短いがん保険をプロが無料でご紹介
がん保険がすぐに保障されない理由

がん保険がすぐに保障されない理由は、主に契約直後のリスク管理と、保険制度全体の公平性を維持するための「免責期間」にあります。
がんは、症状が出るまでに時間を要することが多く、契約前からすでに発症していることも少なくありません。
仮に、保険会社が、契約後すぐに保障を適用してしまうと、既にがんを発症していた人が保険金を請求できてしまい、他契約者との間に不公平が生じます。
そのため、がん保険は、免責期間を設けることで、契約後の新たなリスクに対してのみ、保障を適用する仕組みになっています。
最近では、免責期間を短縮した商品や、上皮内がんなどの初期がんに対してのみ、契約直後から保障するプランも登場しています。
しかし、これらは、例外的なケースであり、一定期間経過するまで保障されないのが一般的です。
がん保険の免責期間中に罹患した場合

契約者が免責期間中に罹患した場合は、契約時に発症していた可能性を考慮して、保険金や給付金の支払い対象にはなりません。
また、罹患している事実を隠して加入した場合には、告知義務違反とみなされ、契約が解除されるだけではなく、すでに支払った保険料も返還されません。
すぐに保障されないがん保険の注意点

保障が開始するタイミングや条件は、保険商品(会社)ごとに異なるため、契約前の確認が大切です。
ここでは、すぐに保障されない「がん保険の注意点」について、詳しく解説していきます。
保障を受けられない空白期間がある
がん保険には、契約日または責任開始日から、一定期間(一般的に90日間)保険金や給付金が支払われない「免責期間」が存在します。
契約者は、空白期間中でも保険料の支払い義務が継続するため、免責期間に保険料の支払いを止めてしまうと、契約が失効して再加入が必要になる場合があります。
再加入時には、健康状態によって加入できないこともあるので、空白期間中であっても、保険料を継続して支払うことが重要です。
保険を見直す際は空白期間を作らない
がん保険の見直しを行う際は、保障されない「空白期間」を作らないことが非常に重要です。
空白期間が発生した場合は、入院費や治療費などが全額自己負担になる可能性もあるため、契約の切れ目が生じないように、注意しながら手続きを行う必要があります。
空白期間を作らないためには、新しい保険契約の開始日を旧契約の終了日と同日、もしくは、それ以前に設定することが基本です。
また、保険会社によっては、見直しする方に向けて「引き継ぎ特約」や「新旧契約の同日移行」を提供している場合もあるので、安心して保障を受けられる状態を維持できます。
免責期間は保険会社によって異なる
がん保険の注意点としては、免責期間が保険会社によって、異なることを理解しておくことが重要です。
多くのがん保険では、免責期間を90日程度に設定していますが、保険会社や商品によっては30日から180日程度まで幅があり、免責期間の長さや適用条件が異なる場合があります。
さらに、一部の保険会社では、特定の疾病や診断内容(加入条件)に応じて、免責期間を短縮することもあります。
そのため、契約前には、免責期間の長さだけでなく、対象となる疾病や適用条件をしっかり確認しておくことが、加入後のトラブルを防ぎます。
プランによって保障の範囲が異なる
がん保険は、商品(プラン)ごとに保障内容が異なるため、同じ「がん保険」という名前であっても、カバーされる疾病の種類・診断給付金の対象・通院・入院・手術の保障範囲が変わります。
例えば、上皮内がんや初期のがんは、一部のプランで給付対象外になる場合もあり、契約者が期待する保障を受けられないこともあります。
そのため、がん保険を検討する際は、すぐに加入するのではなく、各プランの保障内容をしっかり比較する必要があります。
保障の範囲がプランごとに異なる理由としては、加入者のニーズに応じて、基本的な保障内容を抑えた低価格なプランから、入院・手術・通院・先進医療まで含めた手厚いプランまで、多数の選択肢を用意しているからです。
そのため、加入者は、自分のライフスタイル・医療リスク・予算に応じて、適切なプランを選ぶことが重要です。
また、保障範囲が広いプランは、保険料が高くなる傾向があるので、費用負担と保障内容のバランスを考慮することも大切です。
がんの罹患歴があると加入が難しい
がん保険は、加入者が将来的にがんを発症した際のリスクに備える保険なので、契約時に加入者の健康状態や既往症を審査します。
そのため、過去にがんを経験した人は、再発リスクが高いと判断されて、保険制度全体の公平性と持続可能性を保つために、加入を断られたり、条件付きでの加入になることがあります。
しかし、再発のリスクについては、がんの種類・発症時期・治療内容・経過によっても変わるため、一律に判断されるわけではありません。
また、保険会社によっては、罹患歴がある場合でも加入できる特別な保険商品や、罹患歴のあるがんを保障から除外する「条件付きプラン」も存在します。
これらのプランでは、過去に罹患したがんの保障を除外する代わりに、その他の「新たながん」や「治療」は通常通りの保障を受けることができます。
がん保険への加入を希望する場合は、自分の病歴や治療経過を正確に伝えて、保険会社が提示する条件をよく確認することが大切です。
免責期間の短いがん保険をプロが無料でご紹介
すぐに保障が開始するがん保険について

すぐに保障が開始するがん保険とは、契約を結んだその日、または、初回保険料の支払い後すぐに、保障が有効になるがん保険を指します。
即日保障型のがん保険は、免責期間を短縮または免除しており、契約直後から保障を受けられる点が特徴です。
最近では、加入者のニーズに応える形で、初期段階のがんや上皮内がんに対しても、すぐに保障される商品が増えてきています。
一方、即日保障型のがん保険は、商品ごとに保障内容や給付金の対象が異なるため、契約前に保障範囲・給付条件・保険料・加入対象年齢などを、しっかり比較検討することが大切です。
免責期間の短いがん保険をプロが無料でご紹介
がん保険を検討する際は「保険のぷろ」にすぐ相談を!

本記事では、がん保険を契約する前に知っておくべき「注意点」や「免責期間」について、保険のプロがご紹介してきました。
がん保険に加入する際は、自分のライフスタイル・リスク・予算に応じて、適切なプランを賢く選ぶことが大切です。
がん保険をお探しの際は、35社以上の保険会社を取り扱っており、保険のプロが多数在籍している「保険のぷろ」までご相談ください。