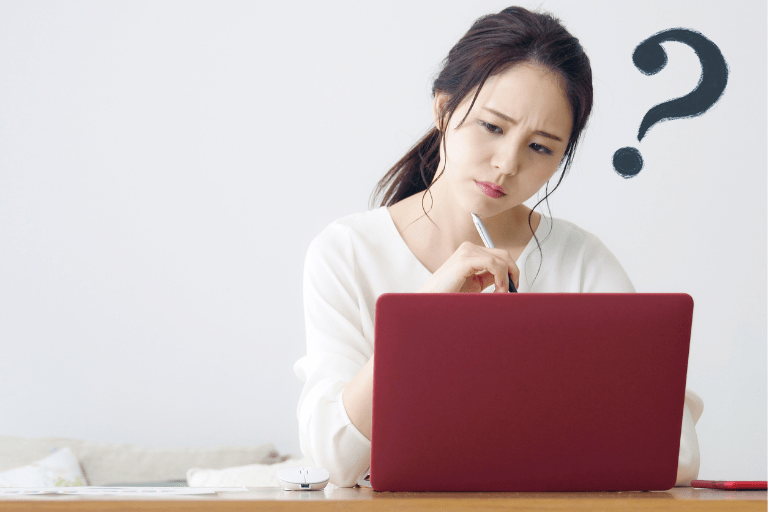医療保険・がん保険の違いと選び方のポイントを解説
「がん保険」と「医療保険」はどちらも医療費を保障するための保険商品ですが、それぞれの違いや使い分けのポイントがよく分かっていないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、がん保険の特徴と医療保険との違い、またがん保険を選ぶ際のポイントを解説します。
がん保険・医療保険と迷いやすい「三大疾病保険」の特徴やメリット・デメリットもまとめているので、合わせて参考にしてみてください。
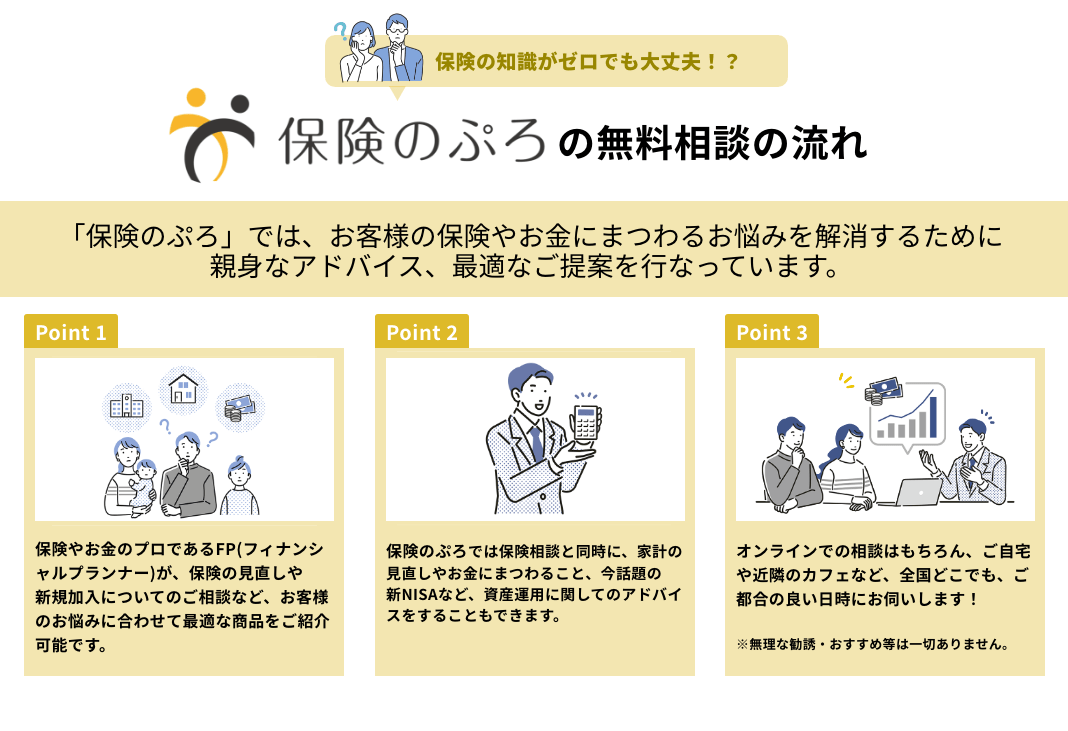
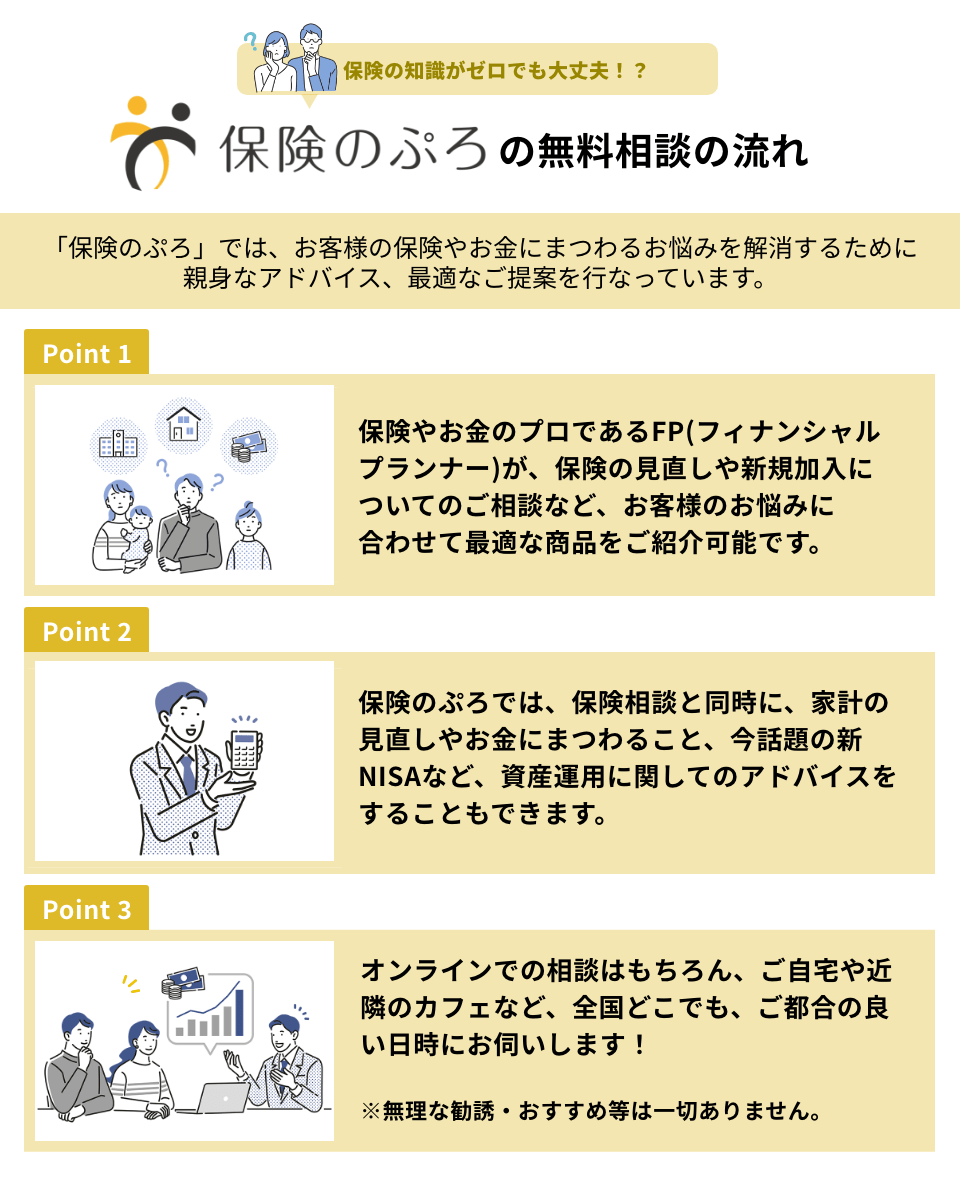
がん保険とは?医療保険との違いを確認

まずは、がん保険の概要と医療保険との違い・加入メリットについて詳しく見ていきましょう。
がん保険と医療保険の違い
がん保険とは、がん治療に伴う通院・入院・手術等の保障を受けられる保険商品のことです。
医療保険ががんを含むあらゆる病気やケガを保障するのに対し、がん保険はがんの保障に特化した内容となっている点が大きな違いです。
がん保険と医療保険の主な違いをまとめると以下のようになります。
| がん保険 | 医療保険 | |
|---|---|---|
| 保障対象 | がん | がんを含む病気やケガ |
| 保障内容 | 診断給付金(一時金)・入院保険金・手術給付金・通院給付金・ がん先進医療給付金 等 |
入院保険金・手術給付金・ 先進医療給付金 等 |
| 免責期間 | 90日間 | なし |
| 入院1回あたりの日数上限 | なし | 契約内容によって異なる (30日、60日、120日等) |
| 通算の入院日数上限 | なし | 契約内容によって異なる (1000日等) |
がん保険は診断給付金の支給があることと、入院給付金の支払い日数に上限がないことが主な特徴です。
医療保険にはこれらの保障がありませんが、別途「がん特約」をセットすることで同様の保障を受けられる場合があります。
がん保険の加入メリット
がん保険ならではの保障として、「がん診断給付金(一時金)」と「通院給付金」の2種類が挙げられます。
がん診断給付金(一時金)
がん診断給付金とは、がんの診断を受けた際に支給される給付金のことです。
近年はがんの場合でも長期入院が難しくなっており、入院給付金も全体的に減額の傾向となっています。
そのため、早期にまとまったお金を受け取れるがん診断給付金の仕組みは、がん保険における1番のメリットと言えるでしょう。
通院給付金
がんを患った場合、退院後も再発や転移を予防するために抗がん剤・ホルモン剤・放射線等の治療が必要です。
入院期間が短くなる一方で通院期間は長引きやすいというのが現状のため、通院に伴う給付金はがん保険を選ぶうえで重要なポイントの1つと言えるでしょう。
通院給付金は日額計算となっているものが多く、入院の有無に関わらず給付される商品等も存在します。
“仕事を続けながら通院でがん治療を行う”という新しい治療スタイルにも適応できることから、近年は通院給付金の充実度にも注目が集まっています。
がん保険への加入を検討した方が良いケース
がんは他の病気と比較して経済的リスクが大きいとされており、その理由として以下のような点が挙げられます。
- 先進医療等の保険外治療に頼る必要がある
- 化学療法の外来治療が長引いたり、再発・転移によって治療費が高額化したりする可能性がある
- 症状・治療の影響で仕事ができなくなり、生活に支障をきたす可能性がある 等
そのため、貯蓄に不安のある方や傷病手当金の支給がない自営業の方等は、医療保険よりもがん保険への加入を優先した方が経済的ダメージの回避に繋がりやすいでしょう。
一方、医療保険に加入済みの方で貯蓄も十分にあるという場合は、あえてがん保険に加入する必要はありません。
現在の貯蓄や収入の見込み、また家賃の支払いや子どもの教育費等、家計全体のお金の動きを踏まえてがん保険の必要有無を判断することが大切です。
三大疾病保険とは?がん保険・医療保険との比較

次に、がん保険・医療保険と並べられることの多い「三大疾病保険」について解説していきます。
三大疾病保険は、日本人の死因トップ3となっている「がん」「急性心筋梗塞」「脳卒中」を保障するための保険商品です。
- がん
- 急性心筋梗塞
- 脳卒中
以前は医療保険の特約としてセットするケースが一般的でしたが、近年は三大疾病の保障に特化した単独の保険商品が登場しています。
三大疾病保険の仕組み・特徴
保険金の種類と内容
三大疾病保険は主に以下の3つの保険金から構成される保険商品です。
| 特定疾病保険金 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中によって所定の状態 (診断後から60日以上にわたって労働制限を必要とする状態)になった場合に給付される一時金 |
|---|---|
| 死亡保険金 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中を含む病気や事故で死亡した場合に給付される保険金 |
| 高度障害保険金 | がん・急性心筋梗塞・脳卒中を含む病気や事故で 高度障害となった場合に給付される保険金 |
保険期間
三大疾病保険の保険期間は以下の3タイプに分けられます。
| 定期(年満了) | 10年や15年等の一定年数を保険期間とし、会社の規定年齢まで更新できるタイプです。 更新する度に保険料が高くなるのが一般的です。 |
|---|---|
| 定期(歳満了) | 「60歳まで」等、契約時に決めた年齢まで 保障が続くタイプです。 |
| 終身 | 一生涯にわたって保障が続くタイプです。 保険料は一定のため変わりません。 |
定期型は基本的に掛け捨てとなっており、保険期間内に三大疾病・死亡・高度障害状態のいずれにも該当しなかった場合は何も受け取れませんが、その分保険料が安いのが特徴です。
また終身型は解約や失効にならない限り保障が一生涯続くため、最終的には必ず保険金を受け取れます。
がん保険・医療保険との違い
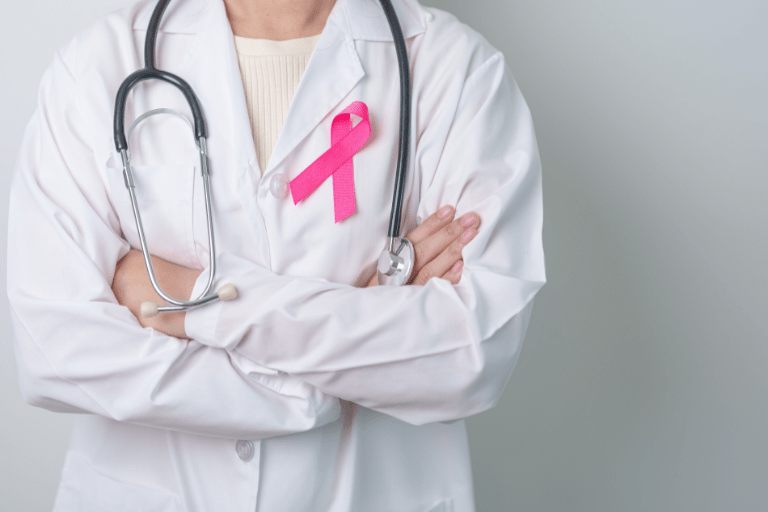
がん保険・医療保険と比較した場合の三大疾病保険の加入メリットとしては以下のような点が挙げられます。
- 一時金で治療費や生活費を補える
- 三大疾病以外でも死亡・高度障害の保障を受けられる
- 終身型保険なら三大疾病にならなくても解約返戻金を受け取れる
厚生労働省の「人口動態統計年報(2021)」によると、日本人の死因における三大疾病の割合は48.7%となっており、内訳はがん(悪性新生物)26.5%・心疾患14.9%・脳血管疾患7.3%という結果でした。
がんが第1位ではあるものの、心疾患や脳血管疾患の割合も決して低くないことが分かります。
三大疾病保険に加入すれば、心疾患や脳血管疾患の場合でも特定疾病保険金としてまとまった一時金が入るため、仕事の制限等で収入が減った場合の補てんが可能となります。
治療費には医療保険の保障を使用し、三大疾病保険は治療費の不足分や収入減少分をカバーするという使い方ができる点は三大疾病保険に加入する大きなメリットと言えるでしょう。
また三大疾病保険の死亡・高度障害保険金は三大疾病以外の病気・ケガも対象となるため、事故等を含む様々なケースに備えられるといった点も加入メリットの1つです。
三大疾病保険は支給要件が厳しいというデメリットも
様々な加入メリットがある三大疾病保険ですが、一方で保険金の支給要件が厳しいというデメリットも存在します。
三大疾病保険の保障は、保険会社が定める「所定の状態」になることが支給要件となっており、主な要件内容としては以下のようなものが挙げられます。
| がん(悪性新生物) | 上皮内がん(上皮内新生物)と悪性黒色腫以外の皮膚ガン、 また責任開始日から90日以内に罹患した乳がんは保障対象外 |
|---|---|
| 急性心筋梗塞 | 60日以上にわたって労働の制限を必要とする状態(家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動はできない状態)が継続したと医師に診断されたときのみ保障 |
| 脳卒中(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞) | 脳卒中と診断された日から60日以上にわたって運動失調・ 言語障害・麻痺が継続したと医師に診断されたときのみ保障 |
つまり三大疾病になったからと言って必ずしも保障を受けられるわけではないということです。
なお「所定の状態」については生命保険会社によって内容が異なるため、契約前に確認するようにしましょう。
保険の選び方と比較のポイント

ここからは、医療保険・三大疾病保険との違いを踏まえたがん保険選びのポイントを解説していきます。
がん保険はがん診断給付金+通院給付金の充実度で選ぶ
昨今のがん治療の傾向を踏まえると、「診断一時金 + 通院給付金(放射線、抗がん剤、ホルモン剤治療)の保障が充実した保険」を選ぶのがおすすめと言えます。
貯蓄が少ない方、勤務先の保障(傷病手当、健康保険からの一定割合還付等)が十分でない方、また妻が専業主婦の方等は、上記を基本にして医療保険だけではカバーできない保障を受けられるようながん保険に加入しましょう。
また医療保険に加入していない場合は、入院給付金や手術給付金の内容も確認すべきポイントとなります。
がん保険の特約は医療保険との重複に注意
医療保険とがん保険の両方に加入する場合は、特約の内容が重複しないように注意しましょう。
すでに医療保険に先進医療特約をセットしているのであれば、あえてがん保険にもセットする必要はありません。
がん保険の先進医療特約はがんのみを対象とした内容ですが、医療保険の先進医療特約はがんを含む幅広い病気を対象としているため、これから契約する場合は医療保険の方に特約をセットするのがおすすめです。
三大疾病保障は医療保険の特約を利用するのも1つ
医療保険・がん保険・三大疾病保険はそれぞれ特徴の異なる保険ですが、深く考えずに加入するとそれぞれの保障内容が重複してしまう可能性があります。
保障内容の重複は無駄な保険料の支払いに繋がるため、まずは現在加入している保険の内容を確認し、不足する部分を補い合えるような組み合わせを選ぶことが大切です。
また三大疾病に関する保障は医療保険の特約として提供している保険会社も多いため、単独では契約せず医療保険にセットする形で加入するのも1つの方法です。
記事まとめ

医療保険・がん保険・三大疾病保険はそれぞれに加入メリットとデメリットが存在します。
どの保険が適しているかは家族構成や職種等によって異なるため、収支のバランスや貯蓄状況を踏まえながら自身に合う商品を見つけることが大切です。
また日本は社会保障制度が充実しており、医療保険等に加入していなくても「高額療養費制度」や「障害年金」による手厚い保障を受けることができます。
医療保険等への加入は最小限に抑え、国の保障制度や貯蓄で備えるというのも1つの選択肢と言えるでしょう。
自身がどのような病気に備えるべきか、どのような保障を必要としているかをじっくりと検討し、きちんと納得したうえで保険契約を行うようにしましょう。